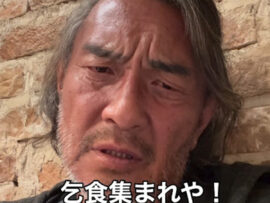認知症による行方不明は、高齢化社会の日本で深刻な問題となっています。この記事では、行方不明者の現状、その背景にある認知症の特性、そして私たちができる対策について詳しく解説します。愛する家族を守るために、ぜひ最後までお読みください。
行方不明の現実と家族の苦悩
2024年9月、大阪府和泉市在住の岡崎良子さんは、最愛の夫・洋さん(当時82歳)の行方不明という辛い現実と向き合わなければなりませんでした。6年前から認知症を患っていた洋さんは、自宅を出てから行方が分からなくなってしまったのです。 名前は言えるものの、住所や電話番号を忘れてしまっていた洋さん。良子さんは常に注意を払い、門扉にも鍵をかけていましたが、その日に限ってうっかり忘れてしまったことが悔やまれてなりません。「自分が目を離した隙にいなくなってしまった…」と、自責の念に駆られる良子さんの心中は察するに余りあります。
 岡崎洋さんの写真
岡崎洋さんの写真
洋さんは黄色のノースリーブに黒の短パン、黒のスニーカーという服装で、財布や身分証などは持っていませんでした。自宅マンション近くの防犯カメラには、坂を上がっていく後ろ姿が捉えられていましたが、その後の足取りは掴めていません。一日も早い洋さんの発見と無事の帰還を願うばかりです。
認知症行方不明の現状と増加の要因
警察庁の発表によると、2023年に届け出のあった認知症による行方不明者数は、過去最多の1万9039人に上ります。日本失踪者捜索協力機構(MPSジャパン)の柳学代表理事は、「約9割以上は発見されているものの、1割弱はまだ見つかっていない」と現状を語っています。
 認知症に係る行方不明者数の推移
認知症に係る行方不明者数の推移
認知症介護研究・研修東京センターの永田久美子副センター長は、行方不明者の行動は地理的条件によって大きく異なると指摘します。道路沿い、川沿い、山の中など、20km以上歩くケースもある一方で、ごく近所の意外な場所で発見されるケースもあるそうです。
厚生労働省の研究班は、認知症高齢者数は2040年には584.2万人にまで増加すると推計しています。また、永田氏は一人暮らしの高齢者の増加により、行方不明に気づきにくい状況も増えていると警鐘を鳴らしています。
認知症の特性と誤解
認知症は、日常の延長で始まり、少しずつ進行していくため、周囲が気づきにくいという特徴があります。行方不明者の約6割は軽度、あるいは診断前であるため、家族も気づかないまま警察に保護されるケースも多いそうです。
また、「徘徊」という言葉は、本人の意思とは関係なく歩き回ってしまう印象を与え、誤解を招きやすいことから、現在では使用を控える傾向にあります。実際には、散歩中にパニックになったり、脱水症状などで体調を崩したり、いつもと違う風景に戸惑って道に迷ってしまうケースが多いのです。
私たちにできる対策
認知症の行方不明を防ぐためには、どのような対策が有効なのでしょうか。永田氏は以下の4つの対策を推奨しています。
- 位置情報検索付き携帯電話の利用サポート
- 地域包括支援センターや地域住民との情報共有
- 自治体のSOSネットワークへの事前登録
- GPS機能付き機器の活用
特に軽度の認知症の方の場合、これらの対策を講じることで、行方不明のリスクを軽減できる可能性が高まります。
専門家の声
認知症専門医の佐藤先生(仮名)は、「認知症は早期発見・早期対応が重要です。少しでも異変を感じたら、ためらわずに専門機関に相談しましょう。また、家族や地域全体で認知症への理解を深め、支え合う体制を築くことが大切です」と述べています。
まとめ
認知症による行方不明は、誰にでも起こりうる問題です。この記事を通して、認知症への理解を深め、私たち一人ひとりができることを考えていただければ幸いです。岡崎洋さんのような悲しい出来事が二度と起こらないよう、社会全体でこの問題に取り組んでいく必要があります。
情報提供のお願い
岡崎洋さんに関する情報をお持ちの方は、一般社団法人日本失踪者捜索協力機構(代表番号0570-034-110)までご連絡ください。