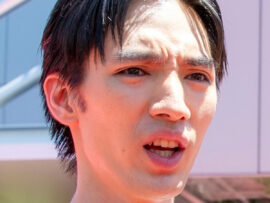日本の自動車整備業界は、大きな転換期を迎えています。休廃業・解散件数が過去最多を更新し、多くの事業者が厳しい状況に立たされています。この記事では、その現状と課題、そして未来への展望について詳しく解説します。
自動車整備業界の現状:倒産・廃業の増加
帝国データバンクの調査によると、2024年度の自動車整備事業者の休廃業・解散件数は382件と過去最多を記録。倒産件数を含めると、445件もの事業者が市場から姿を消しました。
 自動車整備業界で淘汰が加速している様子
自動車整備業界で淘汰が加速している様子
この背景には、部品価格や人件費の高騰、少子高齢化による顧客の減少、整備士不足など、複合的な要因が絡み合っています。2024年度の調査では、26.2%の事業者が赤字、さらに半数以上が業績悪化を経験しているという厳しい現実が浮き彫りになりました。
整備士不足という深刻な課題
特に深刻なのは、慢性的な整備士不足です。若者の車離れや高齢化の影響で、整備士のなり手が減少。人手不足は納期の遅延や受注制限に繋がり、事業者の収益を圧迫しています。自動車整備士専門学校の講師、山田太郎氏(仮名)は、「若者に整備士の魅力を伝え、育成していくことが業界の未来にとって不可欠」と指摘しています。
電動化・先進技術への対応も急務
電気自動車(BEV)やハイブリッド車(HV)、先進運転支援システム(ADAS)搭載車など、自動車の技術革新は急速に進んでいます。しかし、街の整備工場では、これらの最新技術に対応できる設備や人材が不足しているのが現状です。そのため、顧客がディーラーに流出してしまうケースも少なくありません。
 自動車整備業の倒産・休廃業解散件数の推移
自動車整備業の倒産・休廃業解散件数の推移
保険修理単価の抑制も収益悪化の一因
自動車保険を使った修理の単価抑制も、整備工場の経営を圧迫する要因となっています。整備コストは上昇しているにも関わらず、保険会社からの単価引き下げ圧力が強く、利益を確保することが難しくなっています。
未来への展望:業界の取り組みと生き残りの鍵
こうした厳しい状況を打破するため、業界全体で様々な取り組みが始まっています。大手自動車メーカーによる整備士教育への連携や、整備代金の単価引き上げに向けた動きなど、明るい兆しも見え始めています。
自動車整備業界の専門家、佐藤花子氏(仮名)は、「今後、生き残るためには、最新技術への対応、顧客ニーズの多様化への対応、そして優秀な人材の確保が不可欠」と述べています。
変化の激しい時代において、自動車整備業界は大きな岐路に立っています。それぞれの事業者が、時代の変化に柔軟に対応していくことが、未来への活路を開く鍵となるでしょう。