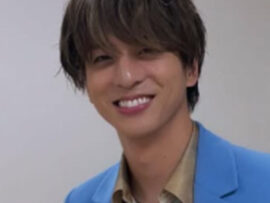首都圏などの都市部で、マンション価格の高騰が続いている。夫婦とも有名な大企業で働くパワーカップルでさえも「高すぎて、とても買えない」という声が増えてきた。
今後の人口減少が確実な日本では、住宅の需要は減っていくはずなのに、マンションの新築は継続し、その価格も上がり続けている。
建設費の高騰がその理由の1つだが、そもそも購入する側の数が減少するのなら、建設自体に歯止めがかかるはずだ。しかし、そうなっていないのは、何かおかしな「横やり」が入っているようにも思える。
◾️タワマン規制で持続可能な神戸市を
神戸市は2020年から三宮や元町などの中心部で、条例によって建物の容積率のうち住居系用途の部分に上限を設定し、事実上高層タワーマンションの建設ができないようにしている。
神戸市でも全国的な傾向と同じく、マンションの価格は上昇し続けていたが、それだけでなく、最近の調査で住民登録のない部屋がかなりの割合で存在することが明らかとなった。
確かに、生活に便利な市街地の中心部にタワマンが建てば人口は増える。ところが、神戸市の方針はその真逆を行っている。神戸市がそう考える理由は、この街の成り立ちを考えるとクリアに理解できる。
東京、大阪、名古屋、京都、福岡といった他の大都市と較べると、神戸の歴史はそれほど長くはない。神戸は1868年の明治の開港に始まり、国際港湾である神戸港を中心に製造業や卸売業などが集積、第二次世界大戦前後の急成長を経て、日本を代表する都市となった。
それゆえ、瀬戸内海と六甲山に挟まれた東西に長い市街地が広がり、その北や西につくられた住宅団地、それらの合間を縫うように森林や里山が広がるという特色を持つ。都市部と郊外の住宅地、そして緑豊かな自然の3つが、コンパクトなエリアに集まっているのが魅力ともいえる。
であれば、この恵まれたバランスを崩しかねない、中心部でのタワマン建設を避けたいと考えるのは当然の判断だ。特に三宮や元町エリアは、買い物や食事、アートシーンといった「非日常」が楽しめ、日々の仕事をするオフィスエリアとしての利用が優先されるべきなのだ。
一方で、戦後の高度成長の時代に郊外につくられた住宅団地は、都心部と鉄道インフラがうまく結節している。住宅街もリニューアルして、適切に新陳代謝ができれば、将来的にもバランスのとれた真に持続可能な神戸が維持できる。
◾️高層タワマンは廃墟化する可能性も
そのようななか、神戸市は昨年5月からタワーマンション自体が地域社会にもたらす問題を深掘りしようと、有識者会議を開催していた。そして今年2月にその会議での意見が最終報告書としてまとめられた。
報告書によると、神戸市内のタワマンを調査したところ、低層階と高層階の居住者の平均年齢はいずれも約48歳と差はなかった。ところが、住民1人当たりの平均年収(所得から換算)でみると、低層の1階から9階では448万円だが、40階以上では1032万円と2.3倍となり、大きな差があることが明らかになった。