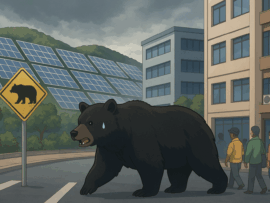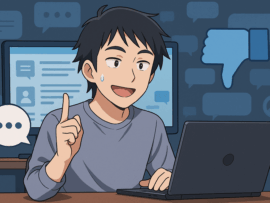[ad_1]
10年以上にわたって全国で争われてきた集団訴訟が、今年6月、最高裁での判決言い渡しというクライマックスを迎えると見られる。それは、2013年8月に実施された「生活扶助基準引き下げ」の取り消しを求める集団訴訟「いのちのとりで裁判」。
これまでに原告が地裁で19勝11敗、高裁では7勝4敗と、大きく勝ち越している。
公権力側が有利といわれる行政訴訟では、異例のことといわざるを得ない。その理由は、裁判を通じて国側の露骨な「不正」が明らかになったことにある。その「不正」は国側の「オウンゴール」を招いてきた。最高裁判決を前に、裁判の経緯を振り返ろう。(みわ よしこ)
それは、“自民党の公約”から始まった
2012年12月、衆議院選挙によって自民党が圧勝し、民主党政権から自民党政権への政権交代が行われることとなり、第二次安倍内閣が発足した。
自民党の選挙対策の目玉の一つは、生活保護基準のうち生活費分(生活扶助)を10%引き下げ、不正受給に厳しく対処することであった。
生活保護が「ゼイタク」と言えるほどの生活水準を保障していた時期はない。金額ベースで0.5%程度の不正受給が、いわゆる“本当に困っている人”を苦しめていたという事実もない。
しかし、「ゼイタクすぎる生活保護のせいで、私たちの税金が無駄食いされる」「不正受給のせいで、本当に困っている人に助けが届かない」といった言説の人気に対して、ファクトはあまりにも無力だ。
さらに、2012年4月からゴールデンウィークにかけてメディアをにぎわせた「人気お笑い芸人の母親が生活保護受給」というメディアスクラムと世間の反応も重なった。お笑い芸人と母親の対応には違法性は全くなかったにもかかわらず、「炎上」の格好のターゲットとされた形であった。
結果として、生活保護基準を引き下げて利用しにくくする“正義”を掲げた自民党は、年末の総選挙で勝利した。そして2013年1月、厚生労働省は生活保護基準の引き下げ方針を示した。
引き下げ幅は、全国平均で6.5%。自民党の当初案「10%」よりは少なく抑えられたが、それでも生活保護世帯にとっては大打撃だ。
この方針は、同月に取りまとめられたばかりの社会保障審議会・生活保護基準部会(以下、基準部会)の報告書を参照して決定されているべきものだった。しかし、引き下げ幅のうち87%分の根拠である「デフレ調整」は、報告書のどこにも書かれていなかった。
[ad_2]
Source link