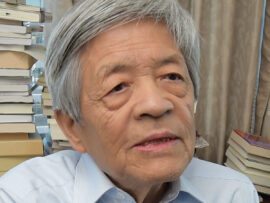京都府で観光公害が深刻な問題となる中、2024年にはついに同府を訪れる外国人観光客数が日本人観光客数を上回った。政府がインバウンド年間6000万人という高い目標を掲げる一方で、急増する観光客、すなわちオーバーツーリズムに圧迫される地元住民の不満と疲弊は頂点に達している。かつて「千年の都」と称賛された古都は、今や世界中からの観光客にとって外せない訪問先となり、その代償として市民生活のインフラ機能が麻痺し始めている現状を、現場の声から探る。
交通インフラの機能不全:バス・電車・車の利用困難に
京都市民が最も切実に訴えるのは、生活に不可欠なバスや電車といった公共交通機関が使い物にならないという点だ。京都駅から清水寺・祇園方面へ向かう主要系統である206系統や、四条河原町方面の205系統などのバスは、大型スーツケースを持ったインバウンド観光客の長い行列で乗車自体が困難になっている。これにより、地元住民が通勤や通学で日常的にこれらのバスを利用することは、ほぼ不可能になったと言える。
京都市は混雑緩和策として、2023年から観光特急バスを導入したが、週末限定の運行であり、平日における深刻な混雑や交通渋滞の緩和には繋がっていない。状況は悪化の一途をたどるばかりだ。「もう外に出られへん。まずバスに乗れないし、もし乗れても身動きがとれず、毎回『降ります!』って大声で叫ばないと降りられないのが本当にしんどい」と話す50代の女性は、そのストレスから外出そのものを控えるようになった。また、「墓参りに行こうとしたらバスに乗れず、何台か見送らざるを得なかった」という40代男性の声もある。
電車でも、改札口での混乱や列車の遅延が常態化しており、「大事な予定に間に合わないことが増えた」という会社員からの不満も少なくない。さらに、「私が指定席券を購入した特急列車の座席に、外国人観光客グループの一人が勝手に座っており、しかも正規の乗車券を持っていなかった」という、ルール軽視の事例も報告されている(50代男性)。加えて、市内の車道では、レンタサイクルを利用する外国人観光客が道幅いっぱいに広がって走行するため、「追い越しができずイライラする」「車での移動にかかる時間が読めなくなった」と、自動車通勤者や配送業者など、あらゆる移動手段を使う市民生活や経済活動に深刻な影響が出ている。
 京都・四条大橋に密集する外国人観光客。交通インフラへの負担増を象徴する光景。
京都・四条大橋に密集する外国人観光客。交通インフラへの負担増を象徴する光景。
歴史的景観と文化遺産の荒廃:民泊とゴミ問題
京都観光の大きな魅力である神社仏閣や歴史的な街並みも、観光公害による荒廃が進んでいる。主要な観光エリアである洛中・洛北では、築100年を超える伝統的な京町家が次々と民泊施設に転用されている。しかし、これらの民泊施設は管理が行き届いていないケースが多く、宿泊客の増加が周辺環境の悪化を招く悪循環が生じている。ある40代の男性住民は、「隣の民泊でボヤ騒ぎがあった。どうやら軒先で花火をしたらしい。木造建築だから、もし燃え広がったら一帯が全焼するんじゃないかと、本当に不安だ」と、火災リスクへの懸念を口にする。
一方、寺社仏閣が多く集まる祇園や東山エリアの境内では、ペットボトルや空き缶などのゴミをその場に捨てていく外国人観光客が後を絶たず、清掃作業の負担は限界を超えている。多くの寺の住職たちの間では、「本来、静かで神聖であるべき参拝空間が、ただの“撮影スポット”に成り下がってしまった」という嘆きが広がっている。ある寺の僧侶は、現状についてこう述べる。「東アジアからの旅行者はまだ比較的マナーを守る方ですが、円安の影響もあり、日本の文化や宗教に対する理解がほとんどない欧米からの低所得層の観光客が増えたせいか、境内の雰囲気が一気に悪化しました。平気でご本尊の前で蓋が開いた飲み物を片手に大声で騒いだり、前庭に座り込んだりするので、地元の方がお参りする際の妨げになっています。その上、お賽銭も入れず、お守りやお札なども買わずに帰っていくので、寺社側としては収入にならず、清掃などの負担だけが増える一方です」。八坂神社には、昨年、観光客と住民間の摩擦を受けて注意書きが設置されるなど、具体的な対策も講じられているが、抜本的な解決には至っていない。
まとめ
京都市におけるインバウンド観光客の急増は、政府が掲げる観光立国目標の一方で、市民生活の基盤である交通インフラの機能不全や、大切にしてきた歴史的景観、文化遺産の荒廃という深刻な代償をもたらしている。住民からは「もう外に出られない」という悲鳴にも似た声が上がり、静かで秩序ある古都の姿が失われつつある現状は、早急な対策が求められている。オーバーツーリズムの問題は、単なる観光客のマナー問題に留まらず、都市の持続可能性、住民のQOL(生活の質)、そして文化財保護という多岐にわたる課題を突きつけている。