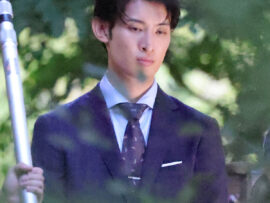東武鉄道は長年、大きな問題に頭を悩ませてきた。それは、東武鉄道における重要駅「浅草駅」の不便さだ。浅草駅は駅ホームが短く、長い編成の通勤列車に対応できないほか、浅草駅で乗り換えられる地下鉄が主に「東京メトロ銀座線」になってしまい、都心へのアクセスに限界がある。駅の不便さは、街の魅力低下にもつながりかねない大きな問題だが、東武鉄道はこの問題にどう対処しているのか。
東武鉄道は「ちょっと独特」と言えるワケ
東武鉄道は、多様な性格を持つ鉄道会社だ。関東を中心に東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県にまたがる鉄道網を持ち、鉄道事業を中核に、バス事業、不動産開発、商業施設運営、観光事業などに多角的に取り組む企業だ。
江戸時代からの繁華街・浅草をターミナル駅とし、複々線区間から複数の地下鉄に乗り入れがあるなど都心への通勤にも便利な一方、栃木県や群馬県まで特急を運行しているなど、他の鉄道会社とはやや異なる性格を持つ。また、東上線系統の路線もあり、地域輸送を担うローカル線としての役割も果たしているのだ。
営業エリアは広域ゆえ、ちょっとしたJRくらいの存在にはなっている。閑散路線もあれば、稠密路線もあり、線区ごとに事情がある。それゆえに面白い、とも言える鉄道会社なのだ。
新宿・渋谷じゃない…東武鉄道の重要駅が「浅草」である理由
そんな東武鉄道の現状を形作っているのが、伊勢崎線(東武スカイツリーライン)のターミナル駅となっている浅草駅の存在だ。この東武鉄道の核とも言える浅草駅は、時代の変化とともにターミナル駅として機能しなくなっていたのだ。
もともと浅草エリアは戦前、新宿や渋谷などとは比較にならないほどの繁華街だった。浅草寺を中心にさまざまなお店が集まり、寄席などもあり、日々の楽しみの一大集積地だった。
そんな下町の中心として多くの人が集まる浅草に、1931年5月東武鉄道は乗り入れた。この地に、頭端式ホーム(とうたんしき:直通運転の仕様とは異なり、行き止まりがある終点駅のホーム)のターミナル駅をつくったり、百貨店の入るビルも併設したりすることで、東武鉄道は繁栄することを目指していたのだ。
創業時は北千住発着だったものが、業平橋(現在のとうきょうスカイツリー)まで延伸、虎視眈々と浅草への乗り入れを狙った。そしてそれは成功したのだった。
しかしその後、東武鉄道のターミナル駅・浅草は、時代の変化とともに衰退していき、乗客視点で見ても「不便さ」の際立つ駅となってしまった。このターミナル駅の問題は、浅草エリアの街自体の魅力低下にもつながりかねないほど深刻であった。東武鉄道はどう対処したのか。