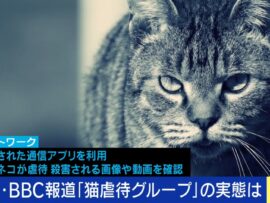1月からの「ネズミソ汁」騒動で話題を呼んだすき家。
騒動の余波は長引き、ほぼ全店を数日間閉鎖したり、24時間営業を廃止して店の清掃を行うなどの対策が取られるまでになった。店舗の閉鎖に営業時間の短縮。こう聞くと当然、「売上減」がちらつく。
【画像】最近のすき家では容器の「ディストピア化」も進んでいる?
しかし、蓋を開けてみればその予想は大きく外れた。すき家の4月全店売上高はわずか2割減で済んだのだ。ここには、すき家の持つ「強さ」と、「そうならざる得ない」日本の現状がある。
■「売上高2割減」は「むしろすごいこと」
最初に指摘しておきたいのは、「売上高2割減」は、かなり「軽微な傷」で済んでいるということだ。各種報道では「2割の大減少」と報じられているが、この程度で済んでいることにもう少し注目すべきである。
単純比較はできないが、2015年1月に異物混入が発覚したマクドナルドの同月の売上高は前年比38.6%減であり、今回のすき家のほぼ2倍。しかも、すき家は3月31日〜4月4日の午前中までほとんどの店舗を閉鎖。さらに4月5日からは24時間営業を23時間営業にしているので、単純計算でこれまでの月と比べて4日ほど営業時間が少ないのだ。
1カ月のうちの4日は、割合にして13%ほど。それだけでも単純計算で13%の売り上げ減になるはずだが、全体では20%程度の減少で済んだのだ。
そもそもすき家の業績は事件前の段階で非常に好調だった。先日発表された2025年5月期決算では、すき家を有するゼンショーホールディングスが、外食企業として初の売上高1兆円を記録している。
すき家だけを見ても、売上高は前年同期比で11.5%増、営業利益は前年同期比で32.4%増になっている。
こうした事件以前からの好調ぶりもあって、予想よりも軽微な影響で済んだのだろう。
ちなみにゼンショーの予測によれば2025年上期は減益予想を立てているが、下期では再度増収予想を行っている。上期の減益はネズミ混入事件の余波だろうが、その復活もすでに見込んでいるわけだ。
ここからわかるのは「私たちは思っているよりも、すき家を使っている」という単純な事実だ。
■愛されすぎている「すき家」
すき家が愛される理由はどこにあるのだろうか。ここにはポジティブな理由とネガティブな理由の2つがある。