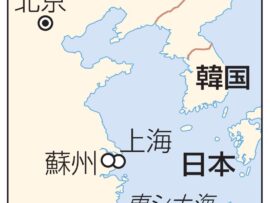犯罪の動機と行為が結びついていない。そんな事件が増えているように感じる方も多いことだろう。
【写真を見る】養老孟司さんが「子どもに投資を教えるなんて“アホ”」と言うワケ
東京メトロ・東大前駅で切りつけ事件を起こした容疑者は、「教育熱心な親たちに度がすぎると犯罪を犯すと示したかった」と供述しているという。その主張も行為も一般的に理解されないであろうことは言うまでもない。
この種の犯罪者は、何らかの病気を抱えている場合もあるだろうが、身勝手な自己アピール、自己顕示欲が動機となっている面もありそうだ。主張を世界に発信するためにSNSではなく犯罪という手段を選んだわけである。
『バカの壁』で知られる解剖学者の養老孟司さんは、新著『人生の壁』の中で、「自分の重みを無理にアピールする人間が極端な行動に走るのではないか」と指摘している。
そのうえで、他人とかかわって生きることの大切さを説く。
養老さんの話を聞いてみよう(以下、『人生の壁』より抜粋・引用)
***
自分とは中身のないトンネルのようなもの
ドイツの若い哲学者でトーマス・メッツィンガーという人がいます。彼は著書の中で、自己とはトンネルである、と述べています(『エゴ・トンネル 心の科学と「わたし」という謎』原塑・鹿野祐介訳、岩波書店)。
トンネルというのは壁だけがあるけれども中は空(から)です。空ではないとトンネルとしては使えません。
要は、自分なんて空っぽだというのです。面白いのは、この考えが老子と共通している点です。老子は、部屋は中が空でないと使えないと述べています。
現代人、とくに若い人は、おそらくトンネルの中身があると、よく考えないで信じ込んでしまっているのではないか、と思います。その中身のほうを「自分」と呼んで、実体があると思い込んでいる。
その中身が詰まっているほど充実しているという勘ちがいがそこから生まれます。確固とした「個性」があり、それこそが自分の本質だと考えている。でも、実はそうではなくてあるのは壁だけ、確実にあるのは身体のほうです。
仏教もまた、自分なんか無い、ということを昔から教えてきました。「無我(むが)」です。そういう仏教が今は人気が無くなってきているのも理解できます。今の人の考えとはまったく正反対だから受けないのでしょう。
一方で、一神教の世界では、「自分」というものが一貫して存在することを前提としています。最後の審判で、それまでの人生をすべて裁かれるというのはそういうことでしょう。生まれた時から死ぬ時まで一貫した本質的な「自分」があるとしないと、最後に裁かれることを納得できるはずがない。
しかし、3歳の時の自分と80歳の時の自分が同じはずがない、というのが日本人の普通の感覚ではないでしょうか。
キリスト教やイスラム教はそんなことは考えもしません。本質的な「自分」が存在しているという前提の上に成り立っています。だから無我なんて聞けば、「なんだそれ」と思うでしょう。
そこで興味深いのが、メッツィンガーです。西洋人である彼は考えに考え抜いたうえで「トンネルだ」という結論に至ったのでしょうが、実はそれは仏教がずっと言ってきたことでした。一貫した自分なんてない、という考えはもともと日本では比較的すんなり受け止められてきたはずなのです。一方で、そういう考え方は、一神教の側から見ればいい加減に映ることでしょう。
でも、「最後に神の前に出るのは誰だよ」という質問に彼らはどう答えるのでしょうか。仮にそういうことになった時に、神の前に立つのは何歳の時のあなたなのか。