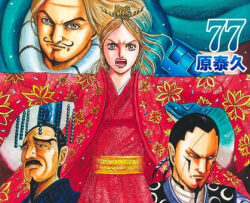江藤拓農林水産相が「私はコメを買ったことはありません。支援者の方がたくさんくださるのでまさに売るほどある」などの発言で5月21日に事実上更迭され、後任に小泉進次郎氏が任命された。
小泉氏は、将来の総理として期待され、昨年9月の自民党総裁選にも出馬したが、雇用流動化を巡る発言などによって国民の評価が低下してしまった。小泉氏に対しては生煮え、準備不足との批判が付いて回り、他候補や野党から、「労働解雇規制を緩和する」という発言を〝首切り自由化政策〟などと攻撃され、失速した(これについては、本欄2024年9月13日「<検証>自民党総裁選候補の9人の経済政策、日本経済を救う尖ったアイデアは洗練されるのか」参照)。結果、小泉氏は、総裁選の第1回投票で3位に終わり、決選投票に残れなかった。
小泉氏が、国民に関心の高いコメ価格高騰問題を解決すれば、国民の評価が回復することは間違いない。また、人気低迷に悩む石破茂内閣としても、政策面での評価を高め、選挙応援力で群を抜く小泉大臣の存在を参院選対策でも有効に活用できるだろう。しかし、そのためには、いくつかの〝壁〟が存在している。
コメの価格が下がらない理由
なぜコメの価格が下がらないかと言えば、実は、自民党の農水族や農協がコメの価格を下げたくないからだ。これまで、生産調整などによって何とかコメの価格を下がらないようにしてきたのに、たまたま上がってくれた。これを下げようという気がないのは当然だ。
しかし、コメの価格を下げるのは簡単である。需要よりも供給を増やせば良い。そのためには、備蓄米の放出、コメの増産、コメの輸入の3つの方法がある。
備蓄米の販売については、買い戻し条件が付いている。売った後に買い戻すのであれば、現在供給が増えても将来供給が減ることになる。農水省の言い分としては、備蓄米は元のレベルに戻しておかなければならないのだから、買い戻し条件が付いているのは当然だということになる。
これでは備蓄米を買った業者も安心して売ることはできない。つまり、供給は増えない(熊野孝文「これは暴動が起きるレベル…上がり続けるコメ価格、なぜ備蓄米放出でも下がらないのか?笑いが止まらない人たちがいる現実」2025年5月2日、参照)。
確実なのは増産である。農水省は、減反はしていないと言うが、あの手この手の事実上の減反を続けている。そもそも、コメの価格が倍になったのなら、本来農家は増産するはずだ。価格が倍になって増産しないものがあるだろうか。
農水省は、「農業生産は工業生産と異なって、そう簡単に増産できない」と言うだろうが、作付面積を増やす、より多くのコメをとれる多収米にするなど様々な方法がある。ただし、すでに田植えの時期だから、間に合わない可能性がある。
増産が間に合わなければコメの輸入である。コメを輸入しても日本の対米貿易黒字9兆円のうちのわずかな額にしかならないから、トランプ大統領へのプレゼントとしてはインパクトがないかもしれないが、ないよりはましだろう。