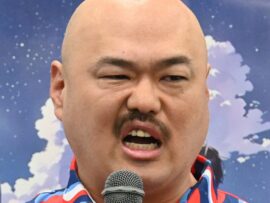〈「服従させることに躍起になっていましたね」日本の障害福祉の現場で起きている“非人道的な対応”のリアル〉 から続く
精神・知的障害者の脱施設化がはじまり、地域移行の政策が進むなかで、グループホーム事業運営に参入する民間事業者が登場した。そのなかには営利を目的とするばかりで障害者を理解していない団体もある。
ここではノンフィクション作家の織田淳太郎氏による『 知的障害者施設 潜入記 』(光文社新書)の一部を抜粋。密室で起きている虐待の実情を紹介する。(全4回の3回目/ 続きを読む )
◆◆◆
脱施設化(脱入院化)
日本において、精神・知的障害者に対する脱施設化(脱入院化)と地域移行の政策が、本格的にスタートしたのは、障害者自立支援法が施行された2006年からである。
これは1980年代になって国際的に叫ばれるようになった「ノーマライゼーション」や「インクルーシブな社会の実現」の理念が、ようやく日本でも受け入れられるようになったことを意味する。
入所施設や精神科病院はその流れに反する「非人道的な存在」として、多くの障害者団体や研究者から否定されてきたが、国がようやく重い腰を上げたことで、2012年現在、累計の地域移行者数は、政府の見込みを上回る2万5000人近くに達した。
前記したように、この流れの勢いが、グループホームの入居者数が入所施設の入所者数を12万人台後半で凌駕するという2019年の逆転現象に繋がった。その後、グループホーム入居者は増加の一途を辿り、2023年には17万人を超えたと言われている。
営利目的の法人の参入
「その流れに入り込んできた一つが、営利を目的とする法人でした」
東京都手をつなぐ育成会の前事務局長の齊藤一紀さんは言う。
「グループホームの運営に関しては、国がそれなりの予算の裏付けを示すようになりました。そこから、福祉事業は企業的に成り立つと計算できた人たちが、グループホームをやり始めたり、グループホームをセットにした福祉事業にどんどん乗り出したりしてきたのです。
都の育成会にも『グループホームをやりたいけど、どうしたらいいか』という問い合わせがけっこうありましたし、空き物件をグループホームとして有効活用させるための仲介業者まで登場したほどでした。
たしかにグループホームはニーズがあるし、家賃の取りっぱぐれもない。それほど元手がかかるわけでもなく、手軽に始められる事業だったんですね。問題の一つはそういう事業に、障害者を理解していない人たちが参入してきたことです。