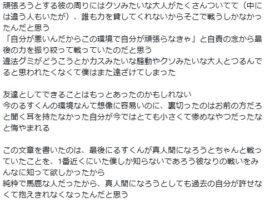「眉毛が抜けた」その時、すべてがつながった――病を悟った決定的瞬間
正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!
● 病の宣告後に映画館で喜劇を観るも1人笑えず
北條民雄(ほうじょう・たみお 1914〜1937年) ソウル生まれ。本名・七條晃司。代表作は『いのちの初夜』。高等小学校を卒業後、上京し、法政中学夜間部で勉強するなどプロレタリア文学を志すが、19歳でハンセン病を発症。東京・東村山のハンセン病療養所「全生病院」(現・国立療養所多磨全生園)への入院を余儀なくされる。病院から川端康成に作品を見てほしいと手紙を書き、作品を執筆。自身の経験をもとに書いた代表作『いのちの初夜』は、小林秀雄が「文学そのもの」と評するなど文壇から高い評価を得て、第2回文學界賞を受賞、芥川賞候補にもなった。作品集『いのちの初夜』がベストセラーになったものの、腸結核のため、その短い一生を23歳で終えた。
● ■「眉毛が抜けた」――確信へと至る瞬間
足に麻痺を感じ始め、鏡に映る自分の顔の血色が妙にいい―急にどうしたのだろうと不思議に思っていたところ、偶然、ある雑誌でらい病(ハンセン病)の記事を見かけます。
どうも、自分の身に起こった症状と似ていると思っていると、眉毛が抜け落ち、これでハンセン病であることが決定的になったと、のちに随筆に書いてます。
● ■恐怖と絶望が交差した一瞬の描写
「妙に眉毛がかゆく、私はぽりぽりと掻きながら自分の部屋へ這入った。そして何気なく指先を眺めると抜けた毛が五六本かたまってくっついているのである。おかしいと思ってまた掻いてみると、また四五本くっついているのであった。おや、と思い、眉毛をつまんで引っぱって見ると、十本余りが一度に抜けて来る。
胸がどきりとして、急いで鏡を出して眺めて見た時には、既に幾分薄くなっているのだった。私は鏡を投げすてて五六分の間というもの体をこわばらしたままじっと立竦んでいた。LEPRA!という文字がさっと頭にひらめいた」
『北條民雄 小説随筆書簡集』(講談社文芸文庫)
● ■診断、そして笑えなかった「喜劇王」
北條は自宅から20キロほど離れた病院に行き、「らい病」と診断されました。
その宣告にショックを受け、家に帰る気にならず映画館に行って、当時人気だったバスター・キートン主演の『喜劇王』を観て、気を紛らわせようとしました。
● ■笑い声のなかで、ひとり感じた孤独
笑いが起こる館内にあって北條はショックを拭いきれず、ほかの観客と同じように笑えないことに孤独感を覚えたと振り返っています。
※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
富岡幸一郎