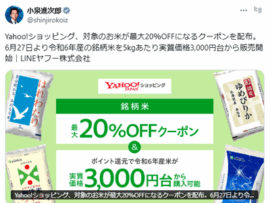2024年、東京の中古マンション市場に歴史的な変化が起きました。江東区の平均成約価格が7928万円となり、世田谷区の7746万円を史上初めて上回ったのです。わずか7年前の2017年には、江東区が4663万円、世田谷区が5617万円と1000万円近い差がありましたが、この差がわずか7年で覆されました。この価格逆転は、過去4年間の価格上昇率が江東区で15.4%だったのに対し、世田谷区は8.4%に留まったことが大きく影響しています。現実として、今やマンション購入において、世田谷区よりも江東区が有利な状況が生まれています。この価格上昇率の差は単年で見れば7%ですが、複利で考えると将来的にさらに拡大する可能性が高く、5年後には江東区の住民が世田谷区のマンション立地を格下に見るようになるという予測も成り立ちます。このような現象が起こる背景には、「マンションの資産性の法則」とも呼べる明確な理由が存在します。
現代において共働き世帯が増加し、通勤だけでなく子育ての必要性も高まる中で、「職住近接」は非常に切実なニーズとなっています。オフィスの約半分が都心3区(千代田区、中央区、港区)に集中している現状を考えれば、都心への通勤時間短縮はライフスタイルを支える上で不可欠な要素です。都区部の平均通勤時間は45.6分ですが、江東区は39.8分、世田谷区は50.0分となっています(住宅・土地統計調査2023年)。この片道わずか5分の差は、往復で10分、年間200日通勤とすれば33時間にも及びます。共働き世帯であれば年間66時間です。この時間を労働に充てれば、時給3000円の場合、一人当たり年間10万円の価値を生み出す計算になります。また、休息や自己啓発、家族との時間に充てる有効な時間となることは間違いありません。都心へのアクセス時間は、都市生活者にとって「時間を買う」という感覚に近く、極めて重要視されています。職住近接のニーズは、住居の面積に対する考え方も変えています。かつて理想とされた100平方メートル超の戸建てよりも、都心へのアクセスが良い70平方メートルのマンションで十分だと考える人々が増えているのです。
 東京23区、特に江東区や世田谷区におけるマンション価格と資産価値の変化を示すイメージ
東京23区、特に江東区や世田谷区におけるマンション価格と資産価値の変化を示すイメージ
マンションは一般的に利便性の高い土地に建設される傾向が強い一方、戸建ては駅から多少距離がある場所にも建てられます。マンションの駅からの平均徒歩時間は都区部平均で7.0分ですが、江東区は7.6分、世田谷区は9.3分です(住まいサーフィン調べ)。ちなみに、最も駅に近いのは千代田区の3.7分、最も遠いのは江戸川区の9.5分です。山手線の内側は地下鉄網が発達しており、駅から遠い場所はほとんどありませんが、山手線の外側では私鉄沿線などが放射状に伸びるため、都区部の外周部ほど駅間隔が離れる傾向にあります。このような立地は、マンションのような利便性を追求するニーズとは自然と合致しにくくなります。マンションは利便性の高い立地にしか建たないのに対し、戸建ては駅から徒歩20分かかるような場所にも建てられるため、そもそも立地の種類が異なります。駅から半径徒歩1分の面積と徒歩10分の面積の違いは単純な10倍ではなく、およそ100倍にもなります。都市部における立地の稀少性は桁違いに違うのです。都市に住む人々が最も望むものは利便性であり、「時間距離」が不動産の価値を決定する上で非常に重要視されると考えるべきです。
次に、建物の階数が高いほどマンションは建てやすく、過去のデータ分析からもその資産性が担保されやすい傾向が明らかになっています。資産性があるということは、価格が上昇しやすいということでもあります。一方で、低層のマンションは戸建てと競争関係に置かれやすく、戸建てが多い場所では価格が下落しやすい傾向があります。戸建ては土地代が下がりにくいとしても、建物価値は築22年程度でほぼゼロと評価されるのが一般的です。築22年経過した戸建てを購入する際には、土地代分の住宅ローンしか利用できないケースも多くあります。このように戸建てと競合する低層マンションは、価格が下がりやすいという特徴があります。
持ち家に限って見ると、江東区の戸建て比率は25%であるのに対し、世田谷区は60%と高い比率です。つまり、江東区では75%が共同住宅(マンションなど)であり、世田谷区では40%が共同住宅ということになります。マンション立地は資産価値が高く、戸建て立地は資産価値が低いと考えた場合、街並みを見ただけでそのエリアの不動産としての有望度をある程度判断できることになります。さらに、都区部のマンションの平均階数は9.7階ですが、江東区は13.5階と高い一方、世田谷区は6.1階と23区内でワーストクラスの低さです。世田谷区は2017年から建築物の高さ制限を導入しており、これにより高い建物がほぼ建てられなくなりました。結果として、世田谷区は高層マンションが建たない戸建て中心の立地となり、これは区民が保有する不動産の資産価値を下げる方向に作用していると考えられます。
江東区が世田谷区をマンション価格で逆転した背景には、職住近接を重視する現代のライフスタイル、駅からの距離による立地の稀少性、建物の階数と資産性の関係、そして区域ごとの戸建て比率や高さ制限といった都市計画や地理的特性が複合的に影響しています。江東区の都心へのアクセスの良さ、高い共同住宅比率、および高層建築の可能性がある環境が、資産価値の上昇を牽引した主要因と言えるでしょう。この価格逆転劇は、マンションの資産性を評価する上で、従来のイメージだけでなく、具体的なデータに基づいた「利便性」と「土地・建物の特性」がますます重要になっていることを示唆しています。
参考文献
- 住宅・土地統計調査2023年 (Housing and Land Survey 2023)
- 住まいサーフィン調べ (Sumai Surfin Research)