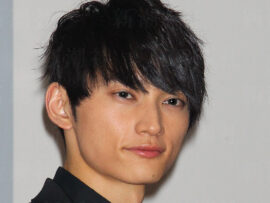玄関先に届いたはずの荷物が消えていた――。近年、「置き配」に関するトラブルが増加傾向にあり、消費者の間で不安が広がっています。こうした状況下、国土交通省は宅配便の受け取り方法として置き配を標準化する方向での検討を開始しました。これは再配達の削減や物流効率化に寄与する一方で、特に高額商品の盗難や消失といった新たなリスクもはらんでいます。利便性の向上と安全性の確保、そのバランスをどのように取るべきか、また個人としてどのような対策が考えられるのか、見ていきましょう。
国土交通省が進める「置き配の標準化」
2025年6月、国土交通省は宅配便の配送方法として、受取人が希望しない限り玄関前などに荷物を置く「置き配」を標準サービスとする検討に入ったと発表しました。この背景にあるのは、EC市場の拡大に伴う宅配物量の増加と、それに伴うドライバー不足の深刻化、そして依然として高い水準にある再配達率です。令和7年4月時点での全国平均再配達率は約8.4%に上り、これは物流業界における人件費や燃料費の増加、現場の負担増大に直結しています。
国土交通省は、持続可能な物流インフラの構築を目指し、これらの課題を解決する手段として置き配の標準化を推進する方針です。新たなルールでは、受取人からの特別な要望がない限り置き配が基本となり、対面での受け渡しは有料オプションとなる可能性も示唆されています。これにより、再配達が大幅に削減され、ドライバーの労働負担が軽減されるとともに、長期的な物流コストの抑制にもつながることが期待されています。
 玄関先に置かれた宅配便の荷物
玄関先に置かれた宅配便の荷物
置き配標準化で懸念される盗難・消失トラブルと金銭的リスク
置き配の普及が進むにつれて顕在化しているのが、盗難や消失といった配送トラブルの増加です。特に注意が必要なのは、高額な商品や精密機器が盗難・消失した場合の金銭的損失です。消費者の不安要因として、この点が最も大きくクローズアップされています。
また、置き配には天候による荷物の水濡れや破損、誤った場所に配達されてしまう誤配送のリスクも伴います。万が一、盗難や消失が発生した場合、被害額が数万円から十数万円に及ぶケースも報告されており、高額商品を購入する際には特に注意が必要です。このようなトラブルが頻繁に発生すると、個人の金銭的損失が増えるだけでなく、消費者がECサイトを利用する上での心理的なハードルを高める懸念も指摘されています。
まとめ
国土交通省による置き配標準化の検討は、物流業界が抱える喫緊の課題解決に向けた重要な一歩です。再配達削減による効率化は多くのメリットをもたらしますが、同時に盗難・消失といったリスクへの対策が不可欠となります。特に高額商品の配送に関しては、消費者自身も宅配ボックスの設置、セキュリティカメラの導入、あるいは有料オプションを利用した対面受け取りを選択するなど、自己防衛策を講じることが求められるでしょう。今後の制度設計と、それに伴う社会全体の意識の変化が注目されます。
参照
- 置き配で“高額の配達物が消えた”が頻発する可能性も? 国交省が「置き配標準化」検討へ (金融・経済メディア Financial Field)