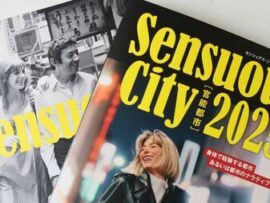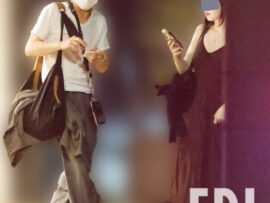2026年度からの導入が予定されている「子ども・子育て支援金」制度に対し、「実質的な独身税ではないか」との懸念が広がっています。この制度は、全ての医療保険加入者を対象とし、高齢者や事業主を含む広範な主体から、所得に応じて徴収される仕組みです。そのため、子どものいない世帯からは、手取りの減少だけが先行し、制度の恩恵が感じにくいとの声があがっています。また、少子化対策の主要な財源となる目的がある一方で、負担と支援のバランスについて疑問を持つ人も少なくありません。本記事では、この「子ども・子育て支援金」制度の仕組み、具体的な負担額の目安、そして集められた資金がどのように使われるのかを、分かりやすく解説します。
子ども・子育て支援金の仕組みと徴収方法
子ども・子育て支援金制度は、2026年度から開始され、公的医療保険の保険料に上乗せされる形で徴収されます。徴収対象は全ての健康保険加入者です。拠出額は、加入者が支払う医療保険料に含められる形となり、所得水準に応じて決定されます。
政府による2021年度の賃金実績に基づいた試算では、2028年度時点の水準として具体的な月額負担額が示されています。例えば、年収400万円の会社員や公務員(給与所得者)の場合、月額約650円、年収600万円で約1000円、年収1000万円では約1650円程度の負担が見込まれています。
この支援金は、2026年度から2028年度にかけて段階的に負担額が引き上げられる計画です。最終的に2028年度には、1人あたりの月額平均拠出額が800円から950円程度に達すると試算されています。ただし、これらの試算値は将来の賃金水準によって変動する可能性があるため、現時点ではあくまで目安として捉える必要があります。
 子ども・子育て支援金の制度概要や所得に応じた負担額の試算図
子ども・子育て支援金の制度概要や所得に応じた負担額の試算図
集められた資金の使い道
子ども・子育て支援金として集められた財源は、「子ども・子育て支援法」に基づき、主に既存の児童手当や育児関連給付の拡充に充当されます。
具体的な使い道としては、まず児童手当の支給対象年齢が高校生年代まで拡大され、これまで設けられていた所得制限も撤廃されました。さらに、2025年4月からは妊娠時・出産時に計10万円を給付する制度が整備されたほか、育児休業を取得した際の給付金拡充、短時間勤務を選択した場合の就業給付創設なども含まれます。
また、育児期間中の国民年金保険料の免除措置といった支援策も強化されています。これらの支援拡充を合計すると、0歳から18歳までの子ども1人あたりに対して、児童手当と合わせて総額およそ352万円の支援が行われると試算されています。集められた支援金は、これらの多岐にわたる子育て支援策の財源として活用される計画です。
今回の制度変更は、少子化という喫緊の課題に対応するための財源確保策の一つとして位置づけられています。制度の仕組みや負担、そして資金の具体的な使い道を知ることは、「実質独身税」といった懸念に対する理解を深める上で重要な一助となるでしょう。
出典: https://news.yahoo.co.jp/articles/1ff5656a692783d0d383d7e30b388838bd6a3b5a