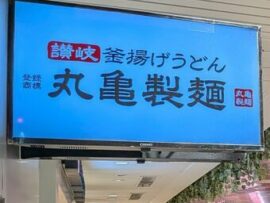日本の大手流通グループであるセブン&アイホールディングスの公式SNSアカウントが、台湾に関する表記を巡り大きな波紋を広げている。この一件は、企業が国際的な事業展開において直面する地政学的なリスクを浮き彫りにすると同時に、過去に日本の首相の発言が引き起こした事例とも重なり、台湾を巡る日本の複雑な立ち位置と「戦略的曖昧さ」の必要性を改めて示唆している。
セブン公式SNSでの「中国(台湾)」表記と炎上
今回問題となったのは、2025年7月にセブン&アイホールディングスの公式SNSアカウントに投稿された「世界のセブン‐イレブンのユニフォーム」を紹介する画像である。この画像内で、台湾が「中国(台湾)」と表記されていたことが発端となった。
この表記に対し、主に台湾および日本のインターネットユーザーから、多数の批判的な意見が寄せられ、いわゆる「炎上」状態となった。批判の声は、この表記が中国政府の主張する「一つの中国」原則に迎合するものであり、事実上の独立状態にある台湾の地位を軽視するものだという認識に基づいている。事態を受けて、セブン-イレブン側は公式に謝罪を行い、該当の投稿は削除されるに至った。
 セブン&アイホールディングスのSNS投稿。台湾表記を巡る炎上を示す画像
セブン&アイホールディングスのSNS投稿。台湾表記を巡る炎上を示す画像
過去の首相発言が示した台湾の「国」性に関する日本の複雑さ
台湾の「国」としての位置づけを巡るこの種の波紋は、今回が初めてではない。2021年、コロナ禍の最中に当時の菅義偉首相(現・元首相)が、感染対策で厳しい私権制限を行っている例として「オーストラリア、ニュージーランド、台湾の3国」と発言した際も、同様の衝撃と議論を呼んだ。
当時、情報番組に出演していた原著者(筆者)は、その発言を聞き「大丈夫なんですか、これは」と連呼してしまうほどの衝撃を受けたと記している。発言の趣旨がコロナ対策にあったことは理解できるものの、日本の首相が公の場で台湾を明確に「国」と表現したことへの驚きは大きかったという。その後、当時の加藤勝信官房長官は、首相の発言について事実上の修正を行う対応を取った。
日本政府の公式見解と国民感情のギャップ
このような出来事が波紋を呼ぶ背景には、日本政府の公式見解と、多くの日本国民が台湾に対して抱く感情との間に存在する一定のギャップがあると考えられる。
日本政府の公式見解は、中国政府の主張する「一つの中国」原則を理解し、尊重するというスタンスに基づいている。これは外交上の配慮からくるものであり、台湾を国家として正式に承認しているわけではないことを意味する。
一方で、多くの日本国民の間では、台湾は事実上民主主義を享受しており、日本と基本的価値観を共有する緊密な友好相手であるという認識が根強く存在する。半導体供給網をはじめとする経済的な結びつきも強く、「同志」とも呼べる存在だと感じている人は少なくない。そのため、公式見解として台湾を「国」と呼びにくい立場にあることに対し、複雑な感情や、時に無知であることへの批判が生まれる可能性がある。しかし、長年の友好関係や経済的連携から、台湾を大切に思う国民感情が強いゆえに、政府の公式な立場を知らない、あるいは理解しつつも納得しきれないという状況もまた、無理からぬことと言えるだろう。
企業が直面する地政学リスクと「戦略的曖昧さ」
今回のセブン&アイホールディングスの一件は、中国を含む国際市場で事業を展開する企業が、台湾問題のようなデリケートな地政学的リスクに常に直面していることを改めて浮き彫りにした。どのような表記や対応を取るにしても、関係各方面からの反応を招く可能性がある。
このような複雑な状況においては、日本政府が長年取ってきたとされる「戦略的曖昧さ」のようなアプローチが、企業にとっても必要な場合があることを示唆している。公式な立場の維持と、現実的な関係性や国民感情とのバランスをどのように取るかは、今後も多くの主体にとっての課題であり続けるだろう。
まとめ
セブン&アイホールディングスの公式SNSにおける台湾表記問題は、単なる企業のコミュニケーションミスにとどまらず、台湾を巡る日本政府の公式な立場、国民感情、そして企業が国際ビジネスで直面する地政学リスクという多層的な課題を内包している。過去の首相発言の事例も示すように、台湾の地位に関する言動は常に細心の注意を要するテーマである。日本が公式見解と国民感情の間の複雑なバランスを取りながら、企業がグローバルな展開を進める上で、こうしたデリケートな問題にいかに対応していくかは、今後も注視が必要である。