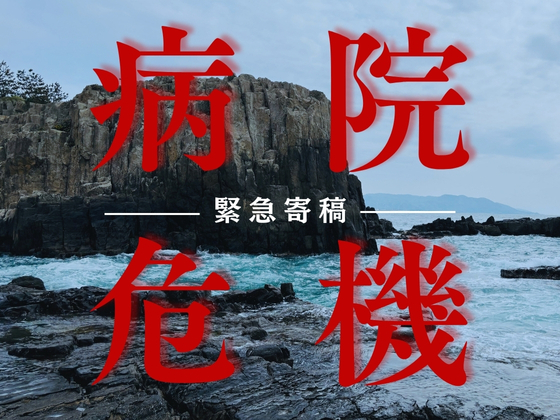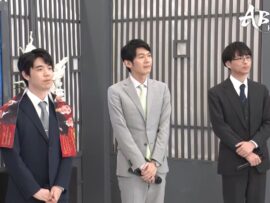CBnewsでは、医療経営の厳しい現状や国への要望を病院のトップから募り、緊急寄稿「病院危機」として配信している。第4弾は、長崎大学病院の尾崎誠院⻑。(随時配信)
【長崎大学病院 尾崎誠院⻑】
日本の医療制度は、公的医療保険制度に基づき、国民が保険料や自己負担を支払うことで、医療サービスを受ける仕組みとなっています。この制度は、国会で決定された予算に基づき、政府が医療費の総枠を設定し、その中で診療報酬や薬価などが決定されるトップダウン型の管理体制で運営されています。国が「どの程度の費用を国民に負担していただくか」を決め、その対価としての医療サービスを、全国の医療機関を通じて国民に現物給付しているとも解釈できます。
医療サービスを実際に提供しているのは各医療機関であり、診療報酬制度という厳格なルールの中で、提供内容に応じた報酬を、保険者を通じて受け取っています。制度上、保険者と医療機関に直接的な契約関係はありませんが、医療機関は実質的には、定められた制度の枠内で医療を提供する「下請け的な存在」ともいえます。たとえるなら、保険者が“ゼネコン(元請け)”として財源管理と制度設計を担い、医療機関はその方針に従って、一定の裁量を持ちながら業務を遂行する“下請け業者”のような構図です。
日本では長年、医療費を含む社会保障関係費は「高齢化による自然増の範囲内に抑える」という“目安対応”がとられ、薬価の引き下げや診療報酬の抑制を通じて医療費の伸びが制限されてきました。その結果、本来は受益者である国民に転嫁されるべき、物価や人件費の上昇、ロボット手術や高額薬剤、医療DXなど医療の高度化に伴うコスト増加が、医療機関の“企業努力”によって吸収されてきたのです。
しかし現在、多くの医療機関が経営的限界に直面しています。国立大学病院でも、無駄を省き、新規医療機器の購入を控え、さらに研究や教育の時間を診療に振り向けるなどの努力を長年にわたり重ねていますが、それでも赤字に転落しており、もはや現在の医療水準を維持することすら困難な状況にあります。
このように、現場の努力に依存する構造はすでに限界に達しており、今後の医療の持続可能性をどのように確保するかが、喫緊の課題となっています。今後の選択肢の一つは、これまで同様に、国民の負担をこれ以上増やさず、医療サービスの量や質を見直すという方法です。この場合、すでに医療機関の企業努力は限界に達し、赤字経営に陥っている現状を踏まえると、新たな医療技術の導入を抑制し、医療サービスを縮小せざるを得ない可能性があります。
もう一つは、これまで医療機関が吸収してきたコストを「必要な費用」として国民に適切に負担していただく、すなわち価格転嫁をお願いする方法です。これにより、現行の医療水準や質を維持しつつ、将来の医療の高度化にも対応できる可能性が生まれます。
もちろん、他にも様々な選択肢があると思われますが、いずれにしても、医療現場の努力に過度に依存してきた従来の構造は限界を迎えており、制度の持続可能性と、国民が安心して受けられる医療との両立を図るために、今後の医療の在り方を考え直す時期に来ていると考えています。
CBnews