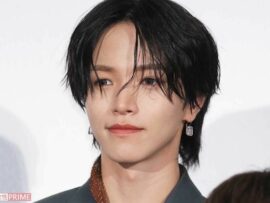夏の行楽シーズン、多くの人々が暑さを避け、山へと足を向ける中、山岳遭難事故が多発する時期でもあります。近年特に懸念されているのは、外国人観光客による無謀な登山が増加傾向にあることです。警察庁の統計によると、令和6年の遭難者合計3357人のうち、外国人は135人(4.5%)を占め、これは平成30年の統計開始以降、令和5年に次ぐ高い数値となっています。
しかし、長年変わらない傾向として、遭難者が多い年齢層の上位は高齢者です。令和6年のデータでは、70〜79歳が771人(23.0%)で最多、次いで60〜69歳が630人(18.8%)、50〜59歳が624人(18.6%)と続きます。これらシニア登山者とその予備軍にあたる層が、全体の6割以上を占めているのが現状です。本記事では、過去の事例から現代の課題まで、高齢者および外国人登山における安全対策の重要性を探ります。
増加する外国人登山者の遭難と変わらぬシニア層のリスク
近年、日本を訪れる外国人観光客の増加に伴い、山岳地域での活動も活発化しています。その一方で、日本の山の特性や気象条件に関する知識不足、準備不足が原因で遭難に至るケースが目立ちます。令和6年の警察庁統計は、外国人遭難者の数が依然として高い水準にあることを示しており、国際的な観光促進と並行して、適切な情報提供や安全啓発が喫緊の課題となっています。
一方、日本の山岳遭難で最も大きな割合を占め続けているのは、長年にわたる経験を持つベテラン登山者を含むシニア層です。彼らは山の知識や体力に自信を持つ一方で、年齢に伴う身体能力の変化や判断力の低下を見過ごしがちです。また、自身の経験を過信し、無理な計画を立ててしまうケースも見受けられます。これらの背景から、日本の山岳遭難対策は、外国人登山者へのアプローチと、シニア登山者への継続的な啓発という二つの側面から強化される必要があります。
 乗鞍岳の山小屋「肩ノ小屋」
乗鞍岳の山小屋「肩ノ小屋」
1985年乗鞍岳「遭難騒ぎ」の真実:準備万端のはずが高齢者グループを襲った事態
1985年7月、北アルプス・乗鞍岳で発生した男女16人、最年長78歳のシニアグループによる「遭難騒ぎ」は、当時の「週刊新潮」でも報じられ、大きな注目を集めました。地元関係者からは「ほぼ遭難」と指摘されたこの一件について、グループのリーダーは「遭難などしていない」と断言しましたが、彼らに一体何が起こったのでしょうか。
一行が前日(20日)に宿泊した岐阜県側、中尾温泉の旅館「美寿野館」の女将は、当時の状況をこう語ります。「あのご一行は、前日の午後3時ごろに私どもの旅館に到着しました。若い方が2人ほど交じっていましたが、ほとんどはお年寄りの方々でしたね。それだけに、旅館に到着してからも、入念に山の状況を調べていらっしゃいました。」
当初、彼らは岐阜県側の登山口・畳平(標高2800メートル)までマイクロバスで向かい、そこから山頂の剣ヶ峰へ登頂後、さらに尾根伝いに野麦峠まで足を延ばす計画でした。しかし、女将の夫が「今年の長雨で山道はひどく荒れている」とアドバイスしたところ、リーダーは長野県側の山小屋にも電話で確認を取った上で、「やはり遠くまで行くのは止めよう」と計画を変更しました。「無理をしてはいけないことを知っている人たちだと、私たちも安心していたのです」と女将は振り返ります。このエピソードは、入念な準備と慎重な判断がなされたにも関わらず、なぜ一晩の足止めを余儀なくされたのか、その背景に潜む山の予測不能な側面を示唆しています。
夏の乗鞍岳に咲く高山植物と雄大な景色
終わりに:安全登山のために情報を更新し、油断しない心構えを
乗鞍岳での「遭難騒ぎ」は、どれほど経験豊富で慎重な登山者であっても、山の状況が常に変化し、予測不能なリスクが存在することを教えてくれます。現代においても、外国人登山者の増加や、シニア層の遭難件数の高止まりは、過去の教訓が今なお重要であることを示唆しています。
安全な登山のためには、事前の情報収集と計画が不可欠です。登山ルートの状況、気象情報、そして自身の体力や経験を過信せず、常に余裕を持った計画を立てることが重要です。特に、高齢者や外国人登山者は、地域の山岳情報センターや経験豊富なガイドからのアドバイスを積極的に求め、適切な装備と準備を怠らないよう心掛けるべきでしょう。山は美しい自然を提供してくれる一方で、常に謙虚な気持ちで向き合うことが求められます。
参考文献
- 「週刊新潮」1985年7月20日号「『男8人女8人』老人登山隊 『遭難劇』進行中の分別」(再編集版)
- 警察庁統計(令和6年)「山岳遭難の概況」