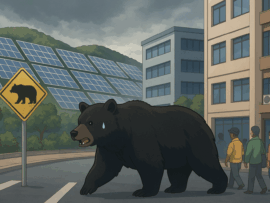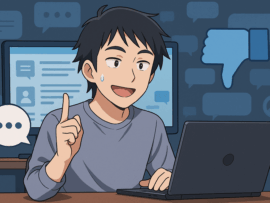「ご心配ありがとうございます!!嫌な世の中です。また落ち着いたら!」
2024年11月、故竹内英明・兵庫県議会議員から筆者が最後に受け取ったLINEメッセージには、そう記されていた。竹内氏が議員辞職したとのニュースに接し、慌てて連絡した際の返信であった。筆者はかつて産経新聞記者として姫路支局に勤務しており、姫路市を地盤とする竹内氏には度々取材の機会があった。何度も顔を合わせるうちに、歳が近いこともあって意気投合し、筆者が東京本社に異動した後も交流は続いていた。
筆者の知る限り、彼ほど優秀で精力的に働く地方議員はいない。個人としても明るく快活で、そして強い人だった。健全な議会制民主主義の確立が日本社会を良くすると信じ、有権者のために日夜奔走する竹内氏の情熱と気力体力には常に感銘を受けていたが、その彼が議員を辞めるとは――。
冒頭のやり取りの前日に行われた兵庫県知事選挙では、パワハラ問題などで県議会の不信任議決を受けて失職した前知事の斎藤元彦氏が、事前の予想を覆す形で再選を果たした。再選の原動力として、斎藤氏を「県庁やオールドメディアなど既得権益勢力に挑んで潰された被害者」とみなして擁護する言説がSNSや動画サイトで広く拡散したことが指摘されている。
インターネット上でそうした陰謀論的なムーブメントが過熱する中、竹内氏は「斎藤知事を貶めた主犯格」と位置付けられ、大量の誹謗中傷を受けていた。信頼していた地元の有権者が、徐々に荒唐無稽な陰謀論に染まってデマをまき散らすようになっていく状況は、耐え難いものがあっただろう。選挙後も悪意ある風説の流布や嫌がらせ電話は執拗に続き、竹内氏は2025年1月、自宅で亡くなった。この出来事が、今も筆者の心の中に重くわだかまっている。
日本におけるSNS選挙の台頭とその影響
2024年は、まさに日本の「SNS選挙元年」と呼ぶに相応しい年であった。兵庫県知事選挙をはじめ、その4カ月前に行われた東京都知事選挙などに際し、SNSや動画サイトといったネット空間で行われた情報戦が、従来の選挙戦では考えられなかったほど大きな影響を選挙結果に及ぼしたとされる。
こうした情報戦の場において、新聞や雑誌、テレビに代表される「オールドメディア」は否定的に捉えられ、その存在感は急速に低下しているように映る。政治の対立軸が、旧来の「左右」というイデオロギー的な区分から、既成政党と新興勢力という「新旧」の構図へと移行する中で、メディアもまた同様の対立軸に組み込まれつつあるのだ。しかし、この新たな対立軸の設定は、「ジャーナリズム」そのものを失わせてしまうのではないかという深刻な懸念を抱かせる。
ジャーナリズムの現状に対するこうした危機意識は、『アステイオン』102号の特集「アカデミック・ジャーナリズム2」の背景にある。同特集の緒言で、武田徹編集委員は次のように述べている。「マスコミ不信が高じて、『マスコミが伝えていない』という理由をもって実証性から著しく乖離した言説を信じようとする奇怪な逆張り思考法がSNSや動画共有サービス上で優勢になっている。ジャーナリズムが存在感を取り戻すことで、そうした傾向に少しでも歯止めがかけられることを願っている」。
同名の特集は2021年刊行の95号でも組まれているが、今回の切迫感は明らかにより強い。文化部記者として論壇を長く担当し、昨年からは論壇誌の編集にも携わっている筆者にとっても、その内容はこれ以上ないほど切実であり、学ぶところが甚大であった。
 SNS時代に情報と向き合う人々:ジャーナリズムの課題を表すイメージ
SNS時代に情報と向き合う人々:ジャーナリズムの課題を表すイメージ
オールドメディア不信とジャーナリズムの危機
武田徹氏の論文「SNS時代のジャーナリズム」は、従来型の「オールドメディア」の発信が信用されなくなりつつある現状を打開するため、哲学者・鶴見俊輔が提起した「マチガイ主義」(可謬主義)という概念を手がかりに議論を展開する。
これは、マスコミは嘘ばかりだと決めつけるネットの「逆張り言論」に対して、「マスコミは間違うこともあるが、間違いを正そうとするものでもある」という姿勢を打ち出すことで、逆説的に信頼性の回復を図るというアプローチである。
確かに、これまでのように無謬主義的な態度でいたずらに報道の正確性を強調するばかりでは、たった一つの誤報で積み上げてきた信頼が容易に崩れてしまう。誤報をゼロにすることは原理的に不可能である以上、第一報の後も取材や調査を続け、新事実が発見された際には過去の報道の間違いを訂正することが重要とする武田氏の主張は、まさにその通りであろう。ジャーナリズムには、自己修正能力が不可欠である。
「可謬主義」はメディアの信頼を回復できるか
しかし、「マチガイ主義」、すなわち可謬主義のジャーナリズムを実際に社会に受容させることは、現実的に容易ではない。例えば、新聞が「弊紙に書いてあることは間違っているかもしれませんので、その可能性に留意してお読みください」などと、自ら報道の不完全性を正面切って表明することは、実務上極めて難しい課題を伴う。
そうした可謬主義のジャーナリズムが受け入れられるためには、受け手である読者側との間に、強固な信頼関係が既に築かれていることが前提となるだろう。ここに一つのアポリア、すなわち解決困難な問いが潜んでいる。失われた信頼を回復するためには、信頼の存在が前提となるという循環論的な問題である。さらに、可謬主義を受け入れるような高度な情報リテラシーを持つ読者共同体が成立したとして、それは「マス」の単位、すなわち社会全体において可能なのであろうか。
ジャーナリズムは、SNSによって変容した情報環境の中で、その存在意義と持続可能性を問われている。情報過多と不信感が蔓延する現代において、メディアが如何にして信頼を再構築し、社会に貢献していくかは、引き続き探求されるべき喫緊の課題である。
参考文献
- 『アステイオン』102号 特集「アカデミック・ジャーナリズム2」
- 武田徹 論文「SNS時代のジャーナリズム」