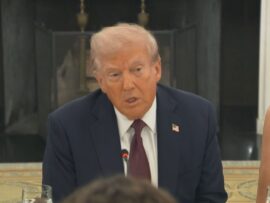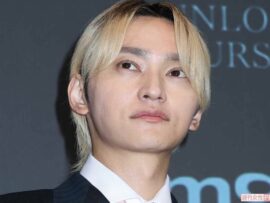教育現場で静かに浸透しつつある「自由進度学習」。しかし、これを単に「子どもたちのペースに任せること」と捉えているとしたら、それは大きな誤解かもしれません。もしそうであれば、「自由」は「放任」へと転じ、結果として一斉授業よりも質の低い学びを招く危険性があります。真に有意義な自由進度学習を実現するためには何が必要なのでしょうか。その核心となる視点について深く掘り下げていきます。
自由進度学習:子どもに寄り添う新たな学習形態
あなたは、子どもたち一人ひとりの学びに、どれほど真剣に寄り添えているでしょうか。私たちは「見取っているつもり」でも、実際には見取れていないことのほうがはるかに多いのが教育現場の現実です。では、今以上に子どもの学びに深く寄り添うにはどうすれば良いのでしょうか。その重要なヒントは、「寄り添う機会を構造的に増やすこと」にあります。そしてこれは、私たちが長年慣れ親しんできた一斉授業から、子どもが主体となる自由進度学習へと、学習形態そのものを見直すことにもつながります。
自由進度学習の本質は、単に学習のペースを子どもに委ねるだけではありません。これは、子どもが「自分の学び方」に対して責任を持ち、「何を、なぜ、どのように学ぶか」を自ら深く考えるようになるための仕組みなのです。このプロセスは、「自律した学習者」を育てるための不可欠な道筋であると言えるでしょう。
 教育現場で注目される自由進度学習の取り組み
教育現場で注目される自由進度学習の取り組み
「自律した学習者」の育成とPISA2022の示唆
PISA2022の調査結果は、日本の子どもたちの課題として「自ら学ぶ力」、すなわち目標設定、計画、振り返りといった自己調整能力の不足を明確に示しました。このような背景から、「自律した学習者」の育成がこれまで以上に喫緊の課題となっています。
しかし、「自律した学習者」とは具体的に何を指すのでしょうか。単に問題が解ける、漢字が書ける、計算ができるといった知識や技能の習得だけではありません。私が考える「自律した学習者」とは、「学習者自らが深い学びを実現できる存在」です。これは、得た知識を単に記憶するだけでなく、それらを関連付けて統合し、意味づけ、そして新たな課題に応じて柔軟に活用できる能力を指します。学習者が知識をただ覚えるのではなく、それらを体系的に整理し、状況に応じて応用できる力を育てることこそ、自由進度学習が持つ最大の可能性であり、その真価が発揮される点なのです。

「自由」と「放任」の境界線:誤解が生む学習の分断
しかし、自由進度学習は決して万能な「魔法」ではありません。「自由に進めていいよ」という言葉は、確かに学びの自由を保障する一方で、「放任」へと転じてしまう危うさを常に内包しています。
例えば、単元のプリントを配り、「自由に先に進めていいよ」と指示したとしましょう。子どもたちは言われた通り、ただ順番に問題を解き進めるだけです。教科書の「まとめ」や学習の要点にはほとんど触れることなく、ただ進度だけが進んでいく。このような状況において、本当に学びの深まりがあるのかといえば、強い疑問が残ります。これは、自由進度学習の実践現場を参観する際によく見られる光景です。
さらに深刻な問題は、「できる子」が表面的な理解のまま次の単元へ進んでしまうケースです。一方で、「わからない子」はどこでつまずいているのかさえ分からず、学習が完全に止まってしまいます。これでは、「自由」という言葉がかえって子どもたちの学びの分断を生み、学習格差を拡大させる結果になりかねません。自由進度学習が真に子どもたちの成長を促すためには、「放任」ではない、質の高い「寄り添い」が構造的に組み込まれる必要があるのです。
結論
自由進度学習は、子どもたちの「自律した学習者」としての成長を促し、「深い学び」を実現するための強力な手段となり得ます。しかし、その実践においては、「自由」と「放任」の厳密な境界線を理解し、子どもたち一人ひとりに「寄り添う機会」をいかに構造的に組み込むかが鍵となります。単にペースを任せるのではなく、教師が適切なサポートとフィードバックを提供し、子どもが自らの学びのプロセスに責任を持ち、試行錯誤できる環境を整えることが不可欠です。これにより、子どもたちは真に主体的な学びを経験し、未来を切り拓く力を育むことができるでしょう。
参考資料
- 樋口万太郎. “子どもに寄り添う機会を構造的に増やすには”. 東洋経済education × ICT. 2024年7月27日.
https://news.yahoo.co.jp/articles/36b83e4c3268d6842991b1b3680db8a6f103f8ba - OECD. PISA2022 (学習到達度調査). https://www.oecd.org/pisa/pisa-2022-results-japan.htm (参照される情報源の例、実際のURLはOECDのPISA2022結果ページを参照)