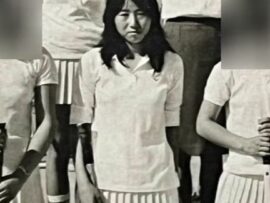先の参議院選挙は、これまでの予測を覆す結果となり、日本政治に新たな潮流が生まれたことを示唆しています。既存政党が抱える構造的な問題に加え、参政党のような新興勢力の台頭が、その背景にはありました。憲政史研究家である倉山満氏の分析を通し、一部で「カルト的」とも評される参政党の「近代軍」としての強さの秘密、そして今後の日本政治の展開を読み解く鍵を考察します。
予測が困難になった参院選と変化する有権者意識
今回の参議院選挙では、事前の情勢調査がほとんど機能しませんでした。投票日直前まで当選確実とされていた候補者が落選したり、その逆のケースが頻繁に見られたのです。例えば、自民党の鈴木宗男参議院議員は、午前中に引退会見を行ったにもかかわらず、午後には当選が確定するという異例の事態が生じました。また、全国の多くの選挙区で1%差という僅差の争いが多数発生しており、これは有権者一人ひとりが自ら考え、主体的に投票行動を行う傾向が強まっていることを明確に示しています。もはや選挙は「やってみなければ分からない」時代に入り、国民が投票に意味を見出す政治へと変容しつつあります。
参政党の「近代政党」としての組織力
参政党が持つ特異な組織力について、何を隠そう、倉山満氏自身が2012年正月に神谷宗幣氏にその組織論を教授したと語っています。倉山氏が提唱する「近代政党」とは、明確な「綱領」、全国を網羅する「全国組織」、そして「議員」という三要素から構成される政党です。具体的には、明確な理念や政策がシンクタンクで練り上げられ、それが組織的に全国の党員に展開され、党員がその綱領に基づいて全国組織を構築し、議員を当選させるというプロセスを踏みます。この意味での近代政党の典型は、公明党や共産党であり、彼らが強い組織力を持つ理由もここにあります。
対照的に、自民党や平成の政治改革以降に誕生した多くの新党は、議員個人の後援会や既得権益団体が中心となり、政策は後付けで形成される「前近代的」な組織だと倉山氏は指摘します。神谷代表が「公明党は創価学会が支配している。あれをやるんです」と街頭演説で語っていたように、参政党はまさにこの「近代政党」モデル、あるいは一部からは「新興宗教の如き」組織力を実際に構築し、その強さを見せつけているのです。
 参政党の政治活動を示すイメージ。日本政治における彼らの台頭と独自の組織力を象徴。
参政党の政治活動を示すイメージ。日本政治における彼らの台頭と独自の組織力を象徴。
自民党が「近代政党」を上回る理由:「神風」と国民政党の強み
しかしながら、この「近代政党」論には続きがあります。では、なぜ公明党や共産党といった「近代軍」に例えられる政党が、源平合戦の騎馬武者の集まりのような「前近代的」な組織構造を持つ自民党よりも多くの議席を獲得したことがないのでしょうか。倉山氏はその理由を二つ挙げます。
一つ目は、公明党や共産党が掲げる理念や綱領が、多くの日本人にとって受け入れがたいものであるという点です。これに対し、自民党は国民の多数派に支持される、いわば「国民政党」としての特性を持っているため、幅広い層からの支持を得やすいのです。
二つ目は、自民党が決定的な危機に直面した際に「神風」を吹かせてきた歴史があることです。「神風」とは、国民の支持を瞬時に集めるような画期的な政策やリーダーシップを打ち出すことを指します。その典型例として、森喜朗内閣時代に党が結党以来の危機に瀕した際、小泉純一郎氏を総理・総裁に据え、一大「小泉旋風」を巻き起こした事例が挙げられます。このように、自民党は国民の支持を得るための大胆な戦略転換を図ることで、危機を乗り越え、勢力を維持してきたのです。
これらの分析は、今後の日本政治の動向を予測する上で重要な視点を提供します。参政党の台頭は、既存の政治システムへの不満と、有権者の意識変化の表れであり、自民党が「国民政党」としての立ち位置と「神風」を吹かせる能力を今後も維持できるかどうかが、日本政治の均衡を左右する鍵となるでしょう。