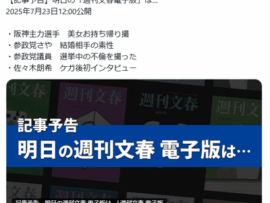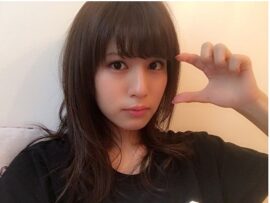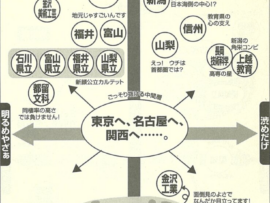7月20日に投開票日を迎えた参議院選挙で、自民党と公明党の与党は過半数を割る結果となり、政権運営に大きな課題を突きつけられました。この歴史的な敗北を受けてもなお、自民党総裁である石破茂首相は続投の意向を表明し、国内外で波紋を呼んでいます。特に、過去の経緯から麻生太郎氏が石破首相の退陣を強く求める動きを見せており、自民党内の対立が顕在化しています。
参院選惨敗、石破首相のまさかの続投表明
参議院選挙の大敗という厳しい結果にもかかわらず、開票日の翌日、石破茂首相は続投の意思を表明しました。首相は、「政治を停滞させず、漂流させないよう、地方の皆様方の声も丁寧に真摯にお聞きしながら、比較第一党としての責任、そして、国家・国民の皆様方に対する責任を果たしていかねばならない」と述べ、自身の損得ではなく国家のために職務を続ける意向を示しました。この発言には、米国との関税問題、深刻な物価高対策、そしていつ起こるか分からない自然災害への対応といった喫緊の課題への責任を果たすという考えがあったと報じられています。しかし、この続投表明に対し、他党だけでなく自民党内からも強い懐疑的な視線が注がれています。
「ブーメラン」批判の的となる石破氏の過去発言
石破首相の続投表明が特に強い批判を浴びているのは、彼自身の過去の発言との矛盾によるものです。全国紙政治部記者によると、石破氏は2007年に行われた参議院選挙で敗北し、辞任に追い込まれた安倍晋三元首相に対し、「辞めるべき」「私だったら即座に辞めて、落選した人に謝って回る」と厳しく指摘していました。この発言はインターネット上で広く拡散され、「ブーメラン」と揶揄され、石破氏の評価は急速に低下しています。現状では、自民党執行部を含め、誰も今回の選挙結果の責任を明確に負わない形となっており、党内や国民からの反発は避けられない状況にあります。
 参議院選挙大敗後も首相続投の意向を示す石破茂氏(左)と、その退陣を強く求める麻生太郎氏(右)が並び立つ様子。
参議院選挙大敗後も首相続投の意向を示す石破茂氏(左)と、その退陣を強く求める麻生太郎氏(右)が並び立つ様子。
石破氏の続投に対し、ネット上では以下のような厳しい意見が飛び交っています。
- 「国民の声聞かないんなら日本からでてけよまず」
- 「かつて一回選挙に負けた総理に辞任を何回も迫ったのが石破。自分は三連敗しても総理の座にしがみつこうとするのも石破。」
- 「往生際が悪すぎる。今回の結果が民意でしょ。いい加減にしてくれ」
麻生太郎氏の「石破おろし」画策と国民の複雑な反応
自民党内でも特に石破首相の続投に憤りを示しているのが、麻生太郎氏です。麻生氏は2009年の都議選で自民党が敗北した際の首相であり、当時、石破氏から自身の退陣を求められていました。現在の石破首相の状況は、まさに当時の麻生氏自身の経験と重なります。そのため、今回の選挙結果を受けてもなお「責任逃れ」をしようとする石破氏に対し、麻生氏は激しく憤慨しており、周囲には「続投は認めない」と話し、石破氏を退陣に追い込む動きを見せていると報じられています。これは民意を踏まえての行動とされますが、両者の間には「犬猿の仲」ともいえる私怨も背景にあると指摘されています。
麻生氏による「石破おろし」の行方に注目が集まる中、ネット上では賛否両論が渦巻いています。
麻生氏の動きを好意的に捉える意見:
- 「頼むよ麻生さん!!!」
- 「麻生さんガンバレ!石破さんが続投なら民意の否定です 民主主義の否定です 石破さんはいつ責任を取る取るのかな?」
一方で、麻生氏自身への批判や日本の政治状況全体への不満も噴出しています:
- 「80歳過ぎた爺さんが偉そうに国を背負う日本 そりゃいつまで経ってもよくならんわ」
- 「てか、あなたもそろそろ勇退をお考えになる年齢なのでは?」
- 「麻生お前も議員として認めたくねーよ 国民の生活より、保身のことしか考えない70歳以上の税金泥棒は全員議員辞職してくれ」
政治の停滞を乗り越え、次なるリーダーシップへ
全国紙政治部記者は、麻生氏が今年で85歳になることを指摘し、勇退を考えても良い年齢であるとの見解を示しています。石破氏を躍起になって退陣させようとする麻生氏の姿勢も、国民の目には冷静に映っており、どちらの政治家も国民の信頼を完全に得ているとは言えない状況です。
現在の自民党には国民からの強い批判とヘイトが向けられており、次の総裁には計り知れないプレッシャーがかかることになります。政治の停滞を打破し、国民の負託に応えるためには、足の引っ張り合いではなく、建設的な議論を重ね、真に国と国民のために尽くすことのできる次なるリーダーを発掘することが喫緊の課題となっています。