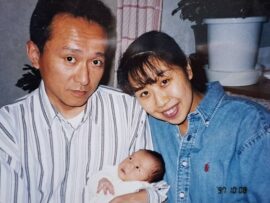家族が経営する会社で働く場合、給与の受け取り方が口座振込ではなく「手渡し」となるケースは少なくありません。しかし、手渡しであっても所得税や住民税の申告義務が発生するかどうかは、給与の内容や年収額によって変わります。特に源泉徴収の有無は確定申告の必要性を大きく左右するため、注意が必要です。本記事では、手渡し給与の法的な問題点、そして確定申告や税金に関する重要なポイントについて詳しく解説します。
手渡しでの給料支払いは法的に問題ない?
労働基準法第24条では、企業が労働者に賃金を支払う際のルールが定められています。主な条件は以下の通りです。
- 通貨払い: 現金(通貨)で支払われること。
- 直接払い: 労働者本人に直接支払われること。
- 全額払い: 給与の全額が支払われること。
- 毎月1回以上、一定期日払い: 賞与などを除き、毎月1回以上、決められた期日に支払われること。
これらの条件を満たしていれば、給与が手渡しであっても法的には問題ありません。労働基準法施行規則第7条の2には、労働者の同意があれば、指定された銀行口座などへの振込も可能であると明記されています。もし手渡しでの受け取りに不安を感じる場合は、事前に雇用主(家族)と相談し、合意の上で口座振込に変更してもらうことも検討しましょう。
源泉徴収の有無が確定申告の鍵を握る
給料を手渡しで受け取る際に最も重要なのが、「源泉徴収」がされているかどうかを確認することです。源泉徴収とは、会社が給与を支払う際に、あらかじめ決められた計算方法に基づいて所得税を差し引く制度を指します。
源泉徴収済みなら原則確定申告は不要
もし給与から所得税が源泉徴収されていれば、原則として労働者側で改めて確定申告を行う必要はありません。年末調整によって税額が精算されるため、基本的には手続きが完了します。しかし、源泉徴収が全くされていない場合は、ご自身で所得税の申告を行う必要があります。これを怠ると、税金の無申告として扱われる可能性があるため注意が必要です。
所得税が課されないケースと住民税の注意点
ただし、収入が一定額以下の場合、所得税が課税されず、確定申告が不要となるケースもあります。令和6年度の所得税に関する主な控除額は以下の通りです。
- 給与所得控除: 最低55万円
- 基礎控除: 48万円
これらを合計すると103万円となるため、年間の給与収入が103万円以下であれば、基本的に所得税は課税されません。ご質問のケースのように月7万円の給料であれば、年収は84万円となり、この103万円の基準を下回るため、所得税の申告は原則として不要です。
 家族経営で手渡し給与を受け取る手元と確定申告の必要性を示すイメージ画像
家族経営で手渡し給与を受け取る手元と確定申告の必要性を示すイメージ画像
ここで見落としがちなのが「住民税」です。所得税が課税されない年収であっても、住民税の申告が必要となる場合があります。住民税の非課税基準は、お住まいの自治体によって異なり、扶養親族の有無や家族構成などによって基準額が変わるのが一般的です。ご自身の居住地の自治体ホームページなどで、事前に住民税の非課税基準を確認しておくことが非常に重要です。
月10万円の収入で所得税はどうなる?(具体的な計算例)
もし手渡し給与が月7万円から月10万円に増額した場合、所得税が課税される可能性が出てきます。具体的な計算例を見てみましょう。
前提条件:
- 東京都在住
- 夫婦2人(雇用主が夫の会社)
- 社会保険には未加入
- 賞与は考慮しない
- 控除は給与所得控除と基礎控除のみ
- 控除額は令和6年度の基準を使用
計算ステップ:
- 年収の算出: 月10万円 × 12ヶ月 = 120万円
- 給与所得の算出: 年収120万円 – 給与所得控除55万円 = 65万円
- この65万円が「給与所得」となり、課税対象のベースとなります。
- 課税所得の算出: 給与所得65万円 – 基礎控除48万円 = 17万円
- この17万円が所得税の計算に用いられる「課税所得」です。
- 所得税額の算出: 課税所得17万円 × 所得税率5% = 8,500円
この例では、年収120万円の場合、年間8,500円の所得税が課されることになります。このように、わずかな収入増であっても、税金の計算が必要となる場合があります。
まとめ
家族が経営する会社から手渡しで給料を受け取ることは法的に問題ありませんが、税金に関する確認と理解は不可欠です。最も重要なのは、給与から源泉徴収がされているかを確認することです。源泉徴収されていれば基本的に確定申告は不要ですが、されていない場合はご自身で所得税の申告が必要になる場合があります。
また、年収が所得税の非課税基準(令和6年度は103万円)以下であっても、住民税の申告義務が発生する可能性がある点には特に注意が必要です。住民税の非課税基準は自治体によって異なるため、お住まいの地域の情報を必ず確認しましょう。不明な点があれば、税務署や自治体の窓口、あるいは税理士などの専門家に相談することをおすすめします。