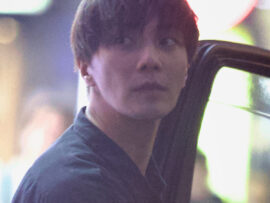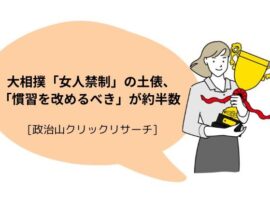急速な進展を見せていたテスラの自動運転関連サービス「オートパイロット」に、重大な転機が訪れました。米国連邦裁判所が、オートパイロット作動中の死亡事故に関してテスラに一部責任を認める初の判決を下したのです。テスラ側は控訴の意向を示していますが、この判決は同社が進めるロボタクシー事業の拡張戦略、さらには自動運転業界全体の未来にも大きな影響を与える可能性があり、注目が集まっています。
米国での画期的な判決とテスラの責任認定
今回の歴史的な判決は、米マイアミ連邦裁判所の陪審団によって言い渡されました。2019年にフロリダ州で発生したオートパイロット関連の死亡事故について、裁判所はテスラ側の責任割合を33%と認定し、原告に対し2億4300万ドル(約358億円、うち懲罰的損害賠償2億ドル)の支払いを命じました。これまでテスラは、自動運転関連の訴訟において、裁判前の和解や訴えの却下、あるいはテスラ勝訴の判決を得ることが多く、今回の敗訴はオートパイロット関連事故では初の事例となります。この判例は、今後類似の訴訟に多大な影響を及ぼすと自動運転業界関係者は見ています。非営利サイト「TeslaDeaths.com」の集計によれば、オートパイロット作動中に死亡に至った事例は、推定で少なくとも58件に上るとされています。
 テスラ社のロゴマーク。自動運転支援システム「オートパイロット」に関連する初の責任判決のニュースを伝える。
テスラ社のロゴマーク。自動運転支援システム「オートパイロット」に関連する初の責任判決のニュースを伝える。
オートパイロットとFSDの技術的分類、そして誇張広告の問題
テスラの「オートパイロット」と「FSD(Full Self-Driving)」は、同社のロボタクシー事業の中核をなす先進運転支援システム(ADAS)です。しかし、その名称が「完全自動運転」を想起させるにもかかわらず、米国自動車技術者協会(SAE)はこれらを自動運転5段階中の「レベル2(部分自動化)」に分類しています。これは、運転者が常に運転操作を監視し、必要に応じて介入することが求められる段階を意味します。テスラが最新技術を適用したロボタクシーも、「特定条件下での完全自動運転」を意味するレベル4の直前と評価されるに留まっています。
専門家は、こうした自動運転技術に対する誇張された宣伝が事故の一因であると指摘します。大林大学自動車学科のキム・ピルス教授は、「オートパイロットやFSDはあくまで運転支援機能に過ぎないが、その名称が誤解を招き、運転者の過信や錯覚による事故につながる側面がある」と述べ、2023年にGMのロボタクシー「クルーズ」の事故が市場全体を低迷させたような状況が再び起こる可能性を危惧しています。現在、カリフォルニア州では交通当局が、「テスラがオートパイロットやFSDという名称や広告で消費者を誤導した」として、虚偽広告の責任を問う訴訟を提起しています。
中国における自動運転技術の安全性議論と規制強化
自動運転技術の覇権を米国と争う中国でも、安全性に対する懸念が高まっています。今年3月には、中国の電気自動車メーカー小米(シャオミ)の「SU7」に搭載された運転支援システム「NOA(Navigate on Autopilot)」に関連して3人が死亡する事故が発生しました。この事故を受け、中国政府は「自動運転」や「スマート運転」といった誤解を招く恐れのある用語の使用や広告を禁止し、「運転支援」「補助運転」といった用語のみを使用するよう厳しく定めています。これは、消費者保護を強化しつつ、用語規制を通じて自動運転市場全体の萎縮リスクに対応しようとする措置と解釈されています。
テスラの反論と事業戦略への影響
今回の判決後、テスラは「今回の判決は技術の進歩を脅かし、人命を救う安全装置の開発を萎縮させる恐れがある」と述べ、控訴する意向を表明しました。直近のテスラの業績は芳しくなく、2四半期連続で市場予想を下回る結果を記録しています。前年同期比で、4~6月期の売上は224億9600万ドルで12%減、営業利益は9億2300万ドルで42%減となりました。主力の自動車販売とエネルギー貯蔵事業の売上減少が響いた形です。こうした業績不振のさなか、テキサス州オースティン以外にもカリフォルニアなどへのサービス展開を拡大しようとしていたロボタクシー事業の戦略にも、今回の判決が支障を来たすのではないかとの懸念が浮上しています。
自動運転業界の将来展望と課題
今回の判決を受けて、自動運転業界全体で安全性に対する関心が一層高まることは確実です。匿名を条件に取材に応じたモビリティ専門家は、「技術的にはレベル4まで到達可能だが、どこまでが運転者の責任で、どこからがメーカーの責任なのかは依然として曖昧なままだ」と指摘します。自動運転がレベル3やレベル4へと進むにつれてメーカー側の責任が大きくなるため、当面は各社が消費者の責任が大きいレベル2にとどまる可能性が高いとの見方も示されており、技術の進化と法規制、そして消費者の安全確保のバランスが、今後の自動運転開発の鍵となるでしょう。