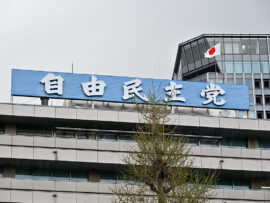1985年8月12日、日本の航空史上最悪の事故として歴史に刻まれた日本航空123便墜落事故。群馬県御巣鷹山に墜落したジャンボ機は520名の尊い命を奪い、その現場は想像を絶する惨状を呈していました。ジャーナリストの米田憲司氏は、事故発生後まもなく現場に足を踏み入れ、そこで目にした「地獄」のような光景と、心に深く刻まれた衝撃を新刊『日航123便事故 40年目の真実』(宝島社)で明かしています。本稿では、当時の状況を克明に記録した米田氏の体験談を一部抜粋し、墜落現場の生々しい実態とその後の深い影響について詳述します。
御巣鷹山、墜落現場への壮絶な道のり
事故現場へと向かう米田氏の耳には、報道陣のヘリコプターのけたたましい音が鳴り響いていました。2、3機が上空を旋回する中、自衛隊員の姿も点在しています。幹部らしき自衛官からは、「この先は行かないほうがいいですよ。もっとひどいから」と忠告を受けますが、ジャーナリストとしての使命感から足を止めることはできません。彼らの忠告に感謝しつつ、「気を付けて。お先に失礼します」と返して先へと進みます。
約5時間半の苦難の道のりを経て、ようやく尾根にたどり着きました。事前の予想では6時間を見込んでいたため、迷うことなく登れたことに不思議な感覚を覚えたと米田氏は語ります。まるで何かに導かれるように現場へと誘われたかのようだった、と。
御巣鷹山に広がる惨劇の光景
尾根から下方を見下ろすと、そこは東京の夢の島のような光景が広がっていました。尾根全体が、まるでゴミの集積場と化していたのです。機体の車輪は逆さまに転がり、左主翼は無残にもちぎれ、横たわっています。窓枠も散乱し、墜落の衝撃を物語っています。
現場のあちこちからは煙が立ち上り、機械油の鼻を突くような臭い、化学製品の刺激臭、そして燃え焦げた木々の臭いが混じり合い、強烈な異臭となって空気を満たしていました。歩を進めると、わずかに水平になった場所には、寝袋に入れられた複数の遺体が安置されています。広範囲にわたる現場には、多くの自衛官や警察官が活動しており、報道陣の姿はあまり見かけません。
その間を通り抜けようと歩くと、全身が焼け焦げた遺体が目に入ります。左手は上を向き、焼けた身体は小さく縮んでいました。目や鼻の穴、口の形も窪んでいて、生前の面影をかろうじてとどめています。その遺体のそばには、客室乗務員らしき紺色の制服をまとった遺体がうつ伏せになり、ショルダーバッグが落ちていました。
 日航123便墜落事故で山中に横たわるJAL機(写真:時事通信)
日航123便墜落事故で山中に横たわるJAL機(写真:時事通信)
記者が直面した「地獄」と精神的衝撃
数々の遺体をまたいで歩き続ける中、米田氏は甘酸っぱい吐瀉物のような臭いを感じます。生暖かい空気が尾根全体を覆い、異様な重苦しさをもたらしていました。そして、靴底に「ぐにゃっ」とした感触が。「土まみれの内臓を踏んだらしい」と、その時の衝撃を語ります。機体後部が滑り落ちていったというスゲノ沢が遠くに見えますが、そこまで往復する気力は到底ありませんでした。
同行していた記者たちの顔色は、無表情でありながら、言葉では形容しがたい感情が入り混じったものでした。放心しているわけではないものの、彼らの心は深く動揺し、「何も考えられない」、あるいは「頭が真っ白になっている」といった状態だったといいます。時間が止まったかのような感覚。まさに「百聞は一見に如かず」ではありましたが、この恐るべき全容を理性的、客観的に把握することなど不可能でした。記者同士の会話もほとんどありませんでした。
少し離れた岩場では、曹長らしき自衛官が弁当を食べているのが見えました。「よく食べられるな」と米田氏は思いましたが、自身も持参したトマトをかじり、何か腹に入れると食欲が湧いてくるのを感じました。下山を考えれば、体力を維持するために食べなければばててしまいます。気晴らしも兼ねて「飯を食べて休憩しよう」と提案し、何もない尾根の上部に座り、堀川さんが握ってくれた握り飯を秩父山系を眺めながら食べました。山で食べる握り飯は格別なはずですが、この時は味をほとんど感じなかったといいます。
向かい側には、123便の機体が擦過して樹林が折れ、ぽっかりと空白になった場所がありました。後に「U字溝」と名付けられたこの場所の下方には、水平尾翼が沢に落ちていたそうです。下山も5時間半を要しました。米田氏は、下山中も現場の悲惨さばかりを考えていたため、下山道の記憶はまったく残っていないと語ります。ただ、皆が黙々と、ひたすら下に向かって歩き続けたことだけが鮮明に残っています。
事故が残した永遠の教訓
日航123便墜落事故は、単なる悲劇としてだけでなく、航空安全の歴史に深く刻まれた教訓として、今もなお語り継がれています。米田憲司氏が御巣鷹山で目撃した惨状は、想像を絶する人間の苦しみと、それを経験した者だけが知り得る深い精神的衝撃を伝えています。彼の証言は、事故の記憶を風化させることなく、未来への警鐘としてその重みを伝え続けています。この事故から得られた教訓は、今後も航空安全と危機管理の重要性を訴え続けるでしょう。
参考文献
- 米田憲司 著『日航123便事故 40年目の真実』宝島社
- 時事通信社 (写真提供)
- 文春オンライン (記事提供元)