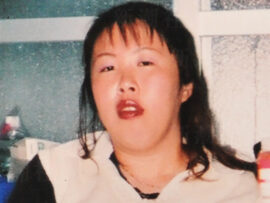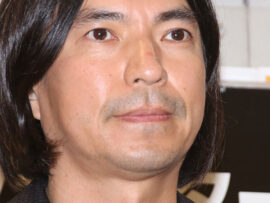1985年8月12日、日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、520人の尊い命が犠牲となりました。羽田空港を離陸した18時12分から、墜落する18時56分までの約44分間、機内で何が起きていたのか。事故発生当初から取材を続けてきたジャーナリストの米田憲司氏が入手し、独自分析した操縦室音声記録(ボイスレコーダー)と乗客の遺書から、当時の緊迫した状況が浮かび上がります。
 1985年8月、群馬県上野村の御巣鷹山で進められる日航ジャンボ機墜落事故の捜索活動。
1985年8月、群馬県上野村の御巣鷹山で進められる日航ジャンボ機墜落事故の捜索活動。
相模湾上空での異変と操縦不能
123便は相模湾上空で垂直尾翼の大部分を失い、油圧系統の配管が裁断されたことで、徐々に思うような操縦ができなくなっていきました。乗員は機体異常の原因について思考を巡らせていたはずですが、なぜか音声記録にはその会話は残されていません。機体は制御不能に陥り、危機的状況に直面していました。
激しい機体動揺:ダッチロールとフゴイド
焼津市を通過する頃から、機体は次第にダッチロール(左右の揺れ)が激しくなり、右に60度、次いで左に50度も傾く異常な挙動を見せます。機長は「バンクをそんなにとるな」と指示しますが、すでにパイロットの意図通りに操縦することは不可能だったと推察されます。横揺れに伴う風切り音が不気味な笛のように響き渡りました。
さらにフゴイド(機首の上下運動)が加わり、機首が15度から20度も上向き、今度は10度から15度も下がる状態を繰り返しました。上昇、降下、旋回がままならず、東京航空交通管制部(埼玉・所沢市)に要求した大島経由での羽田空港への帰還は、もはや絶望的な状況となっていきます。123便は大きく右旋回し、北の富士山方向へと飛行を続けました。
絶望の中の遺書:乗客たちの最後のメッセージ
操縦室音声記録には録音されていませんが、この緊迫した状況下の18時30分頃、客室では乗客たちが機内に備え付けられた紙袋や手帳に遺書を書き残していました。大阪・箕面市の谷口正勝さんは「まち子、子供よろしく」と、横浜市の吉村一男さんは会社の書類に「残された二人の子供をよろしく」と綴りました。
神奈川・藤沢市の河口博次さんは、手帳に「マリコ、津慶、知代子、どうか仲良くがんばってママをたすけて下さい。パパは本当に残念だ。きっと助かるまい……ママこんなことになるとは残念だ。さようなら……」という、家族への深い愛情と無念さが込められたメッセージを残しています。
操縦室の緊迫:操縦継続と酸素マスクの謎
機体の左右エンジンの推力調整を操作することで、操縦室では次第に機体の安定を取り戻し、この頃には機体も比較的安定していく様子がうかがえます。乗員の会話では酸素マスクの着用についてやり取りがあったものの、最終的に酸素マスクを着用しないまま、彼らは最期まで操縦を続けました。これは、音声記録に残された乗員たちの声がこもっていないことから推測される事実です。彼らは極限の状況下で、必死に機体を制御しようと努めていました。
結び
日航123便の墜落までの44分間は、操縦士たちが極限の状況で機体を立て直そうと奮闘し、乗客たちが愛する家族へ最後のメッセージを残した、想像を絶する時間でした。ボイスレコーダーが記録した緊迫の音声と、遺書に込められた悲痛な思いは、この事故の悲劇を私たちに語り継ぎ、航空安全の重要性を改めて深く心に刻みます。
参考文献
- 米田憲司 著『日航123便事故 40年目の真実 御巣鷹の謎を追う 最終章』(宝島社)