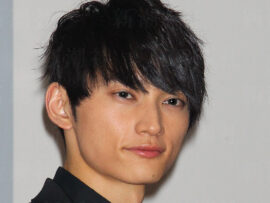定年後の生活は、現役時代の延長線上にあると考えるのは危険です。多くの人が「これだけ貯蓄があれば安心」と思っていても、住宅修繕費、医療・介護費、物価上昇、そして子や孫への予期せぬ援助など、不定期かつ高額な支出が重なることで、数千万円もの貯金が短期間で目減りするケースは決して珍しくありません。実際に、退職直後は経済的に余裕があると考えていた方が、わずか数年で生活設計の見直しを迫られる事態に陥ることもあります。佐伯さん(仮名/68歳)の事例は、まさにその典型と言えるでしょう。
「余裕のはず」が一転…佐伯さん(68歳)を襲った不定期・高額出費の波
65歳で定年を迎えた佐伯さん(仮名/68歳)は、現役時代に地道に貯蓄した5,000万円と、月に28万円の厚生年金という潤沢な資金を手に、第二の人生をスタートさせました。当初は「これだけあれば老後資金の心配は不要だろう」と確信し、旅行や趣味、外食も我慢せずに悠々自適な生活を思い描いていました。
しかし、退職から3年が経過する頃には、貯蓄の減少スピードに漠然とした不安を覚えるようになります。最初に家計に重くのしかかったのは、持ち家の大規模修繕費用でした。
予期せぬ住宅修繕費用の重荷
屋根の葺き替えや外壁塗装、そして給湯器の交換といった住宅メンテナンスは、いずれも多額の出費を伴います。特に屋根と外壁を同時に施工すれば、足場費用を抑えられるメリットがあるものの、その合計額は200万円から300万円に達することも稀ではありません。さらに、下地の補修や断熱材の交換などが必要となれば、費用は一層膨らみ、老後資金計画に大きな穴を開けることになります。
子や孫への支援、物価上昇が家計を圧迫
また、佐伯さんは予期せぬ形で子どもたちの生活費や孫の教育資金を援助することになりました。本人は「喜んで出した」と語るものの、これは当初の資産計画には全く織り込まれていなかった支出です。加えて、ここ数年にわたる物価上昇は、食料品や光熱費など日々の生活費をじわじわと押し上げ、家計に静かながらも確実な負担を加えていきました。
 老後資金の不安を抱え、家計を見直す夫婦
老後資金の不安を抱え、家計を見直す夫婦
医療費・介護費の現実と将来への懸念
さらに追い打ちをかけるように、奥様が持病で通院するようになり、毎月の医療費と薬代が数万円増加しました。将来を見据えれば、介護保険の自己負担増や、介護サービス利用を考慮した自宅のバリアフリー改修なども検討せざるを得ない状況です。これらは、まさに「現役時代の延長線上」では捉えきれない、老後の現実的な出費と言えるでしょう。
ファイナンシャルプランナーが警告する「老後資金計画」の盲点
専門家であるファイナンシャルプランナーは、老後資金の計画において「現役時代の延長」という安易な発想を戒めています。彼らによると、退職後の資金計画には、以下の不定期かつ高額になりやすい支出を具体的に織り込んだ、シナリオ別のシミュレーションが不可欠です。
- 住宅の大規模修繕費用: 築年数が経過した住宅には避けられない、屋根、外壁、水回りなどの高額なメンテナンス費用。
- 医療・介護費の増加: 高齢になるにつれて避けて通れない通院費、入院費、そして介護サービスの利用料など。
- 物価上昇リスク: 経済状況の変化による生活費の増加。
- 子や孫への経済的援助: 予期せぬ形で発生する教育費や生活支援など。
これらのリスクを事前に予測し、複数シナリオで資金の変動をシミュレーションすることで、突発的な出費にも対応できる強固な老後資金計画を築くことができます。
まとめ
佐伯さんの事例は、潤沢な貯蓄や年金があったとしても、定年後の生活設計には「隠れた落とし穴」が潜んでいることを明確に示しています。老後資金計画は、単に「いくら貯めるか」だけでなく、住宅の大規模修繕、医療・介護費、物価変動、そして家族への援助といった、予期せぬ高額出費のリスクを具体的に見積もり、綿密なシミュレーションを行うことが極めて重要です。漠然とした不安を解消し、真に安心して豊かなセカンドライフを送るためには、これらの不定期支出を織り込んだ多角的な視点での家計見直しが不可欠と言えるでしょう。
参考文献
- Gentosha Gold Online. 「【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額」.
https://gentosha-go.com/articles/-/41721 - Yahoo!ニュース. 「定年後の生活は「余裕があるはず」だった…5000万円を貯めていたはずが、老後3年で生活設計の見直しを迫られた男性の事例」.
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b46d1310cbc130f8b77225328f8eebaafaf0f7d