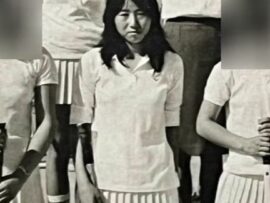「なぜあの人が評価されるんだろう…?」
職場で、自分よりも能力が低いと感じる人が、なぜか上司から高く評価されているのを見て、理不尽に感じた経験はありませんか?もしそうなら、あなたは職場での評価にまつわる「見えない戦略」についてまだ知らないかもしれません。近年、ロングセラーとなっている書籍『雑用は上司の隣でやりなさい』は、まさにこの「周りに実力を“評価させる”戦略」を初めて体系的に言語化し、多くのビジネスパーソンに衝撃を与えています。「よくぞ言ってくれた」「長年の暗黙知が言語化されている」「今まで気づかなかった新事実」といった反響が寄せられる本書から、今回は特に「出世する人」と「しない人」を分ける意外な特徴、そして現代の職場に潜む「サイレント減点」のメカニズムについて深く掘り下げていきます。
 職場での「見えない評価」と出世戦略を考えるビジネスイメージ
職場での「見えない評価」と出世戦略を考えるビジネスイメージ
休み明けのお土産、単なるマナー以上の意味
あなたの職場には、長期休暇の後にお菓子やお土産を配る同僚が必ずと言っていいほどいるのではないでしょうか。連休が明けると、静かにデスクを回って感謝の気持ちを伝えるように手渡される光景は、日本のビジネス文化においてごく日常的なものです。
一方で、「そんなの古い」「義務じゃない」と、お土産を配ることに全く関心を示さない人も少なくありません。確かに、お土産配りは業務規定に書かれたルールではありませんし、直接的な職務内容とは関係ありません。しかし、特にメガバンクのような伝統的な大企業では、そういった「配らない人」が出世街道から外れるケースが少なくないのです。その背景には、一見すると些細に見える行動が、実は職場の人間関係や評価に深く影響する「見えない理由」が隠されています。
見えない場所で決まる「無言の評価」の正体
筆者が勤めていたメガバンクでは、長期休暇明けのお菓子配りは、もはや企業文化の一部として定着していました。特に新入社員の頃は、お土産を持っていくことが当然の選択肢であり、ほとんどの人が実践していました。しかし、近年は「時代遅れだ」「意味がない」といった冷めた見方をする若手が増えているのも事実です。
ここで強く認識すべきは、お土産を配らないからといって、直接的に叱責されたり、人事評価会議で明確なマイナス点として指摘されたりすることはない、という点です。しかし、その行為が「確実に評価を下げている」という厳然たる事実が存在します。これは、誰からも何も言われないまま、静かにあなたの評価が下がっていく「サイレント減点」と呼ぶべき現象です。
以前であれば、経験豊富な先輩や上司が「こういう時は配った方が印象が良いよ」と、やんわりと指導してくれる機会がありました。しかし、現代の職場では状況が大きく異なります。ハラスメントへの意識が高まった結果、たとえ良かれと思って助言しても、それが「ハラスメント」と受け取られかねないリスクがあります。そのため、上の世代ほど、たとえ気づいていても何も言わない、という選択をする傾向にあります。結果として、誰も何も言ってくれない中で、個人の評価は静かに、そして気づかれないうちに下降していく「サイレント減点」が、いつの間にかあなたのキャリアに影響を与えている可能性が高いのです。
出世の鍵は「感情」と「気づき」にあり
出世に必要なのは、決して能力や実績だけではありません。数字で測れる成果はもちろん重要ですが、それだけでは語り尽くせない「人間性」や「関係性」が、評価において大きなウェイトを占めているのが現実です。
かつてのように、誰かがあなたに直接的に「こうすべきだ」と教えてくれる時代は終わりを告げました。今は、あなたが自ら周囲の状況を察し、見えない評価基準に気づき、行動を起こさなければ、評価が静かに沈んでいく時代です。
長期休暇明けのお土産一つで評価に影響するなんて、馬鹿げている、非論理的だと感じるかもしれません。しかし、人間は合理性だけでなく、「感情」によって動く生き物です。どれだけ厳格な定量評価システムを導入している会社であっても、最終的には上司や同僚の「気持ち」や「印象」といった定性的な要素が、評価に深く入り込むことを否定できません。
逆に考えれば、ほんの些細なお菓子を配るという行為が、職場で知らないうちに積み重なる「サイレント減点」を避け、円滑な人間関係を築き、結果的に自身の評価を高める手助けになるのであれば、それは極めて投資対効果の高い「戦略」だとは思いませんか?現代の職場環境においては、目に見える成果だけでなく、こうした「見えない気配り」や「細やかな配慮」こそが、キャリアを左右する重要な鍵となることを理解し、行動に移すことが、出世への近道となるでしょう。
参考文献
- 『雑用は上司の隣でやりなさい』 たこす 著