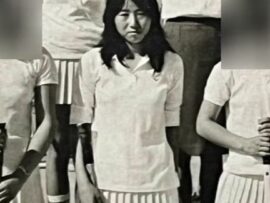2024年8月6日に公表された6月の毎月勤労統計調査(速報)は、日本経済に深い懸念を投げかけています。従業員5人以上の実質賃金は前年比1.3%減となり、これで6カ月連続のマイナスを記録しました。例年、ボーナス支給月である6月は実質賃金がプラスに転じることが多いにもかかわらず、今年は状況が悪化の一途をたどっていることが浮き彫りになりました。
現金給与総額こそ2.5%増と42カ月連続でプラス成長を示しましたが、これは3.8%にまで上昇した消費者物価指数(持ち家の帰属家賃を除く総合)に全く追いついていません。この物価高騰が、名目賃金の上昇を打ち消し、家計の実質的な購買力を蝕んでいるのです。
続く実質賃金の下落とインフレの深刻化
実質賃金がマイナス成長を続ける背景には、インフレの進行があります。消費者物価指数は対前年比で3%を超える伸びが続いており、これは日本銀行が掲げる2%の物価目標を大きく上回る水準です。黒田東彦前総裁時代の日銀は「デフレ脱却」を掲げ、異次元金融緩和を通じて物価上昇を目指しましたが、その力で目標を達成することはできませんでした。
しかし、2022年以降、資源価格の高騰などによる海外からのインフレ輸入をきっかけに、意図せずして物価上昇の状況が実現してしまいました。大規模緩和の根拠となった考えは、消費者物価上昇率が2%になれば経済が活性化するというものでしたが、現在3%を超える物価上昇が続いているにもかかわらず、日本経済は期待されたような活性化を見せていません。
「物価と賃金の好循環」は幻想か?迫り来る「イギリス病」の影
日本銀行は現在も「物価と賃金の好循環」を唱え、賃上げを促していますが、現状の賃上げは生産性の上昇を伴うものではなく、むしろコストプッシュ型のインフレを加速させるスパイラルに陥っていると見られます。これは、生産性が高まらないままインフレと成長停滞が同時に進行した1970年代の「イギリス病」に日本経済がいよいよ近づいている状況と酷似しています。
 実質賃金がボーナス支給月にもかかわらず下落し、家計が圧迫されている状況を示す図
実質賃金がボーナス支給月にもかかわらず下落し、家計が圧迫されている状況を示す図
実質賃金の引き上げを政策目標として掲げる石破政権にとって、この状況を放置することはできない喫緊の課題となっています。
家計調査が示す消費の停滞と実収入の減少
家計調査のデータは、インフレ下での日本経済の停滞状況を一層鮮明に示しています。総世帯の消費支出の対前年同月比を見ると、コロナ禍の影響で2020年にはマイナス6.5%と大きく落ち込みましたが、2021年にはプラス1.0%、2022年には0.9%と回復しました。
ところが、物価上昇が顕著になり始めた2023年には再び伸び率がマイナスに転じ、対前年同月比はマイナス2.1%となりました。つまり、インフレの進行によって消費支出が伸びるどころか、減少傾向に戻ってしまったのです。2024年もマイナス1.6%と、この傾向は続いています。
勤労者世帯の実収入の推移もまた深刻です。2021年から前年比マイナスが続いていましたが、特に2023年においては実収入の減少が著しくなりました。消費が減少したのは、この実収入の減少が主な要因であることは明らかです。2024年において実収入を減少させた大きな要因としては、世帯主の定期収入(マイナス0.28%)と、他の世帯員の収入(マイナス0.14%)が挙げられます。
これは、実質賃金が伸び悩む中で、家計が実質消費を減らさざるを得ない状況が家計調査の結果に如実に表れていることを意味します。ちなみに、2023年は春闘での賃上げ率が例年に比べて高まった年でしたが、それを上回るインフレ下では、名目上の賃上げがあっても実質所得が減少し、結果として実質消費も減少するという、経済の基本法則が示された形です。
望ましい賃上げの姿と日本経済の課題
望ましい賃上げとは、新しい技術の導入やビジネスモデルの革新などによって労働者の生産性が高まり、それを反映して賃金が上昇することです。しかし、現状は物価が上昇し、それに追いつくために賃上げを行うものの、それが生産性の向上に基づかないために、かえって物価をさらに押し上げ、結果として消費を抑制するという悪循環に陥っています。
実質賃金の下落、消費支出の停滞という現状は、日本経済が「インフレと成長の停滞」という複合的な課題に直面していることを示唆しています。持続可能な経済成長を実現するためには、単なる名目賃金の上昇にとどまらず、生産性向上を伴う実質所得の増加と、それに伴う消費の活性化が不可欠です。
参考文献
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査」各年各月速報
- 総務省統計局「家計調査」各年各月速報
- 日本銀行「物価安定の目標」関連資料