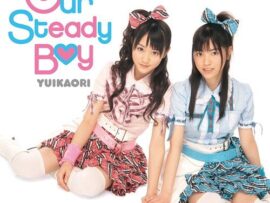長年、年金保険料を納めてきたにもかかわらず、その恩恵を受けられないという理不尽な状況に直面する高齢者が、現在の日本には少なくありません。会社が雇用保険を適切に支払っていなかったり、職場でのハラスメントにより早期退職を余儀なくされたりといった、予期せぬ理由で老後の生活に不安を抱えるケースが増えています。YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」では、こうした高齢者たちの生の声を取材し、その苦悩を伝えています。本稿では、同チャンネルの書籍『聞くのがこわい年金の話 年金、いくらですか?』(興陽館)から、ある男性の事例を抜粋し、その実情に迫ります。
 高齢者が年金に関する書類を持ち、老後の生活と金銭面への不安を抱える様子
高齢者が年金に関する書類を持ち、老後の生活と金銭面への不安を抱える様子
会社が雇用保険を払わず、年金受給で直面した困難
今回取材に応じたのは、現在61歳の独身男性。職業はフェリー(船)の清掃員として働いています。かつては陸上自衛隊に勤務していました。現在の住まいは社宅で家賃はかからず、予想される年金月額は7万円とのことです。
男性は60歳になった際、年金事務所を訪れ年金受給手続きを行おうとしました。通常、60歳から年金を受け取れるケースがあるためです。しかし、そこで「雇用保険受給資格者証」が一つ足りないという予期せぬ事実を告げられました。年金事務所の担当者からは、「あなたの会社は雇用保険を支払っていないため、年金は支払えません」と告げられたのです。
この言葉に男性は当初、何が起きているのか理解できませんでした。これまでに約1000万円もの年金保険料を支払ってきたにもかかわらず、なぜ受け取れないのか。銀行口座のコピーを持参し何度も交渉を試みましたが、「法律は変えられない」の一点張りで、年金受給開始は65歳からとなることが決定しました。男性の現在の会社は、現在は雇用保険に加入しているとのことですが、過去の未納が彼の老後に暗い影を落としています。
現在の仕事はフェリーの清掃で、主に大量の食器を手洗いし、その後食洗器で殺菌・消毒するという重労働です。一度に600~700人分の食器を扱うこともあり、「気が狂いそうになる」ほどの量だと言います。今月は休みなく働き続けている状況です。現在の清掃会社に勤め始めてから8年が経ち、今の勤務地に移ってからは5ヶ月。以前の勤務地では「死ぬかと思った」というほどの激務だったため、給料は半分になったものの、仕事量も半分になった今は「楽になった」と感じているそうです。毎朝早くから出勤前の公園で新聞を読むのが日課で、61年間ずっと一人で暮らしてきたと言います。
若き日の自衛隊経験と老後の不透明な年金額
男性は19歳から54歳まで自衛隊に勤務していました。自衛隊は定年が早く、当時は54歳が定年で、現在は56歳まで延長されたと聞いているとのことです。年を取ると銃を持って走ることが難しくなり、戦争で役に立たなくなるため、定年が早いのだと語ります。階級によって定年の年齢は異なり、少佐以上になると5年ほど延長される場合もあるそうです。
自衛隊を定年退職した人々の多くは、その後も別の職場で働いています。自衛隊内には「援護センター」というハローワークのような機関があり、退職後の仕事を紹介してくれます。仕事のリストの中から、希望する勤務地、内容、勤務時間などを考慮して選ぶことができるとのこと。男性は朝早く起きるのが習慣になっているため、常に朝3時には起床し、休みの日でもこの習慣は変わらないと言います。そのため、早朝から働ける仕事を選んだ結果が、今のフェリー清掃の仕事だったのです。
65歳から受け取れる自身の年金額については、男性はまだ正確には把握していません。「共済年金」など、自衛隊時代の年金保険料として約1000万円を支払ってきたことは書類で確認していますが、具体的な月額は不明です。すでに年金を受給している他の人に聞くと月々7万円程度だったとのことですが、自身が本当に7万円ももらえるのか、インターネットで詳しく調べていないため「わからない」と語っています。長年働き、保険料を納めてきたにもかかわらず、将来の年金額が不透明であるという現実が、彼の老後の不安をさらに深めています。
まとめ
本稿で紹介した男性の事例は、年金制度が複雑であり、予期せぬ事情により老後の生活設計が狂ってしまう現実を浮き彫りにしています。雇用保険の未加入という会社の不手際が、真面目に働き続けてきた個人の年金受給資格に影響を及ぼし、老後の生活不安を増大させる結果となりました。
長年の勤務と保険料納付にもかかわらず、自らの努力だけではどうにもならない事態に直面する高齢者がいることは、社会全体で向き合うべき課題です。年金制度に関する正確な情報へのアクセス、そして万一のトラブル時の相談体制の強化が、多くの高齢者の「年金不安」を軽減し、安定した老後を支えるために不可欠であると言えるでしょう。
参考資料
- 梅子の年金トーク!『聞くのがこわい年金の話 年金、いくらですか?』(興陽館)
- Yahoo!ニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/a14559816d455383be858c87c01173b93691983e