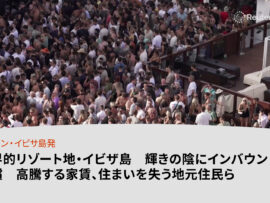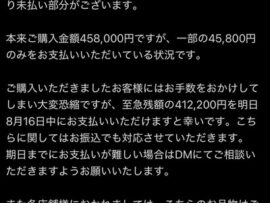「“赤い模様のヘビ”は毒があるから気をつけて」。1990年代、中部地方で育った筆者は、子ども心にそう言い聞かされていました。毒ヘビと聞けば、マムシやハブが真っ先に思い浮かびますが、私たちの身近に生息する「ヤマカガシ」もまた、決して軽視できない危険な存在です。しかし、このヘビの持つ危険性だけでなく、その体色の驚くべき多様性については、あまり知られていません。近年発表された最新の研究が、ヤマカガシの知られざる側面に光を当てています。
ヤマカガシとは?その生態と毒性への認識の変遷
ヤマカガシは、北海道、小笠原諸島、南西諸島を除く日本列島の広範囲に分布する日本固有のヘビです。全長は0.6mから1.2mほどで、カエルを主食とし、田んぼや川といった水辺の近くでしばしば見かけられます。一見するとおとなしく、積極的に人を攻撃する性質はありませんが、その毒性への認識は時代と共に大きく変化してきました。
かつては無毒と考えられていたヤマカガシですが、1984年に中学生が咬まれて亡くなるという痛ましい事故が発生したことで、その強い毒性が広く知られるようになりました。牙は口の奥に位置しているため、深く咬まれると毒が体内に侵入し、重症化する恐れがあります。過去50年間の記録では、ヤマカガシによる咬傷事例は50件近くに上り、そのうち5人が命を落としています。記憶に新しいところでは、2017年に兵庫県で小学生の男の子が咬まれ、一時意識不明となる報道もあり、その危険性が改めて浮き彫りになりました。
驚くべき色彩変異:地域によるヤマカガシの多様性
筆者が中部地方で「赤い模様のヘビ」と認識していたヤマカガシは、2017年のニュース映像に映っていた緑がかった体色のヤマカガシと大きく異なり、その色彩の多様性に驚かされました。春から秋にかけて活動するヤマカガシは、日本全国でどのような色合いを見せるのでしょうか。

全国に生息し、強い毒性を持つヤマカガシ。その体色には地域によって大きな違いがあります。
この色彩変異の謎に迫る研究が、近年発表されました。2025年5月には、北海道大学や京都大学の研究者4名がヤマカガシの色彩多型に着目し、「ヤマカガシ体色プロジェクト」を発足。市民160名の協力も得て、日本列島規模での大規模な調査・分析を実施しました。その結果、イギリスの動物学雑誌『Zoological Journal of Linnean Society』(1856年創刊)に掲載された論文で、なんと「123」もの色柄のパターンが存在することが明らかにされました。
ヤマカガシの体色研究自体は、半世紀以上前から行われてきました。1970年代以降の記載研究によると、ヤマカガシは「関東型」「関西型」「九州型」「青色型」「白黒型」「黒化型」という大まかに6種の体色タイプがあることがすでに判明していました。しかし、今回の「ヤマカガシ体色プロジェクト」は、これらの既知のパターンをはるかに超える多様な色彩が存在することを科学的に裏付けた画期的な成果と言えるでしょう。この研究は、私たちがヤマカガシを識別し、その生態を理解する上で極めて重要な意味を持ちます。
私たちにできること:ヤマカガシとの適切な距離の保ち方
ヤマカガシの色彩が地域によって多岐にわたるため、「赤い模様がないから安全」という認識は誤りです。どの地域のヤマカガシも強い毒性を持つ可能性があるため、見慣れないヘビを見かけた際には、安易に近づいたり触ろうとしたりしないことが最も重要です。特に、田んぼや川辺など、ヤマカガシの生息地とされる場所では、足元に十分注意し、ヘビに遭遇した際は、静かにその場を離れるようにしましょう。
ヤマカガシに関する最新の研究成果は、この身近な毒ヘビの生態理解を深めるとともに、私たち自身の安全意識を高めるきっかけとなります。地域ごとの多様な色彩パターンを知ることは、不必要な恐怖心を煽るのではなく、正しい知識を持って危険を回避するための第一歩となるでしょう。
参考資料
- Zoological Journal of Linnean Society. (2025年5月). ヤマカガシの色彩変異に関する論文.
- 福田将矢. (写真提供者).
- その他、過去のヤマカガシ咬傷事例に関する報道記事.