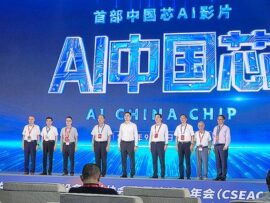家事や育児に専念する「専業主婦」という生き方は、現代日本において常に議論の的となっています。インターネット上では、「働かないのは楽」「生産性がない」「女性の社会進出が進む中、なぜ専業主婦を選ぶのか」といった声が飛び交い、「専業主婦論争」が巻き起こっています。しかし、その背後には、社会からの無理解や当事者自身の深い葛藤が存在しています。
収入がないことに「肩身が狭い」と感じ、食事をとるのも申し訳ないと語るあすかさん(35)は、仕事と家事の両立に限界を感じ、2年前に専業主婦の道を選びました。一方で、産まれてきたお子さんに病気が見つかり、やむを得ず専業主婦を選択したみえさん(37)は、「希望しておらず、ずっとストレス」「自分を見失う日々が続いている」と苦しい胸の内を明かします。かつては多数派だった専業主婦ですが、今や全体の3割を切るまでになり、社会の変化と共にその存在は変容を遂げています。本稿では、『ABEMA Prime』での議論をもとに、専業主婦を取り巻くリアルな声とその背景にある課題を掘り下げます。
「稼ぎがない」「生産性がない」社会の目に映る専業主婦の現実
専業主婦に対する社会の目は厳しく、直接的な収入がないことを理由に「生産性がない」と見なされる傾向があります。これにより、多くの専業主婦が精神的なプレッシャーを感じています。あすかさんが感じる「収入ゼロで肩身が狭い…ご飯食べて申し訳ない」という感覚は、まさにこうした社会からの無意識の重圧を物語っています。
その一方で、自らの意思とは関係なく専業主婦にならざるを得ないケースも少なくありません。専業主婦歴7年のみえさんのように、子どもの病気といった予期せぬ事態に直面し、「働く選択肢はなかった」という状況に追い込まれる人もいます。みえさんは「選択肢がないことが一番苦しい」と語り、希望しない生活がもたらすストレスと自己喪失感を訴えています。このような多様な背景を持つ専業主婦たちが直面する現実を理解することが、議論の第一歩となります。
限界からの選択:あすかさん(35)が専業主婦になった理由
 現代日本における専業主婦の生活と挑戦を表現するイメージ
現代日本における専業主婦の生活と挑戦を表現するイメージ
あすかさんは、2019年の結婚当初、正社員としてフルタイムで週5日勤務していました。当時の生活を振り返り、彼女は「平日は仕事、最低限の家事、寝る準備で1日が終わっていく。それが週5日で、土日休み。週末は平日できなかった家事や雑用、翌週の仕事に向けた準備をしていた」と語ります。食事も作り置きで済ませるなど、常に効率を求められ、心からリフレッシュする時間は皆無でした。
このような生活が続いた結果、彼女は「どんどん疲れていき、ストレスが溜まって、夫婦喧嘩も増えて、家の空気が悪くなった」と述べます。最終的には体調を崩すまでに至り、「何のために結婚したのかわからない家になってしまい」という絶望感を抱きました。この状況をリセットするため、あすかさんは2023年に仕事を一時的に辞め、専業主婦の道を選択することになります。この選択は、彼女にとって心身の健康と夫婦関係を守るための、やむを得ない決断でした。
専業主婦の「肩身の狭さ」:外で働かないことへの無意識のプレッシャー
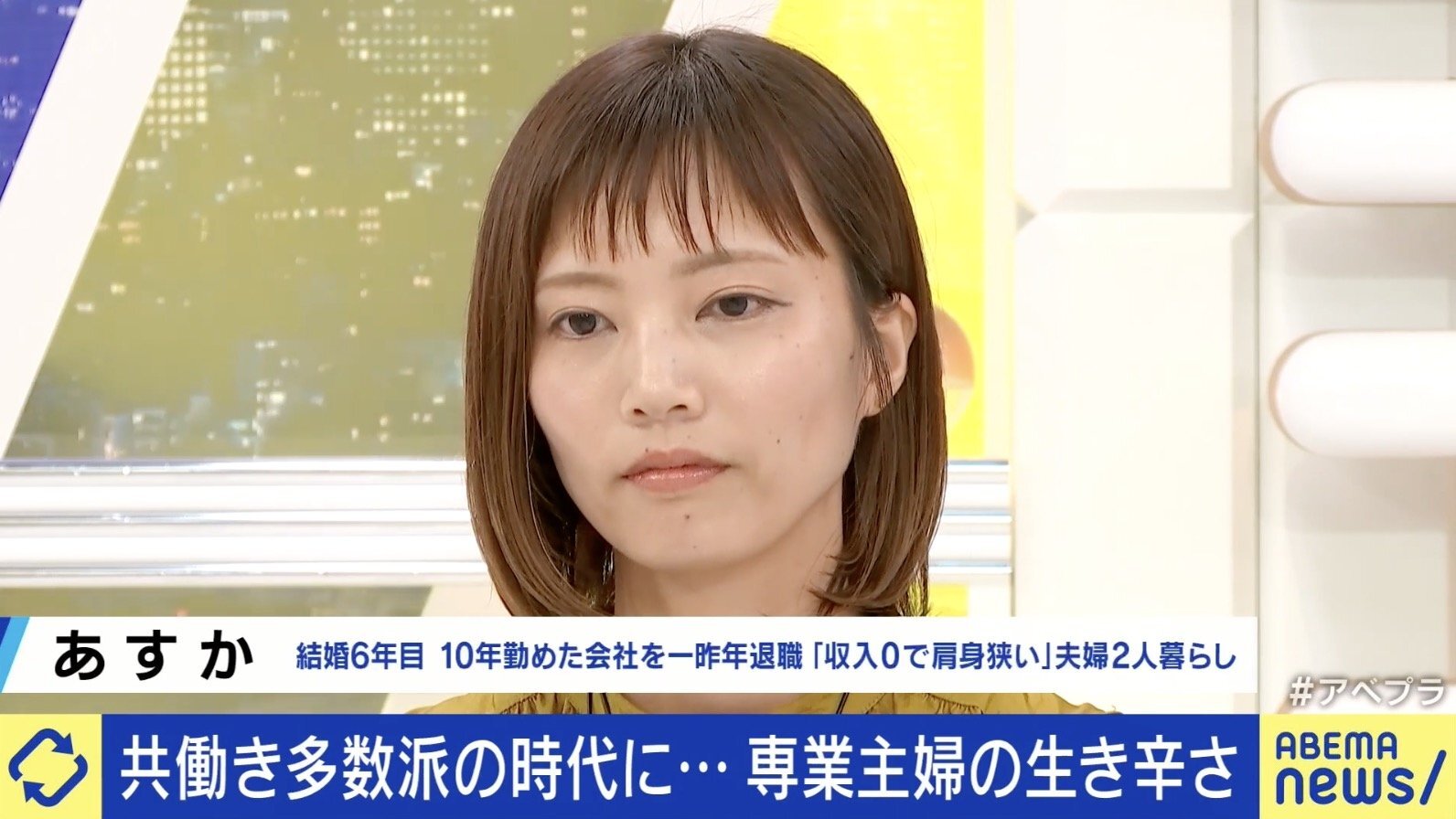 自身の経験を語る専業主婦のあすかさん
自身の経験を語る専業主婦のあすかさん
専業主婦という道を選んだあすかさんですが、いざその生活を送る中で、「肩身が狭い」という感情に頻繁に直面しています。例えば、美容院で髪のカラーリングをする際、「この髪色は会社的に大丈夫ですか?」と尋ねられたことがありました。本来であれば「専業主婦なので大丈夫です」と答えれば済む話ですが、質問する側が「私が外でお金に繋がる仕事をしている前提」で話していると感じ、言葉に詰まってしまうと言います。
これは、社会の中に「外で働いて収入を得ているのが当たり前」という無意識の前提があることを示唆しています。あすかさんは、「空気読みすぎなのかもしれないが、無駄に肩身が狭い。『外で働いてないとダメなのかな?』と思う」と、そのジレンマを打ち明けます。専業主婦が直面するこの「肩身の狭さ」は、単なる個人の感情に留まらず、社会全体の価値観が大きく影響している問題であると言えるでしょう。
まとめ:多様な生き方を尊重する社会へ
「専業主婦」という生き方は、もはや単純な「働くか否か」の二元論では語り尽くせない複雑な現実を抱えています。あすかさんのように、過酷なワークライフバランスの中で心身の健康を守るために選択するケースもあれば、みえさんのように、家庭の事情で「選択肢がない」ままその道を選ぶケースもあります。そして、そのどちらの立場にも、社会からの無言のプレッシャーや、自己肯定感の低下といった共通の苦悩が存在しています。
かつて日本の家庭で多数派だった専業主婦は、社会の変化と共に減少の一途を辿り、今や全体の3割を下回っています。しかし、その数が減っても、専業主婦という選択が持つ意味や、当事者が抱える課題は決して軽視されるべきではありません。現代社会に求められているのは、一人ひとりのライフスタイルや家族の状況を尊重し、多様な生き方を支えるための、より寛容な視点と具体的な支援体制ではないでしょうか。この「専業主婦論争」が、社会全体で真のワークライフバランスや性別役割分業について深く考えるきっかけとなることを期待します。