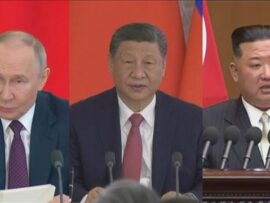著述家・楠木新氏は、「生き方や感情は顔つきに表れる」という独自の視点を持つ。長年にわたり多くの人を取材し、その「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと語る。本稿では、楠木氏自身のキャリアにおいて、どのように「顔つき」が重要な転機をもたらし、ベストセラー『定年後』が生まれたのかをひも解く。彼の経験は、個人の印象がいかに人との縁や仕事の機会を創造するかを示す好例であり、特にセカンドキャリアを模索する現代人にとって示唆に富む。
新聞記事の「顔写真」が明かした意外な執筆活動
生命保険会社に長年勤めた楠木氏は、50代以降、会社員と文筆活動を両立させる「パラレルワーカー」としての道を歩んでいた。著書は「楠木新」というペンネームで刊行し、社内では一部の同僚が知る程度で、積極的に公表することはなかったという。
しかし、定年を控えたある年、全国紙に楠木氏へのインタビュー記事が写真付きで大きく掲載されるという予期せぬ出来事が起こる。翌朝早く、同期入社の友人から電話がかかってきた。「新聞を見たぞ。本を書いていたのか。知らなかった」という友人の言葉に、楠木氏は「顔写真で俺だとわかるか?名前は違っているだろ」と返したが、友人は「誰でもわかるわ。お前はアホか」と笑い飛ばしたという。
このエピソードは、「顔」という身体の一部がいかに強いインパクトを持つかを楠木氏自身が改めて痛感するきっかけとなった。文章だけでは得られないような、表立った直接的な反応が、顔写真によって引き起こされたのである。さらに興味深いことに、この紙面に載った顔写真が、その後の新たな「ご縁」を繋ぐことになる。この記事を読んだ中央公論新社の編集者が、楠木氏の「顔」を見て、「この人とならいい仕事ができそうだ」と直感し、連絡を取ってきたのだ。
 豊かな人生を象徴する、笑顔のビジネスパーソンのイメージ
豊かな人生を象徴する、笑顔のビジネスパーソンのイメージ
「いい顔」が紡いだ縁とベストセラー『定年後』の誕生秘話
朝日新聞夕刊の連載「編集者(が/を)つくった本」で、楠木氏の担当編集者である中央公論新社の並木光晴氏が2019年7月10日に寄稿した記事のタイトルは、「著者の『いい顔』に直感」だった。並木氏はその中で、「楠木さんの“いい顔”なしに、『定年後』という本はあり得なかった。まだ面識がなかった頃、ある新聞記事に載った楠木さんの笑顔の写真を一目見て、ああこの人となら面白い仕事ができそうだと思ったのだ。編集者としての直感としか言いようがない。それは幸い的中し、まず『左遷論』、そして『定年後』でタッグを組むことになる」と語っている。
当時、楠木氏は自身の会社員経験を生かし、『会社が嫌いになったら読む本』や『人事部は見ている。』(共に日経プレミアシリーズ)といったビジネス書を執筆していた。並木氏はそれらの著書をチェックし、「左遷について中公新書で書けますか?」とオファーした。正直なところ、「左遷」というテーマで一冊の本を書き上げるのは難しいと感じたという。多くの人が口にする言葉ではあるものの、その概念が曖昧で、本にする自信がなかったからだ。信頼する先輩に相談した際も「それは無理じゃないか」と言われたという。
しかし、中公新書は学生時代からの憧れのレーベルであり、尊敬する梅棹忠夫氏も著書を刊行している。二度とないチャンスと考えた楠木氏は、ダメ元で挑戦を決意。関連書籍や論文を徹底的に収集するだけでなく、定期異動後の社員たちの生の声なども集め、2016年に『左遷論』(中公新書)を刊行。重版となり、ようやく肩の荷を下ろした。
その後、楠木氏は別の出版社に「定年後」に関する企画案を提出していたが、社内会議で承認されず、2~3カ月もの間、話が進まない状況が続いていた。最終的に一旦仕切り直すべきだと判断し、その出版社との企画を白紙に戻すことにした。
その打ち合わせを終えた足で、楠木氏は並木氏のもとを訪れ、企画案を見せた。すると驚くべきことに、翌週には中公新書編集部から企画の承認が得られた。そして翌年に刊行された『定年後 – 50歳からの生き方、終わり方』は、25万部を超える大ヒット作となる。以前の出版社での企画案がややコミカルな要素が中心だったのに対し、中公新書版ではよりシリアスな内容も加えたことが、多くの読者の共感を呼んだ要因かもしれないと楠木氏は分析する。いずれにしても、この一連の幸運とご縁を繋いでくれたのは、他ならぬ自身の「顔」だったのだ。その後も並木氏との縁は続き、楠木氏は中公新書から計5冊もの本を上梓することができた。
「いい顔」が切り拓く豊かな人生とキャリア
楠木新氏の経験は、「顔つき」がいかに人との出会いやキャリアの機会を創出し、運命を良い方向へ導くかという彼の持論を実証している。彼の「いい顔」は、単なる見た目の美しさではなく、長年の経験、生き方、そしてそこから滲み出る人間性が集約されたものである。それは、単なる文章では伝わりにくい信頼感や親近感を伝え、重要なビジネスチャンスを引き寄せる力を持っていた。特に、現代社会においてセカンドキャリアや人生の再構築が注目される中、楠木氏の物語は、個人の内面が外面に表れ、それが新たな道を切り開く原動力となり得ることを示唆する。私たちも自身の「顔つき」が、日々の生き方や人との関係にどのような影響を与えているかを省み、より豊かな人生を築くための「いい顔」とは何かを考えてみる良い機会となるだろう。
引用元: