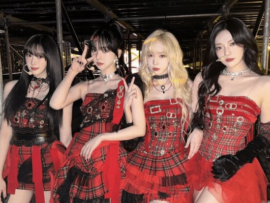日本社会が抱える外国人差別の根深い問題が、改めて浮き彫りになっています。病死、餓死、自殺が後を絶たない「入管施設」の現実、そして「現代の奴隷制」とまで呼ばれる「技能実習制度」の陰で、多くの外国人が苦境に立たされています。これは、安田浩一氏と安田菜津紀氏の共著『外国人差別の現場』(朝日新書)で詳細に語られているテーマです。本稿では、同書の一部を抜粋し、特に日本の縫製業界における技能実習生を取り巻く過酷な実態に迫ります。一見すると経済的な合理性から始まった制度が、いかに労働者の人権を脅かすまでに変質したのか、その現場の声を通じて考察します。
岐路に立つ日本の縫製業界:円高とファストファッションの衝撃
ある縫製業者が語った、技能実習生受け入れに至るまでの経緯は、日本の製造業が直面してきた構造的な課題を浮き彫りにします。彼が妻と二人で数十年間営んできた縫製工場は、1980年代半ばの急激な円高以降、安価な海外製品との激しい競争に晒され、軒並み苦境に陥りました。かつて「ガチャ万産業」(ガチャッと織れば万札が懐に入る)と称された時代は遠い昔の話となり、現在では「織れば織るほど赤字が増える」という、まさに理不尽な状況に陥っていると彼は説明します。
高級ブランドが市場を席巻した時代は終わりを告げ、現代ではファストファッションが業界の主流です。低成長時代の不景気も相まって、消費者の関心は「価格と機能性」に集中するようになりました。これにより、圧倒的に不利な立場に追い込まれたのが国内の縫製産業です。長い歴史と高い技術を持ちながらも、コスト面では海外製品に圧倒的な差をつけられ、国内工場がどれだけ努力しても、販売価格1000円以下のポロシャツやTシャツを生産することは現実的に不可能となりました。
 外国人技能実習生の低賃金を示す書類:2006年に入手された時給200円の記載
外国人技能実習生の低賃金を示す書類:2006年に入手された時給200円の記載
取引先からの「非情な選択」と零細業者の窮地
多くのアパレル会社が海外生産へと移行する中、国内の縫製工場への受注は激減しました。この業者の会社も倒産寸前まで追い込まれ、まさに瀬戸際に立たされた時期、取引先のアパレル会社から「非情な選択」を迫られたと言います。その選択とは、「コストの安い海外へ工場を移転して生産を続けるか、それとも海外製品と同じコストで国内で生産を続けるか、あるいは廃業するか」というものでした。
1980年代後半以降、アパレル会社は下請けの縫製業者に対し、一方的に工賃の切り下げを要求してきました。業者は「干されたくない」一心で、泣く泣くこれに応じるしかありません。しかし、海外移転できるほどの資金的余裕があるなら、とっくの昔にそうしていたはずです。老夫婦とパートだけで切り盛りする零細業者には、そのような資力は全くありません。アパレル会社は当然、そうした事情を知っていながら、あえて無謀な選択を迫り、実質的に切り捨て整理を進めていたのです。
この業者が主に製造している婦人服、例えば市価7000円のブラウスの工賃は、1枚あたりわずか750円だといいます。縫製に要する時間は約1時間。つまり、時間にして750円の売り上げにしかなりません。「景気が良い時は1500円くらいの工賃だったのですが、海外製品との競争が始まってからは、下落に歯止めがききませんでした」と業者は語ります。「しかし、750円の売り上げでは、ランニングコストを考えればほとんど利益が出ない。もう会社を潰すか、首を吊るか、そのくらいしか考えられなくなりました」。この切実な叫びは、日本のものづくりを支えてきた現場の悲鳴であり、技能実習生制度が抱える問題の背景にある構造的な課題を浮き彫りにしています。
結論:制度の歪みと人権問題への警鐘
日本の縫製業界で起きていることは、「技能実習制度」が抱える問題の一端に過ぎません。低賃金と過酷な労働条件は、経済合理性という名のもとに人権が軽視される実態を示しており、これは「現代の奴隷制」という批判が生まれるゆえんです。本稿で紹介した縫製業者の苦悩は、国内産業の衰退とグローバル経済の圧力の中で、最も弱い立場にある技能実習生にしわ寄せがいっている現実を物語っています。私たちは、この構造的な問題に目を向け、持続可能で人道的な労働環境の実現に向けて、制度そのものの見直しを真剣に考える必要があります。
参考文献
- 安田浩一・安田菜津紀『外国人差別の現場』(朝日新書)
- Yahoo!ニュース (2025年9月1日). 実習生の賃金を定めた書類(2006年に筆者が入手したもの)には、1年目の時給が200円と記されていた. (参照元記事)