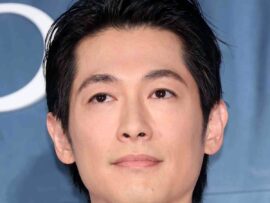東洋経済新報社の貴重なアーカイブ写真から、日本の都市が経験してきた変革の深層を探る連載「東京アナログ時代」。今回は特別編として、活気あふれる大阪の地へと焦点を移します。2025年の関西万博で再び世界の注目を集める大阪ですが、その劇的な都市変貌の根底には、昭和の時代から続く独自の発展の物語があります。本稿では、約45年前の昭和の大阪の風景を写真と共に振り返り、現在の驚くべき変化と未来への展望を探ります。
驚くべき大阪の都市変貌:過去から現在へ
東京を離れて大阪を訪れるたびに、その街の目覚ましい変化には常に驚かされます。約10年前、大阪駅前に降り立つと、そこには以前の面影を留めない全く新しい風景が広がっていました。「グランフロント大阪」として再開発された一帯は、現代的な輝きを放つ街並みに変貌を遂げていました。さらに天王寺駅前では、当時日本一の高さを誇る「あべのハルカス」の巨大な姿に圧倒されました。
近年も大阪の都市開発はとどまることを知りません。大阪駅前には、「グランフロント」に続く「うめきたエリア」の第2期開発「グラングリーン大阪」が新たにオープンし、中之島には新たな美術館も誕生するなど、大阪に不慣れな訪問者であれば、その絶え間ない変化に度肝を抜かれることでしょう。
 1980年7月、活気あふれる道頓堀の街並みと、当時人目を引いたえびの立体看板
1980年7月、活気あふれる道頓堀の街並みと、当時人目を引いたえびの立体看板
大阪独自の都市発展史:万博が牽引した昭和の時代
大阪は、東京とは異なる独自の歴史と文化に沿って築かれてきた都市です。戦後、東京が戦後復興と東京オリンピックに向けた都市改造の道を歩んだのに対し、大阪にとって1970年の日本万国博覧会は、高度経済成長期における都市開発の大きな起爆剤となりました。この万博がもたらした活気と投資が、その後の大阪の発展の礎を築いたのです。
その1970年大阪万博から約10年後の1979年から1980年にかけての大阪の街並みは、今見ると確かにレトロな趣があります。当時はいまだ昭和時代。現代から振り返れば約45年前にあたりますが、当時の写真からは、現在も残る面影と、もはや失われた懐かしい風景とが混じり合って見えてきます。
キタとミナミ:大阪二大中心地の個性
大阪の街には、文化と経済を牽引する二つの大きな中心地があります。それが「キタ」と「ミナミ」です。大阪を初めて訪れる方にとっては、キタが大阪駅や梅田周辺を指し、ミナミが難波(ナンバ)周辺を指すと理解するのが、大阪の街歩きの第一歩となります。これらの地域を実際に訪れてみれば、それぞれが持つ独自の個性や雰囲気がすぐに体感できることでしょう。活気と多様性に満ちた二つのエリアは、大阪という都市の魅力を形成する上で不可欠な存在です。
結論
東洋経済新報社の写真アーカイブから垣間見た昭和の大阪は、単なる懐かしさを超え、現代の大阪へと続く都市変革の物語を雄弁に語りかけます。1970年万博を契機に独自に発展を遂げてきた大阪は、グランフロントやあべのハルカス、そしてうめきたエリアの新たな開発を経て、2025年の万博に向けてさらなる進化を続けています。歴史ある街並みが現代的な景観と融合し、過去と未来が交錯する大阪のダイナミズムは、訪れる人々を魅了し続けることでしょう。