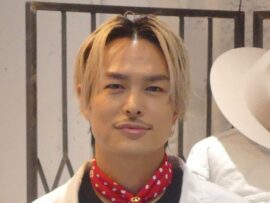認知症は特定の人の問題ではなく、誰もが直面しうる身近な課題です。近年、何気ない生活習慣や日常的に使用するアイテムが、認知症の発症リスクと関連している可能性が指摘されています。米国内科専門医であり老年医学専門医の山田悠史氏は、自身の著書『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』の中で、そうした日常行動と認知症リスクの深い関係について詳しく解説しています。今回は山田氏の知見をもとに、普段持ち歩くかばんの中身に潜む「認知症リスク要因」に焦点を当て、その具体的な内容を探ります。
認知症リスクを最も高める要因は? 難聴が飲酒・喫煙を上回る衝撃
山田氏の著書を読み進めると、認知症の最大のリスク因子が「難聴」であるという事実に多くの読者は驚かされるかもしれません。喫煙や過度な飲酒といったよく知られたリスク要因よりも、難聴がより高いリスクをもたらすという点は、従来の認識を覆す指摘です。
実際、開始時点で認知機能が正常な人々を対象に行われた8年間の追跡調査では、25デシベル以上の聴力障害がある群では、そうでない群と比較して認知症リスクが1.9倍にまで上昇することが明らかになっています。さらに興味深いことに、中年期における聴力低下が、脳の記憶を司る「海馬」や「側頭葉」全体の容積がより早く減少することと関連しているという研究結果も存在します。これらの知見は、単なる「聞こえの不調」と捉えられがちな聴力の問題が、脳の構造的変化や認知機能低下の直接的な引き金となり得ることを示唆しています。だからこそ、難聴に対する予防的なアプローチが極めて重要となるのです。
 認知症のリスクと脳の健康、予防の重要性を示すイメージ
認知症のリスクと脳の健康、予防の重要性を示すイメージ
「難聴」を避けるために日常生活で注意すべき点
脳の構造や機能にまで影響を及ぼすとなると、難聴予防は看過できない問題です。では、日常生活においてどのような点に注意を払うべきでしょうか。
日常的にテレビや音楽の音量を上げがちな方は、無意識のうちに聴力にダメージを蓄積している可能性があります。大きな音に継続的にさらされる生活は、時間の経過とともに聴力低下に繋がりやすく、結果的に難聴を招き、それが認知症リスク増加へと繋がる可能性が指摘されています。
難聴リスクが高まるのは、一般的に80デシベル以上の音です。これは、たとえば賑やかな居酒屋での会話、ピアノの生演奏、カラオケ店の店内といった音環境に相当します。通勤中に音楽を大音量で聴く習慣がある方や、周囲がうるさくなると無意識に音量を上げてしまう方もいるでしょう。また、野球場やコンサート、サッカーのスタジアムなども含め、大音量にさらされる場面は意外と身近に多く存在します。イヤホンやヘッドフォンを使用する場合も、このレベルの音量は簡単に超えてしまうため、特に注意が必要です。
持ち物から読み解く「認知症になりやすい人」の特徴
テレビやイヤホンを使う際の音量調整は、今日からでも意識したい大切な生活習慣です。では、日々の生活の中で、他に認知症リスクを確認する手軽な方法はあるのでしょうか。
「日頃どんな物を持ち歩いているか」――つまり“かばんの中身”を確認してみるだけでも、その人の生活スタイルや将来的な認知症リスクの傾向をある程度推測できるかもしれません。一見すると関係がなさそうな持ち物にも、実は日頃の“癖”が透けて見えることがあります。たとえば、以下のようなアイテムとその使い方に心当たりがないか確認してみることで、自身の生活習慣を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
認知症リスクは、特別な病気や運命として捉えられがちですが、実際には難聴をはじめとする日常の習慣と密接に結びついています。今回ご紹介した山田悠史氏の知見は、難聴が認知症の主要なリスク因子であり、その予防が脳の健康を維持するためにいかに重要であるかを明確に示しています。テレビやイヤホンの音量に注意を払う、賑やかな場所での長時間滞在を避けるなど、日々の少しの心がけが将来の認知症予防へと繋がります。また、自身の持ち物から生活習慣を振り返るというユニークな視点も、健康的なライフスタイルを見直す貴重な機会となるでしょう。
参考文献:
- Yahoo!ニュース (Diamond Online掲載記事)