日本における西サハラに関する言説や記述には、しばしば事実と異なる情報が含まれている。政府機関や関連団体が意図せず、あるいは積極的に誤った情報を発信し続けているケースも見受けられるのが現状だ。この情報格差は、西サハラの複雑な実情を知らない人々が、不正確な情報に気づくことを困難にしている。日本の国際協力や外交政策に関わる人々にとって、この問題への理解は不可欠である。
国際協力イベントの「クイズ」が抱える問題点
2024年9月28日と29日、東京・新宿では「グローバルフェスタJAPAN2024」が開催された。この国際協力イベントの公式ウェブサイト「国際協力を学ぼう!参加しよう! Let’s ODA Quiz」には、参加者の知識を試すクイズが出題されていた。全4問のうち3番目の問いは、「アフリカのモーリタニアとモロッコから日本が輸入する約6〜7割を占める海産物はなんでしょう。」というものだった。その答えは「タコ」。しかし、このクイズには根本的な問題がある。現実には、モロッコ本土では日本へ大量に輸出するほどのタコは漁獲されていない。この事実は、クイズの前提自体が成立しないことを示唆している。
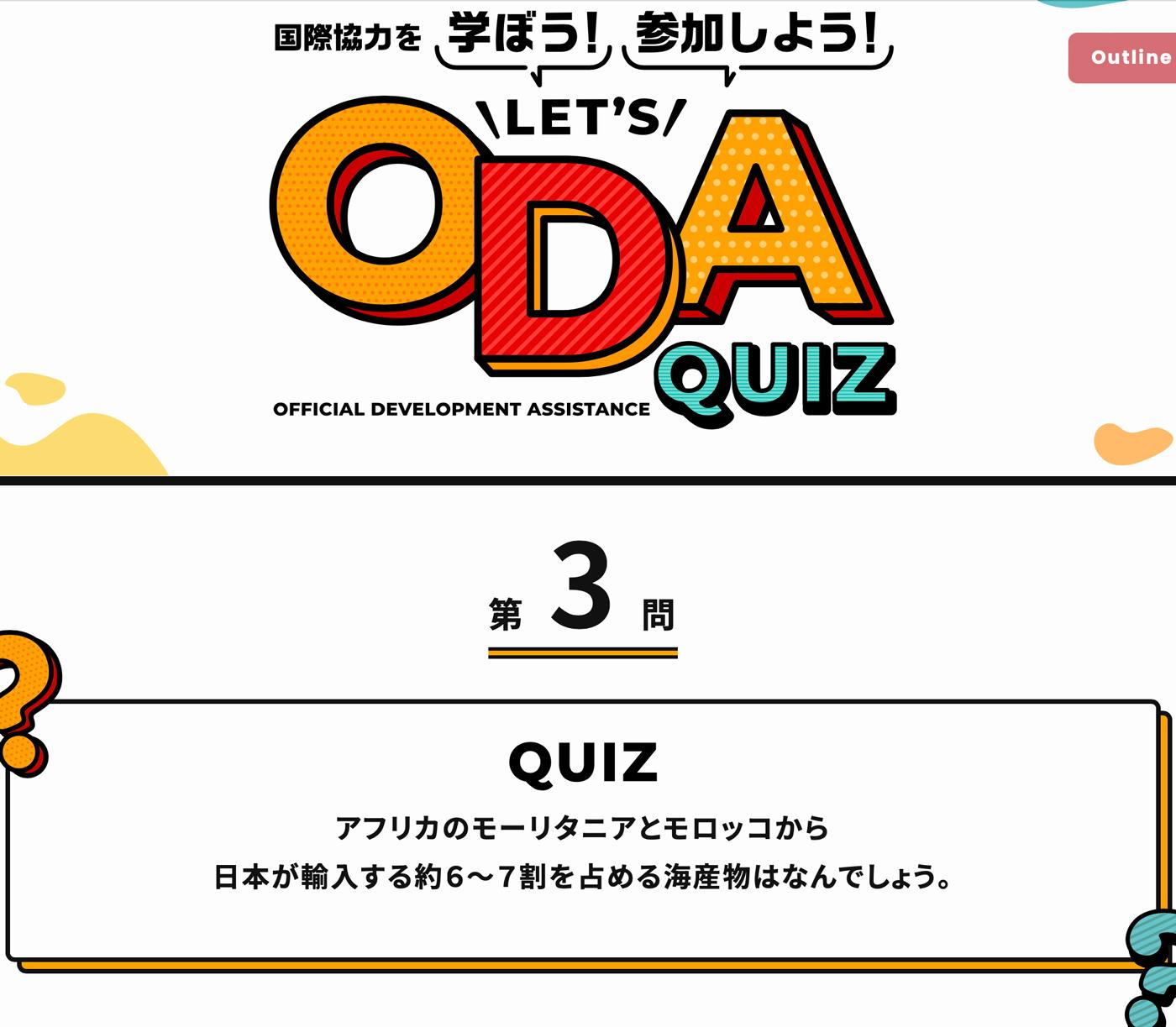 グローバルフェスタJAPAN2024の公式ウェブサイト画像
グローバルフェスタJAPAN2024の公式ウェブサイト画像
JICAの声明と西サハラ産水産物の現実
国際協力機構(JICA)もまた、西サハラに関する情報の曖昧さに加担していると指摘される。2021年2月15日、JICAのウェブサイトに掲載された「日本の食卓を支えるモロッコに最新海洋・漁業調査船が就航」と題するページでは、岡山県で建造された調査船のモロッコへの供与が報じられた。同ページは「日本に輸入されるタコの約2~3割がモロッコ産で、マグロやイカなどおなじみの水産物もモロッコから多く輸入されています」と記し、JICAの公式Xアカウントでは「1万キロ以上離れたモロッコの人と、同じタコを食べながら。」と投稿された。
 JICAの公式Xアカウントからの投稿イメージ、西サハラ問題に言及
JICAの公式Xアカウントからの投稿イメージ、西サハラ問題に言及
しかし、モロッコから輸出されるタコの大部分は、国際法上の地位が未確定である西サハラの海域で漁獲されたものである。モンゴウイカについても同様の状況が見られる。西サハラの港では、タコが「TAKO」、モンゴウイカが「MONGO」と表記されるほど、これらの水産物と日本の関係は深く、長年にわたる。さらに、日本の漁船がモロッコに操業料を支払い、西サハラの海域でマグロ漁を行っているという実態も存在する。
 カナリア諸島で語る日本人漁師、西サハラ沖でのマグロ漁の実態
カナリア諸島で語る日本人漁師、西サハラ沖でのマグロ漁の実態
日本政府は公式にはモロッコによる西サハラの領有を認めていない。それにもかかわらず、JICAの一連の言説は、西サハラで獲れる水産物がモロッコの領土内のものであるかのように示唆している。これは、日本の外交政策と異なるメッセージを国内外に発信していることになり、国際社会における日本の立場に混乱を招く可能性を秘めている。
 西サハラ・ダーフラ港で荷揚げされるタコとモンゴウイカ、日本との貿易を示す
西サハラ・ダーフラ港で荷揚げされるタコとモンゴウイカ、日本との貿易を示す
まとめ
日本国内における西サハラに関する情報には、政府機関や関連団体によって発信されるものを含め、誤解を招く記述が散見される。特に、国際協力イベントのクイズやJICAの公式声明が、西サハラ産水産物の出自について不正確な認識を広めている現状は看過できない。日本政府がモロッコによる西サハラの領有を公式に認めていない以上、こうした情報の齟齬は、外交上の矛盾を生み、日本の国際的な信頼性にも影響を及ぼす可能性がある。西サハラの現実を正確に理解し、透明性の高い情報発信を徹底することが、今後の国際社会における日本の役割を果たす上で極めて重要である。
参考資料
- グローバルフェスタJAPAN2024公式サイト
- JICA公式サイト
- JICA公式Xアカウント
- アジアプレス・インターナショナル





