現在、日本で60歳を過ぎても働き続けるシニアが急増中。かつての「60歳定年」はなく、緩やかな「フェードアウト」の時代です。ジャーナリスト若月澪子氏の著書『ルポ 過労シニア』は、彼らが自身の生活だけでなく、より深刻な社会問題のために働き続ける実態を明らかにしました。
高齢化社会と労働の変化
日本では60代以上の多くが働いています。社会保障や経済変化が背景ですが、若月氏の取材は「子育てが終わらない」という深層を掘り下げました。シニア労働者は社会を支える不可欠な存在でありながら、脇役へと変化しています。
『ルポ 過労シニア』が暴く実態
本書は21人のシニアへのインタビューを通じ、労働動機や現場の問題点を報告。日本の労働現場でシニアの地位は低く、仕事の選択肢も限られ、賃金も低く、健康不安を抱えながら働く人も少なくありません。
筆者は当初、動機を「低年金」と考えていましたが、取材で衝撃を受けたのは、60歳を過ぎても「子育てが終わらない」現状から、働き続けざるを得ないシニアの急増でした。
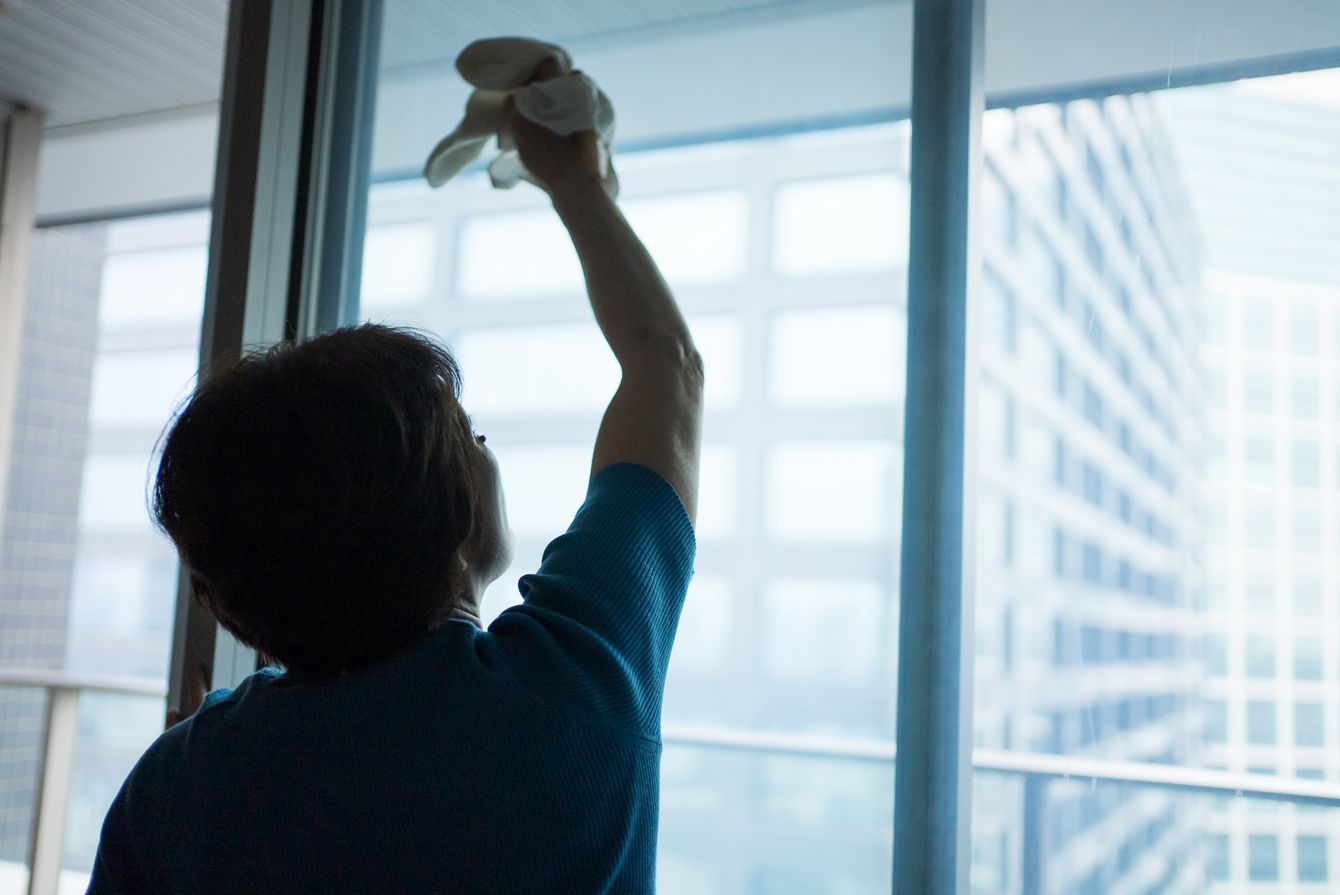 働き続けるシニアのイメージ
働き続けるシニアのイメージ
「子育てが終わらない」という現実
若月氏が最も衝撃を受けたのは、成人した子どもが経済的に自立できない、または「ひきこもり」状態にあるなど、家族内の深刻な問題から、60歳を過ぎても働き続けなければならないシニアの急増でした。親世代が老後資金だけでなく、成人した子どもの生活費まで負担する状況が、シニア労働の長期化を招いています。
ひきこもりの子どもを支える親たちの声
具体的な事例として、ある60代女性は成人した息子がひきこもり、生活費のため60歳過ぎて清掃を始めました。別の70代女性は、中学校からひきこもりの40代息子がおり、家庭内トラブル回避のため今も会社で庶務を続けています。これらはシニアの見えない重荷を浮き彫りにします。

深刻化する日本の「ひきこもり」問題
日本で「ひきこもり」問題は深刻度を増しています。厚生労働省は「社会的参加を避け、原則6カ月以上にわたり概ね家庭にとどまる状態」と定義。内閣府の2022年調査では、全国に146万人のひきこもり状態の人が判明。高齢の親と同居する独身の子どもの割合も増加傾向にあり、高齢者労働の主要な動機となっています。
結論
日本の高齢者労働が急増する背景には、経済的理由だけでなく、成人した子どもの「ひきこもり」という複雑な家族問題が深く関わっています。「子育てが終わらない」現状に直面しながらも働き続けるシニアの姿は、現代日本が抱える新たな課題を浮き彫りにしています。この問題への理解と、高齢者およびその家族への多角的な支援が社会にとって喫緊の課題と言えるでしょう。






