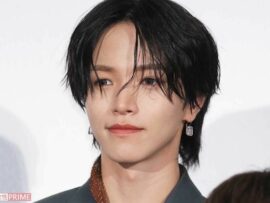幕末期に京都の治安維持を担ったことで知られる新選組は、戊辰戦争以降「逆賊」の汚名を着せられました。しかし、彼らの活動の背景には、将軍や天皇をも守るという崇高な目的があり、局長の近藤勇もまた、幕府に仕えながら強い尊王精神を抱いていました。一体なぜ、江戸近郊の多摩地区の農民出身者が中心となってこの組織が形成されたのでしょうか。そこには、意外なことに一人の指名手配犯が深く関わっています。歴史評論家、香原斗志氏の分析に基づき、新選組の設立と多摩出身者たちの役割に迫ります。
「逆賊」の汚名と新選組の真の目的
新選組は、戊辰戦争の初戦である鳥羽・伏見の戦い以降、新政府軍に抵抗したとして「逆賊」の烙印を押されました。しかし、本来の彼らの役割は、激動の京都の治安を維持し、徳川将軍だけでなく天皇をも守護することにありました。局長である近藤勇も、幕府の要職にありながら、その心には人一倍強い尊王の精神を宿していたと言われています。この「逆賊」という評価は、当時の複雑な政治情勢と時代の理不尽さを色濃く映し出しています。新選組の歴史を紐解く上で、彼らの行動が持つ真の意図を理解することは不可欠です。
清河八郎と浪士組結成の裏側
新選組の母体となった浪士組の構想は、近藤勇ではなく、旗本の松平忠敏と、出羽国庄内藩出身の尊王攘夷派浪士、清河八郎によって練られました。文久2年(1862年)10月、清河の申し出を受け、松平忠敏が幕府に諸国の浪士を登用するよう建言したことが始まりです。
 近藤勇:新選組局長の肖像画
近藤勇:新選組局長の肖像画
驚くべきことに、この時すでに清河八郎は幕府から指名手配されていました。彼は熱心な尊王攘夷運動家として、万延元年(1860年)にはアメリカ公使館通訳官ヒュースケンを暗殺し、翌文久元年(1861年)には尊王攘夷結社「虎尾会」を結成。さらに同年5月には町人を斬り捨てており、幕府に追われる身だったのです。
松平忠敏は、このような状況下で幕府に対し「浪士を放置すれば騒動につながるが、彼らを組織し、意見を聞き、優秀な者を登用すれば人心は幕府に帰する」と建言しました。尊王攘夷派の浪士たちの扱いに手を焼いていた幕府は、忠敏のこの建策に乗り、清河の赦免を強引に推し進め、身分や家柄に関係なく誰もが志願できる浪士組が結成される運びとなったのです。
多摩の武芸者たちが新選組へと集う理由
松平忠敏が浪士取扱頭取となり、清河八郎の赦免が実現したことで、地域や身分、家柄にとらわれない浪士組の結成が決定しました。この動きに、近藤勇が深く関わることになります。彼は、将軍の上洛警護が浪士募集の目的であると聞き、直ちに参加を表明しました。この募集に応じたのは、江戸近郊の多摩地区出身、主に農民階級に属する武芸の達人たちでした。
多摩郡小野路村(現在の東京都町田市)には、名主階級の小島鹿之助という人物がいました。彼は近藤勇の義父となる天然理心流三代目の近藤周助に入門しており、四歳年下の近藤勇とは義兄弟の契りを結んでいた間柄です。鹿之助は近藤らが京都へ上洛した後も、近藤や土方歳三らの相談相手として手紙のやり取りを続けました。京都から送られた近藤らの情報は、正確かつ詳細を極め、新選組の内情を知る上で貴重な史料となっています。
浪士組への応募にあたり、文久3年(1863年)1月、まず土方歳三が鹿之助のもとを訪れて刀を借り、続いて近藤勇が鎖帷子を借りました。さらに沖田総司や山南敬助も小島家を訪れるなど、多摩出身の主要メンバーたちは、応募前に地元名士への挨拶や準備を怠りませんでした。
激動の幕末と天然理心流の広がり
彼らが間もなく京都へ向かうことになりますが、なぜ将軍や御所を警護する浪士組に、多摩地区の農民出身者がこれほど多く集まったのでしょうか。
その背景には、嘉永6年(1853年)6月3日のペリー来航以降、250年続いた徳川幕府の平和が大きく揺らぎ、全国的に治安が悪化した社会情勢がありました。国論は攘夷論と開国論に二分され、激しい議論が交わされる中で、その対立に暴力が伴うようになっていったのです。
こうした激動の時代を受け、農民たちの間でも、自衛の手段として武術の稽古を行う者が増えていきました。彼らが学んだ武術の一つが、特に多摩地区で盛んに行われていた天然理心流でした。例えば、文久元年(1861年)1月15日と16日には、小野路村にあった前述の小島鹿之助の道場に、近藤、土方、山南、井上源三郎といった面々が稽古に赴いています。翌文久2年(1862年)にも、近藤が7回、土方が4回、沖田が6回、山南が1回、小野路村に出稽古に訪れるなど、彼らの武術への熱心な取り組みが記録に残っています。多摩の地で培われた武芸が、彼らを新選組へと導く大きな要因となったのです。
結び
新選組は、戊辰戦争後の「逆賊」という評価とは裏腹に、幕末の京都において治安維持と将軍・天皇の護衛という重要な役割を担っていました。その結成には、松平忠敏と指名手配中の清河八郎の画策があり、激動の時代背景が多摩地区の農民出身の武芸者たちを浪士組、ひいては新選組へと駆り立てたのです。特に、多摩地区で盛んだった天然理心流の存在は、近藤勇をはじめとする彼らが京都で活躍するための確固たる基盤となりました。新選組の物語は、単なる戦闘集団の歴史ではなく、社会情勢、個人の信念、そして偶然が複雑に絡み合った人間ドラマとして、現代に語り継がれるべきでしょう。
参考文献
- Yahoo!ニュース(PRESIDENT Online提供):香原斗志「多摩地区の農民出身者が中心になった「新選組」には、一人の指名手配犯が大きく関係している」
https://news.yahoo.co.jp/articles/7736ec0f82d20e000835dbd37a8c6349feeb3ea1