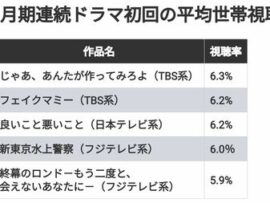10月に入り、八丈島を含む伊豆諸島南部では、線状降水帯の形成による80mm以上の大雨が度々観測されている。特に10月9日には台風22号が直撃し48時間雨量489mmを記録。その後も台風23号が襲来するなど、日本の南の海域では記録的な気象現象が続いている。これまで、日本に接近・上陸する台風は、フィリピン沖などの熱帯海域で発生し、沖縄から九州・四国方面へ進むのが一般的だったが、今年は台風19号や22号が日本近海、具体的には小笠原沖で発生するという異常な傾向が見られる。
日本近海で台風が発生する「異常事態」の背景
慶應義塾大学の宮本佳明准教授は、台風の進路について「太平洋高気圧の縁を回って進むのが基本」と解説する。しかし、日本近海で発生した台風は、この大きな流れに乗ることができず、予測が難しい進路を辿り、関東地方に上陸する可能性も指摘されている。このような日本近海での台風発生の増加は、近年の異常気象の一環として注目すべき事態だ。
「平年+3度」の異常海水温が台風を凶暴化
なぜ日本近海で台風が発生するようになったのか。その鍵を握るのは「海水温の異常上昇」である。宮本准教授によると、台風は海から水蒸気を獲得し、それを巨大な積乱雲の塊に変えて成長する。かつての日本近海は海水温がそれほど高くなく、台風を形成する十分な水蒸気が供給されにくい環境だった。
ところが、今年は日本近海の海水温が、場所によっては平年値より3度も高くなっている。海水温が3度上昇することは極めて重大な事態であり、海が膨大な熱エネルギーを蓄え込んでいる証拠だ。これにより、日本近海でも大量の水蒸気が発生し、台風が発生・発達しやすくなったと考えられる。台風発生の目安とされる海面水温27度以上に対し、今年の日本の南の海面では広い範囲で30度以上が記録されていた。この海水温上昇の一因として、熱帯地域の海の温暖化によって黒潮の温度が上昇し、それが日本近海に影響を及ぼしている可能性も挙げられている。
勢力を保ったまま上陸する「殺人メガ台風」の脅威
日本近海で発生する台風の最も恐ろしい点は、その勢力が衰えることなく上陸する危険性にある。かつてフィリピン沖などで発生した台風は、日本に接近する頃には勢力が弱まる傾向にあった。しかし、日本近海で発生した台風は、高い海水温のエネルギーを吸収し続け、上陸時にも強大な勢力を保つ可能性が高い。
実際、台風22号は八丈島に最大瞬間風速54.7m、総雨量500mm以上の記録的な大雨をもたらし、甚大な被害を与えた。過去にも、2023年7月の台風8号が沖縄県南大東村に580mm、北大東村に531mm、同年にも台風2号が静岡県浜松市で500mm以上の大雨を記録している。
 伊豆諸島への特別警報発表を受け、台風22号について記者会見を行う気象庁の担当者
伊豆諸島への特別警報発表を受け、台風22号について記者会見を行う気象庁の担当者
首都圏・関東地方への500mm超豪雨と河川氾濫リスク
このような規模の台風が首都圏を直撃する可能性について、宮本准教授は警鐘を鳴らす。たとえ都市部での降水量が500mmに達しなくても、山間部でこれほどの雨が降れば、上流から大量の水が押し寄せ、都市部の河川が氾濫する事態は十分に考えられる。日本近海で発生した台風が関東の山間部に500mm級の大雨をもたらした場合、荒川や多摩川といった主要河川が氾濫し、水は低地や地下へと流れ込むため、地下空間にいる市民の命にも危険が及ぶ可能性があると指摘している。
結論
日本近海の異常な海水温上昇は、台風の発生場所や進路、そしてその勢力に深刻な影響を与え、これまでの常識を覆すほどの「凶暴化」を招いている。特に首都圏を含む関東地方は、勢力を保ったまま上陸する台風や、山間部での豪雨による大規模な河川氾濫のリスクに直面しており、これまで以上の警戒と、新たな災害への備えが急務となっている。気候変動による異常気象が常態化する中、正確な情報に基づいた適切な行動が、私たち一人ひとりに求められている。
出典
海水温「平年+3度」の異常事態…:ヤバい! 凶暴化を続ける台風の連続上陸が… (FRIDAY) – Yahoo!ニュース