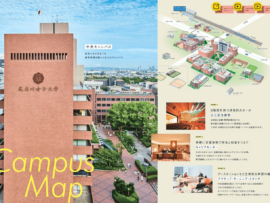厚生労働省が発表した最新のデータによると、今年のインフルエンザは例年になく早いペースで感染が拡大しています。10月17日時点で、定点当たりの報告数は前週の1.5倍に増加し、全国の報告数は9千74件と、昨年の同時期(4千391件)を大きく上回る状況です。例年より1ヶ月以上早い10月3日には全国的な流行期入りが宣言されており、記録的な猛暑や、大阪・関西万博に伴う外国人観光客の増加などが背景にあると指摘されています。
記録的猛暑と外国人観光客増加が背景か:例年より1ヶ月以上早い流行入り
今年のインフルエンザの流行は、専門家も驚くほどの早さで到来しました。過去にない長期にわたる酷暑が人々の体力を奪ったこと、そして水際対策の緩和により、海外からの訪問者が大幅に増加したことが、ウイルス拡散の一因として挙げられています。このような複合的な要因が、季節性インフルエンザの流行期を例年よりも大幅に前倒しにしたと考えられています。
現場の医師が語る流行の現状と今後の見通し
いとう王子神谷内科外科クリニック院長の伊藤博道医師は、現在の流行状況について以下のように警鐘を鳴らします。「当クリニックでは、例年より早く7月から子供を中心に感染者が出始めました。8月は増減を繰り返していましたが、9月に新学期が始まると再び子供の感染が増加。10月に入ってからは大人の感染者も増加しており、現在は週に20人程度の陽性者が出ています」。
伊藤医師は今後の見通しについても懸念を示しており、「昨年は11月から感染者が増えはじめ、12月前半の寒波でドカンと急増しました。現時点ですでに昨年より陽性者が多い今年は、寒波の到来と共に昨年以上に増える可能性もあるため、注視しています」と語っています。このままでは、昨年を上回る規模の感染拡大となる恐れがあるため、警戒が必要です。
昨年過去最高の患者数:今年はさらに深刻化の懸念
昨年は、12月23日から29日の1週間でインフルエンザ患者報告数が31万7千812人に達し、現在の集計方法になって以来、過去最高を記録しました。しかし、今年のインフルエンザは、すでに昨年以上のペースで推移しています。これから低温・低湿度のウイルスが生存しやすい気候になっていく過程で、その数字が40万人、50万人と更新されても決しておかしくない状況であり、医療体制への負担も深刻化する可能性が指摘されています。
異例の拡大要因:「隠れインフルエンザ」の正体とその危険性
今年の異例な感染拡大をもたらしている要因の一つとして、「隠れインフルエンザ」の存在が挙げられます。伊藤医師は次のように説明します。
「インフルエンザというと、一般的に、強い倦怠感や38度以上の高熱、頭痛や関節痛などの症状をイメージしますが、この秋の段階で陽性者に多く見られる症状は、熱も37度台前半で、咳や咽頭痛がある程度。検査をしなければ、普通のかぜと診断されるような患者が少なくないのです」。
この「隠れインフルエンザ」は、高熱を伴わないため軽視されがちです。例えば、家庭内で子供の感染者が出た場合でも、大人が寝込むほどではないと自己判断し、市販薬を服用しながら出勤して周囲に感染を広げてしまうケースも少なくないといいます。
 インフルエンザの咽頭痛と咳症状が強い傾向
インフルエンザの咽頭痛と咳症状が強い傾向
治療の遅れが招く重症化リスク:肺炎、気管支炎、脳症、そして遷延する咳喘息
初期症状が軽いからといって、決して「軽いまま終わるとは限らない」点が大きな問題です。伊藤医師は、「感染初期に抗インフルエンザ薬を服用すれば、ウイルスの増殖をある程度防ぐことができます。しかし、治療開始が遅れると、こじらせて肺炎を併発したり、咳症状が悪化して気管支炎になったりする恐れがあります」と警鐘を鳴らします。
特に子供の場合、インフルエンザ脳症を引き起こし、記憶障害が残るケースも報告されています。また、当院の患者さんの中には、回復後も咳喘息の症状が続き、長期間にわたる通院が必要となる人もいるとのことです。本人が軽症で済んだとしても、誰かに感染させた場合、その相手が重症化するリスクも考慮する必要があります。
複数感染症の同時流行「相乗悪化」の懸念
さらに気がかりなのは、ここ数年、新型コロナウイルス感染症だけでなく、さまざまな感染症が同時流行する傾向にあることです。これにより、単独の感染症よりも重篤な症状を引き起こす「相乗効果ならぬ相乗悪化」を招きかねないという懸念も示されています。複数のウイルスが同時に体内で活動することで、免疫系に過度な負担がかかり、深刻な健康被害に繋がりかねません。
今年のインフルエンザは、その初期症状の軽さから「ただの風邪」と誤解されやすく、知らないうちに感染を広げてしまう危険性をはらんでいます。少しでも体調に異変を感じたら、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な検査と早期治療を受けることが、自分自身と周囲の人々の健康を守るために極めて重要です。手洗いやマスク着用といった基本的な感染対策を徹底し、この異例の流行期を乗り切りましょう。