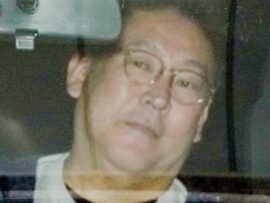閉幕から一ヶ月が経った大阪・関西万博は、開催前の「建設費が高すぎる」「チケットが売れていない」といった批判的な声を覆し、最終的な来場者数は当初予想を大きく上回る2500万人を記録しました。多くの人が「ミャクミャクロス」となるほど魅了され、その成功はまさに「予想以上」と言えるでしょう。今回の万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、多様な「いのち」のあり方を提示しました。
 京都大学の佐野真由子教授が大阪・関西万博について語る
京都大学の佐野真由子教授が大阪・関西万博について語る
佐野真由子教授が語る「万博の真価」
京都大学大学院教育学研究科の教授で「万博学研究会」を主宰する佐野真由子氏は、開幕前の広報が「真面目な話をすれば国民は興味をなくすだろうと考えていたのかもしれませんが、仮にそうだとしたら、国民をバカにしている」と指摘します。しかし、自身29回も会場に足を運んだ佐野教授は、「実際に自分の目で見ると素晴らしいものがたくさんあった」と語り、万博の真価はその多様な展示にあったと評価しています。
各国のパビリオンに見る「いのち」の解釈
「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマのもと、各国のパビリオンでは独自の視点から「いのち」の営みが表現されました。
オマーン館:水が繋ぐ生命の営み
例えば、オマーンのパビリオンは、灌漑水路を模したデザインが特徴的でした。佐野教授は、「水を引くということが、彼らにとって生命維持につながる問題であると考えさせられました」と述べ、水が生命の根源であることを改めて認識させられたと語ります。水の重要性は他のパビリオンでも多く扱われ、それぞれの国にとっての「いのち」の基盤が示されました。
チリ館:少数民族文化と生命の尊重
チリ館では、少数民族の女性たちが作る伝統織物のタペストリーで屋内に屋根が作られ、その下で様々なイベントが行われました。「少数民族の文化を尊重し、継承すること。それを『いのち』の営みと重ね合わせているのではと思いました」と佐野教授は分析し、文化の継承が「いのち」の多様な側面であることを示唆しました。
ポーランド館とクウェート館:芸術と資源が示す生命観
ポーランドのパビリオンでは、ショパンの楽曲と現代アートが融合した展示を通じて、芸術を享受することが「いのち」の問題として捉えられました。一方、クウェートでは石油発見以前と以後の歴史が明確に区別して紹介され、「石油ありきの『いのち』だということが赤裸々に伝えられて、非常に興味深く見ました」と佐野教授は語ります。これらの展示は、国や文化によって「いのち」の定義や価値観がいかに異なるかを浮き彫りにしました。
期待と不安を超えた「いのち」の多様性
大阪・関西万博は、開幕前の期待と不安が入り混じった状況から一転、来場者に「いのち」を巡る問題の多様性を提示する場となりました。当初の批判にもかかわらず、実際に体験することで得られた感動と学びは大きく、万博が持つ真の価値を再認識させる結果となったと言えるでしょう。