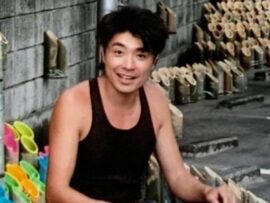10月末、あるファミリーYouTuberの配信動画が「児童虐待ではないか?」という疑惑の目に晒されました。妻が夫に対し「結婚するとき、連れ子邪魔じゃなかった?」と質問し、夫が子どもたちの前で「邪魔だったかもね」と答えたことが問題視されたのです。彼らは後に警察の訪問を告白し、発言は「ネタ」だったと釈明しましたが、批判は収まらず活動休止に追い込まれました。この一件は、SNS上で当事者不在のまま、発言が児童虐待に該当するか否かの議論を巻き起こしています。しかし実際には、保護者からのネグレクトやハラスメントを受けながらも、「児童虐待」の正式な定義には当てはまらないために見過ごされがちな「虐待未満」の子どもたちが、社会には少なくないのが現状です。彼らの精神的苦痛は可視化されにくく、支援の手が届きにくいという深刻な問題があります。
表面化しない心理的虐待の実態
自身の幼少期を「暴力こそ受けませんでしたが、あからさまに邪魔者扱いされて毎日辛かった」と振り返るのは、佐伯美和子さん(仮名・21歳)です。彼女が中学生の頃まで、6人家族で2DKのアパートに住んでいました。父親はビルのメンテナンス業の深夜勤、母親はクリーニング店でパートをしており、佐伯さんには3歳上の姉と2歳下の弟がいました。
一般的な家庭にある門限とは異なり、佐伯さんの家には「逆門限」という独特なルールがありました。午後6時まで父親が寝ているため、子どもたちはその時間まで家に戻ってはいけないというものです。そのため、台風の日や冬の寒い日でも、佐伯さんと姉、弟は駅の待合室やスーパーの階段で時間を潰すことを余儀なくされていました。
佐伯さんたちが帰宅し、父親が仕事のために家を出るまでのわずか30分間も、家族団らんとは無縁だったと言います。基本的に無口な父親でしたが、口を開けば「お前らがいなければなぁ」「あと何年で自立するんだ」といった言葉をこぼすのが常でした。毎日こうした言葉を浴び続けることで、佐伯さんは「生きていてはいけない人間なんだ」「ここにいてはいけないんだ」という絶望的な気持ちになっていったそうです。母親は子どもたちには優しい人でしたが、それ以上に父親に支配されており、「お父さんの迷惑にならないようにね」が口癖でした。このような家庭環境から、佐伯さんの兄と姉は中学を卒業するとすぐに就職の道を選びました。
 精神的に追い詰められながらも社会からの救いの手が届かない「虐待未満」の子どもたちは少なくない
精神的に追い詰められながらも社会からの救いの手が届かない「虐待未満」の子どもたちは少なくない
「邪魔者扱い」が与える心の傷
父親からの「邪魔者扱い」は、佐伯さんの心に深い傷を残しました。「ここにいちゃダメなんだ」という感情は、自己肯定感の低下や孤独感を増幅させます。こうした精神的な苦痛は、身体的な虐待とは異なり表面化しにくく、第三者から見過ごされがちです。しかし、子どもにとっては常に精神的な重圧がかかる養育環境であり、その後の人格形成や社会生活にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
佐伯さんのケースのように、保護者からの露骨な拒絶や存在の否定といった心理的虐待は、子どもの成長に深刻な影を落とします。公式な児童虐待の定義には合致せずとも、子どもが受ける精神的ダメージは計り知れません。これらの「虐待未満」の子どもたちは、児童相談所や公的機関による介入が難しいケースも多く、社会からの支援が届きにくいという課題に直面しています。
認識を深め、支援の網を広げる必要性
「虐待未満」の子どもたちが抱える精神的苦痛は、決して軽視できるものではありません。彼らは、家庭内での不健全なコミュニケーションやネグレクト、ハラスメントによって日々心を蝕まれていますが、その状況は外部からは見えにくいのが実情です。形式的な定義に囚われず、子どもの心の声に耳を傾け、些細なサインも見逃さない社会の目が求められます。このような子どもたちを孤立させないためにも、地域社会や学校、そして私たち一人ひとりが彼らの存在を認識し、適切な支援へと繋げるための理解を深めていくことが喫緊の課題と言えるでしょう。