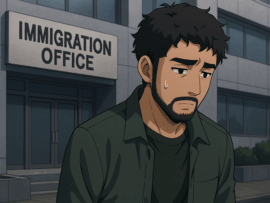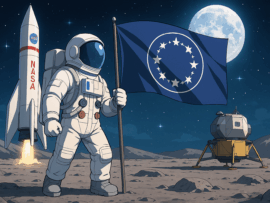[ad_1]
東日本を中心に大きな被害をもたらした昨年10月の台風19号による豪雨は、積乱雲を形成しやすい大気の層が台風に伴って東日本に流れ込み、次々と積乱雲が発達したことが原因となったとする研究成果を、京都大防災研究所の竹見哲也准教授(気象学)らの研究グループがまとめ、21日、国際学術誌に発表した。
台風19号は、東日本を中心に記録的な大雨を降らせ、神奈川県箱根町では観測史上最多となる雨量を記録。今月19日に「令和元年東日本台風」と命名された。
研究グループは気象庁のデータを用いて、最も雨が多かった昨年10月12日の気象状況を分析。その結果、台風19号の周りは、平成30年7月の西日本豪雨時を上回る大量の水蒸気を含んだ大気に覆われていた上、上空3千~9600メートルの湿度も100%に近い、極めて湿った状況だったことが分かった。
こうした条件では、非常に不安定で積乱雲が発達しやすい「モール」と呼ばれる大気の層が形成されるといい、台風19号周辺では厚さ数キロメートルのモールが分布していたことを確認。モールが関東から東北の山間部に流れ込み、同じ場所で積乱雲を次々と形成したことで、下流域で河川の洪水や氾濫をもたらすほどの大雨を降らせた可能性があるという。
竹見准教授は「過去の豪雨災害とモールとの関係も調べながら、積乱雲が発達する仕組みをより詳しく解明して防災に役立てたい」としている。
[ad_2]
Source link