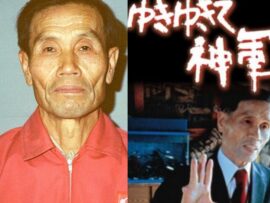「K-POP界隈」「スタートアップ界隈」から「風呂キャンセル界隈」まで、近年“界隈”という言葉の定義が広がっている。若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」所長の長田麻衣は、こうした界隈での消費行動(=界隈消費)が消費トレンドになると予測する。
界隈とは“好き”や興味関心を軸に形成されるゆるい集団のこと。背景には、SNSでのつながりが当たり前になるなかで、2020年代にコロナ禍に入り、個々人でのコンテンツ消費が一般化したことがある。界隈での情報摂取や発信が拡大し、それをきっかけとした界隈消費が生まれてきた。
「界隈は、もっと知りたい・応援したいという“熱量”と気持ちを共有したい・仲間が欲しいという“共感”をベースに発生します。ファンコミュニティよりもつながりの弱い、心地よい距離感のコミュニティです」
目立つのは推し活や趣味にかかわるものだが、それだけでなく、職業や社会的役割などに基づいてSNS上ではさまざまな熱量と共感が集まり、日々界隈が増えている。同社と博報堂の共同調査によれば、決してZ世代だけのものではない。
「自分は何かしらの界隈にいる人だと思う」と回答した人は、10代女性が61%と最多だが、30代でも男女とも25%以上が「YES」と答えている。
長田によると、界隈消費のメカニズムはふたつある。ひとつが、ある界隈のなかでの発信をきっかけに、界隈内で流行する「界隈内消費」。もうひとつが、ある界隈内で起きた流行がほかの界隈に伝播していく「界隈伝播消費」だ。
界隈内消費の一例が、23年にはやった「水色界隈」。水色、白、グレーを基調とし、ジャージやルーズソックスなどのゆるめのサブカルアイテムを好む人たちだ。これは、界隈内で共有されている世界観に共感し、ファッションアイテムを消費する行動に結びついた典型例である。
界隈伝播消費でトレンドにもなったのが「アームカバー」。当初はY2Kブームの影響で、ストリート界隈で流行していたアイテムだが、後にフレンチガーリー界隈などほかのファッション系の界隈にも広がった。このように、近接した界隈同士で“共感”が共有されれば、情報はバイラル的に広がり社会全体で新しい消費トレンドが生まれる。
「調査では、好きなものを集めることが生活の中心となり、消費行動のほとんどが『界隈』に関連しているという生活者の声も挙がっています。界隈消費は個人のライフスタイルに深く根付いた現象なのです」
今後、生活者の嗜好はより細分化し、ますます接点づくりが難しくなっていくことから、企業も「界隈」発想のマーケティングを身につける必要がありそうだ。
「例えばこれまでのファンマーケティングは、企業視点で市場をとらえ、そこに生活者を囲い込む手法でした。
一方で、界隈にアプローチするには、すでに存在する市場に入り込む姿勢が重要です」
つまりこれからの界隈消費時代には、市場を「カテゴリ・商材」ではなく、「生活者の“好き”や興味関心」を軸に考える必要がある。また、ターゲットは企業側が設定するのではなく、すでにある界隈にいる人たちを“見つけに行く”。生活者へのアプローチ方法も、自社のファンを育てるのではなく、その界隈を盛り上げるために自社ができることを提案する、という姿勢をとるべきだという。
「界隈別に、生活者とのコミュニケーションのポイントも異なります。まずは一度、どこかの界隈に参加して楽しんでみてください」
※本記事は、12月24日発売のForbesJAPAN2月号「2025年総予測 トランプ後、世界はこう変わる!」特集内の記事の転載です。
おさだ・まい◎総合マーケティング会社で商品開発・ブランディング・ターゲット設定のための調査やPRサポートを経て、2017年にSHIBUYA109エンタテイメントに入社。マーケティング部を立ち上げ、18年に若者マーケティング機関「SHIBUYA109lab.」を設立。
magazine