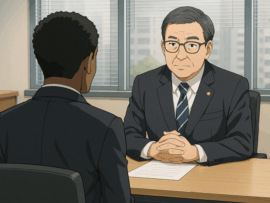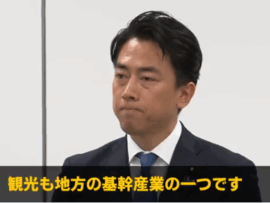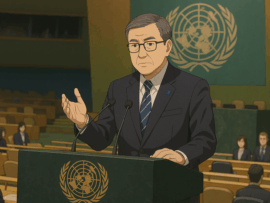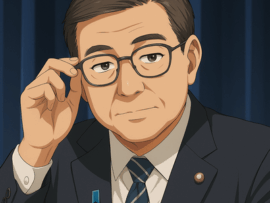[ad_1]
● 「人の不幸でメシを食っている」 週刊誌記者の後ろめたさ
「こんなものは完全に犯罪だろ!」
「仮に不倫をしたとしてもLINEを勝手に公開していいの?」
俳優の永野芽郁さんと田中圭さんの「不倫疑惑」を報じている週刊文春が叩かれている。批判の矛先となっているのは、同誌がおふたりのLINEのやり取りを記事中で紹介していることだ(週刊文春5月15日号「永野芽郁(25)&田中圭(40)燃え上がる不倫LINE」)。
これに関して二人は「このようなやり取りはしていません」と全否定。事実ならば、文春側は虚偽のLINEを世間にバラまいたということになるので罪は重い。このような情報の真偽も含めて、一部の弁護士や評論家が文春を批判をしており、ネットやSNSでも芸能人の不倫をここまで赤裸々に暴くのは公共性もないので「やりすぎ」という声が続出しているのだ。
ご指摘はごもっともだと思う。ただ一方で、週刊誌に長く関わってきた立場から言わせていただくと「もともと週刊誌って、そういうことをやってませんでしたっけ?」というモヤモヤもある。
9年前にタレントのベッキーさんが同じように「不倫LINE」を暴露されたときは「恐るべし、文春砲!」などと拍手喝采され、「ゲス不倫」というタイトルも流行語大賞にノミネートされた。それを思えば、いよいよ「週刊誌」の終焉も近いなという感じがしてしまう。
「文春砲」などと持ち上げられてしまったせいで、多くの人が文春を権力者の不正や理不尽を暴く「調査報道機関」のように勘違いをしているが、実は文藝春秋という一営利企業が発行する「エンタメ雑誌」に過ぎない。
雑誌というものは売れていなくては広告が入らないので存続できないし、取材費も捻出できない。というわけで、とにもかくにも「売れるネタ」が必要不可欠だ。そのためにはプライバシー侵害もするし、名誉毀損も辞さないものなのだ。
しかも、もっと言えば、今回の「LINE暴露」は文春という「エンタメ雑誌」の編集方針的には何十年も続けてきた「王道」路線だ。週刊文春の元編集長の新谷学氏はかつてこのようにおっしゃっている。
「告白」や「告発」も当事者の肉声にこだわっているからですね。「スクープ」も「本誌」も、常に自分たちが誰よりも早く「対象に肉薄する」という姿勢の表れなのです。
事件や出来事の核心をつかみ、生のまま読者にお届けしたい。きれいに加工して特徴のないものにするより、その素材の良さを生かして新鮮なまま届けたいと思っています。(2017年3月8日 ダイヤモンド・オンライン)
テレビや新聞という「報道機関」がよく掲げている「中立公正」「人権の尊重」「社会の公器」なんて美しい言葉はどこにも出てこないことにお気づきだろうか。
相手から訴えられたとき、週刊誌側は訴訟戦略的に「公益性・公共性」というのを持ち出すだけで、別に週刊文春の編集方針にはそんなものは入っていないのだ。筆者も長いことこの世界で働いているので、いろんな編集部員と会ってきたが「このネタは公益性があるのでやりましょう」と言っている人はあまり見たことがない。
これは文春に限らず、すべての週刊誌に当てはまる。もともとこのジャンルは、週刊新潮を創刊した斎藤十一の「君たち、人殺しの顔を見たくないのか」という言葉に象徴されるような、極めてゲスな野次馬根性から誕生した「人間エンタメ誌」なのだ。
そういう出自と新谷元編集長が掲げた「当事者の肉声へのこだわり」という文春の姿勢を鑑みれば、なぜああいう形で、永野さんと田中さんのLINEが晒されたのかも理解できるのではないか。
[ad_2]
Source link