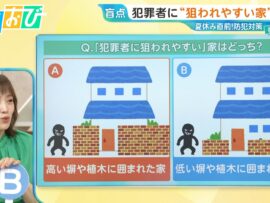大蔵省の官僚として舞台裏にいた人物
1965年5月21日、山一證券の経営状態と再建策が報じられたことで、業界と投資家は混乱に見舞われた。1960年代といえば、東京五輪によるオリンピック景気や高度成長期など、国として活気づいていたイメージがある。しかし実際は、好不況の波に翻弄され、1964年の五輪閉幕後には「昭和40年不況」が始まった。
証券業界の不振はそれよりも前、岩戸景気の終焉時(1961年12月)からだ。1964年1月には株式買い支えの機関として日本共同証券が設立されたが、同年9月期の決算は1社を除いて赤字。中でも拡大路線を推し進めていた山一證券の赤字は大きく、大蔵省の主導で再建策が練られることになった。
山一の深刻な経営状態はメディアも知るところではあったが、大蔵省は大手新聞社に対して計画がまとまるまでの報道自粛を要請。21日に初めて報じたのは、自粛協定外の西日本新聞である。
22日には再建案が発表され、5月28日夜には大蔵大臣の田中角栄氏と日本銀行総裁の宇佐美洵氏(ともに当時)が会見。証券業界への日銀融資や山一への特別融資などを発表する。この経緯や角栄氏の立ち回りぶりは後年にドキュメンタリーなどで明らかにされているが、「週刊新潮」1971年1月9日号は、大蔵省の官僚として舞台裏にいた加治木俊道氏に話を聞いていた。
「山一がニッチもサッチもいかないといい出した」1964年の夏から、再建案のために何回も重ねられたという“隠密会合”。山一再建を強引に推し進めたのは、大蔵省の2、3名の高級官僚でつくられた“作戦本部”だった――。
(「週刊新潮」1971年1月9日号「『山一』特融を決定するまでの大蔵省作戦本部」を再編集しました。文中の肩書き等は掲載当時のままです)
***
2、3名の高級官僚でつくられた“作戦本部”
「四十年五月十九日深夜、大蔵省、日銀は日銀氷川寮に山一証券の取引銀行十八行の頭取をひそかに招き、山一証券再建に関する具体策を協議した。その内容は市中銀行に金利の全額タナ上げ、信託銀行にはその半減を要請するというものだった」(日本経済新聞証券部編『兜町二十年』)
こうして、大蔵省、日銀が銀行側の了承をとりつけると、22日、瀕死の山一証券の再建案が発表された。ところが、この再建案の発表は、逆に「そんなに危ないのか」という感じを一般大衆投資家にいだかせる結果となり、運用預かり証券、投資信託などの解約客が相次ぎ、取付け騒ぎの様相を呈した。
そこで28日、日銀は日銀法25条による無担保、無制限の特別融資に踏み切らざるをえなくなった。これがいわゆる山一特融で、以後、日銀が山一証券に融資した金額は累計282億円。当時、一私企業の経営危機に政府がこれほどまでにテコ入れする必要があるかどうかという疑問、いやこれは一私企業の間題ではなく、日本経済全体に通ずる危難を救ったものであるとする肯定論があった。
そういう賛否両論の中で、この山一再建を強引に推し進めたのは、実は、大蔵省の2、3名の高級官僚でつくられた“作戦本部”だったのである。