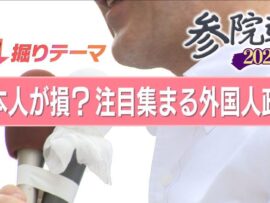救助費用「有料化」議論の焦点
富士山をめぐり、静岡県で遭難救助の有料化をめぐる議論が激化している。
4月、中国籍の大学生男性が富士山山頂付近でアイゼンを紛失したとして救助を要請した。アイゼンとは、登山や雪山歩行の際に靴に装着する金属製の滑り止め具のことだ。山梨県の防災ヘリが出動し救助した。しかし、その4日後、同じ男性が紛失したスマホを取りに行くとして再び富士山に入り、今度は静岡県警の山岳遭難救助隊により救助された。
【画像】「えぇぇぇぇ!」これが4年で108人が死亡した岡山県の「人食い用水路」です 画像で見る(計10枚)
この一連の出来事に、静岡・山梨両県の住民のみならず、多くの関係者が唖然とした。さらにその後も、外国人による富士山遭難が相次いだ。これにより、富士山周辺自治体の我慢は限界に達した。
この問題は、政治的に複雑な背景を抱える静岡県において、一個人の判断だけで解決できるものではない。だが一方で、静岡県全体の総員参加体制を促す契機になる可能性も秘めている。
静岡県知事の「方針転換」
5月22日、静岡県の鈴木康友知事は、富士山の救助有料化に関する検討を関係各局に指示したと発表した。突然かつ意外な発表だった。なぜなら、鈴木知事は同月13日の記者会見で
「(救助有料化は)富士山だけの問題に留まらず、国の法律の問題。県だけの要望で済むとは思えない」
と述べていたからだ。この発言の背景には、静岡県富士宮市の須藤秀忠市長の5月9日の発言がある。須藤市長は
「(遭難者は)いうことを聞かずに勝手に登っている。その費用は莫大なものになり、遭難者の負担にするべき」
と述べ、全国的な話題となった。また、山梨県側の富士吉田市長である堀内茂市長も5月13日の記者会見で、
「まるでタクシーを呼ぶかの如くスマホで救助を要請している。登山客に対して安易に登らないようにと警告を発する意味での有料化だ」
と踏み込んだ発言をしている。鈴木知事の当初の発言は、この両者の意見より一歩引いたものだった。しかし、その約10日後、鈴木知事は大きく態度を変えた。その背景を詳しく探る必要がある。