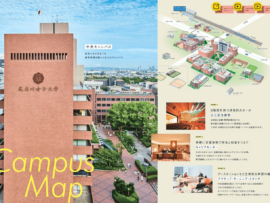和歌山県白浜町にある景勝地、三段壁。太平洋の荒波を望むこの断崖絶壁の駐車場と入り口に、ひっそりと2台の公衆電話が設置されている。ここにかかってくるのは、「生きるのがつらい」「もう終わりにしたい」といった切実な声だ。白浜バプテスト基督教会の牧師である藤藪庸一さんは、26年間にわたり、これらの声に耳を傾け、自ら命を絶とうとする人々を保護する活動を続けている。その数は、これまでに約1100人に上るという。
2人の実子に加え、7人の里子を育て上げた藤藪牧師は、なぜこれほどまでに壮絶な活動を続けることができるのか。フリーライターの川内イオ氏が現地を訪れ、その人生と覚悟に迫った。
三段壁での孤独な活動:1100人の命を救済
藤藪庸一牧師は、人生に絶望し、白浜の三段壁を訪れる人々に26年間、手を差し伸べ続けてきた。白浜バプテスト教会を拠点とする彼の活動により保護された自殺志願者は、年間平均43人、累計でおよそ1100人に及ぶ。これは、文字通り多くの命の危機に日々向き合っていることを意味する。私生活では、自身の子供2人に加え、7人の里親として子供たちを育ててきた。
長年にわたり人助けに奔走してきた藤藪牧師自身の人生もまた、平坦ではなかった。2020年、49歳の時にステージ4のがんが見つかり、全身に転移しているという絶望的な状況に直面した。しかし、すべてのがんを摘出する手術が成功し、驚異的な復活を遂げた。
 和歌山県白浜町の三段壁入口付近に設置された公衆電話と看板。ここから多くの救いを求める電話がかかってくる。
和歌山県白浜町の三段壁入口付近に設置された公衆電話と看板。ここから多くの救いを求める電話がかかってくる。
幾多の困難を乗り越えて:牧師、NPO代表、そして…
がんは克服したものの、現在は抗がん剤の副作用による重い腎不全を患っている。それでも藤藪牧師は活動の手を緩めない。牧師としての働きに加え、自殺志願者を支援するNPOの代表、彼らが社会復帰を目指す場としての弁当店の経営者、学びの機会を提供する通信制高校の教室長、そして児童家庭支援センターのセンター長と、多岐にわたる役割を担っている。
これだけの肩書きを聞くと、光り輝く「聖人」のような人物像を思い浮かべるかもしれない。しかし、実際には違う。藤藪牧師自身、学生時代は「底辺」と言われるような生活を送っており、一度は仕事をクビになり無職のまま結婚した経験もある。牧師になってからも、保護した人たちとの間に激しい衝突を経験し、手痛い失敗や悔しさを何度も味わってきたという。彼の人生は、意外なほどに泥臭く、現実と向き合い続けている。
 長年、三段壁の自殺防止活動に長年従事する藤藪庸一牧師
長年、三段壁の自殺防止活動に長年従事する藤藪庸一牧師
人助けへの原点:「ビルマの竪琴」と「愛は地球を救う」
藤藪牧師は1972年8月、白浜町で公務員の父と保育士の母のもとに生まれた。実家は禅宗であり、キリスト教との直接的な縁はなかった。しかし、小学校1年生の時に近所の姉に誘われて、白浜バプテスト教会の日曜学校に通うようになった。そこでは聖書の話を聞いたり、賛美歌を歌ったり、ゲームやお楽しみ会を楽しんだりと、子供心に楽しい時間を過ごしたという。
小学校の卒業文集には、将来の夢として「牧師」と記した。その大きなきっかけとなったのは、テレビ番組『愛は地球を救う』と、竹山道雄の小説『ビルマの竪琴』である。小学校6年生の時、『愛は地球を救う』で見た、骨と皮だけにやせ細った難民キャンプの子供たちの姿に衝撃を受けた藤藪少年は、自分にも何かできることはないかと考えた。
小銭貯金から学んだ現実と社会貢献への意識
難民の子供たちを助けたい一心で、彼は空き瓶に小銭を貯めて募金することを決めた。しかし、彼が貯金したのは、月300円のお小遣いを好きなだけ使った後に残った1円玉や10円玉だけだった。数カ月かけてようやく貯まった金額は、わずか約600円。
母親に「お小遣いを2カ月我慢すれば、その金額になるね」と言われた時、「貧しい子たちのために良いことをしている!」と胸を張っていた自分が、ひどく恥ずかしくなったという。この時の経験が、藤藪牧師のその後の人生における社会貢献や人助けへの意識に深く根差しているのかもしれない。
まとめ:絶望の淵に立つ人々に光を
和歌山県白浜町の三段壁で、26年間にわたり1100人もの命を救ってきた藤藪庸一牧師。がんとの闘病や自身の過去の苦労など、数々の困難を乗り越えながら、牧師として、またNPO代表として、絶望の淵に立つ人々に寄り添い続けている。彼の泥臭くも力強い生き方は、「聖人」といった言葉では語り尽くせない、真の人間味と深い覚悟に満ちている。三段壁の公衆電話は、今日もまた、誰かの「助けてほしい」という声を受け止めるために、静かにそこにある。
参考資料: https://news.yahoo.co.jp/articles/c038c0b31314d91d8c4c2e0884a2bbf02294d170