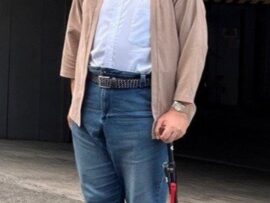道路上で頻繁に見かける光景として、車線を変更しようとする車に対し、意図的に車間距離を詰め、「絶対に入れたくない」という態度をとるドライバーがいます。こうした「進路変更妨害」とも取れる運転行為は、法的に問題はないのでしょうか。多くのドライバーが疑問に思うこの行為について、交通ルールの観点から解説します。
 合流しようとする車と、車間距離を詰めて妨害する車のイメージ。合流時の車間距離不保持は交通違反となる可能性がある。
合流しようとする車と、車間距離を詰めて妨害する車のイメージ。合流時の車間距離不保持は交通違反となる可能性がある。
進路変更の基本ルール:後続車への配慮義務
まず、進路変更を行う側の基本的なルールを確認しましょう。道路交通法第26条の2(進路の変更の禁止)では、車両は進路変更によって、後方から進行してくる他の車両の速度や方向を急に変えさせるおそれがある場合は、進路変更をしてはならないと定められています。これは、円滑な交通の流れを保つための重要な原則です。しかし、特に交通集中による混雑時など、やむを得ず進路変更が必要な状況は少なくありません。
進路変更を「妨害」する運転はなぜ違反となりうるのか
では、進路変更しようとする車を「入れさせない」ようにする行為はどうでしょうか。交通の方法に関する教則「交差点の通行方法」などには、前の車両が右左折や指定された車両通行帯を通行するため等に進路を変えようと合図をしたときは、やむを得ない場合(急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合)を除き、その車両の進路の変更を妨げてはいけないと明記されています。
そして、進路変更しようとする車両を阻止するために、自車の前を走る車との車間距離を異常に詰めて走行し続ける行為は、道路交通法第26条に定める「車間距離不保持」の違反となる可能性が極めて高いのです。進路変更を妨害する意図であったとしても、結果として適正な車間距離を保たない危険な運転は、交通違反として取り締まりの対象となり得ます。つまり、「意地でも入れさせない」という行為は、結果的に別の交通違反を引き起こす可能性が高いと言えます。
円滑な交通のための「譲り合い」と「ファスナー合流」
交通渋滞や混雑時における合流や進路変更は、多くのドライバーにとってストレスの原因となります。NEXCOなどが推奨する「ファスナー合流」のように、合流する側とされる側が互いに一台ずつ交互に進む意識を持つことが、全体の交通の流れをスムーズにし、無用なトラブルや事故を防ぐために有効です。
意地になって他の車をブロックするのではなく、お互いに譲り合う気持ちを持つことが、結果として自分自身の時間的なゆとりにも繋がります。混雑時こそ、冷静な判断と思いやりのある運転が求められます。
「意地でも入れさせない」という運転は、単なるマナー違反に留まらず、車間距離不保持などの交通違反に該当する可能性が高い危険な行為です。交通全体の安全と円滑化のためには、一人ひとりが譲り合いの精神を持ち、特に混雑時の合流などでは思いやりのある運転を心がけることが重要です。冷静な判断とゆとりある運転が、事故防止にも繋がります。
参考資料
本記事は、道路交通法および交通の方法に関する教則等の内容を参考に作成しています。