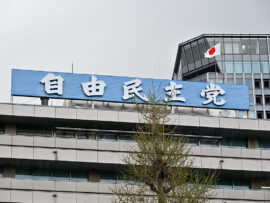6月に発表された厚生労働省の「人口動態統計(速報)」によると、2024年の合計特殊出生率は1.15。前年(2023年)の1.20からさらに低下し、過去最低となったが、ここに立ちはだかっているのが、「結婚する人が減っている」という事実だ。
婚姻数は、1973年から年々減り続け、2024年は一時的には回復したものの、それが長期的な流れを変える兆しにはなっていない。なぜなら、結婚を選ぶ人自体が減り続けているという構造的な問題が、根深く存在しているからだ。
仲人として、婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながらテーマ別に婚活を考えていく連載。今回は、なぜ結婚離れが起きているのかを考えながら、それでも「結婚したい」と思っている人たちがいることを、伝えたい。
■なぜ婚姻率は低下していくのか
いわゆる“結婚離れ”が目に見えて進み始めたのは、2000年代に入ってからなのだが、この数字の裏には、さまざまな社会的背景や、個人の価値観の変化があるように思う。
まず若者が結婚しなくなったのは、結婚に対する価値観の多様化が急激に進んだからだろう。それによって、“結婚=幸せ”の神話が崩れた。
今の20〜30代は、「あなたは、あなたらしく」と言われて育ってきた世代だ。2003年にリリースされ、大ヒットした『世界に一つだけの花』は、まさにその価値観を象徴する一曲だろう。
しかし、結婚は、“自分らしさ”だけでは成り立たない。夫婦関係というのは、お互いの考え方や生き方に歩み寄り、ときにはゆずり合い、受け入れ合いながら、ともに形を作り上げていく営みだ。
また、今は気軽に婚活できるポータルサイトが数多く存在し、選択肢があふれすぎているのも結婚しづらい状況を作っている。
“自分が自分らしくいられる結婚相手”など、本来は存在しえない幻想なのだが、いくらでも出会えるので、それを追い求めて出会いを繰り返していく。そして、結局決められない“婚活迷子”に陥っている。
さらに、経済的な不安定さも、若者たちの結婚にブレーキをかけている要因だろう。
深刻な人手不足に直面しているにもかかわらず、多くの企業が“安くて使い勝手のいい”非正規雇用の労働力に依存している。その結果、非正規雇用者は、将来の生活設計が立てにくく、“婚活して結婚する”という舞台には上がってこない。